「ペンタックスカメラ博物館」が7月31日で閉館 ― 2009年07月02日 00時00分00秒
昨日は更新できなかった。すまん。
遅れてしまったネタだが、触れないわけにはいかない。
「ペンタックスカメラ博物館」が7月31日で閉館(デジカメWatch)
ペンタックスは30日、栃木県芳賀郡益子町の「ペンタックスカメラ博物館」を閉館すると発表した。7月31日で業務を終了する。
約1,000台のクラシックカメラを中心に、国内外の蒐集品を公開していた。1839年頃のダゲレオタイプも所蔵する。
カメラ機材などの収蔵品については、団体への引き継ぎを検討しているという。新たな展開が決まり次第、改めて告知するとしている。
以前、HOYA、カメラ事業を海外移管-益子事業所の一部閉鎖のニュースに関するコメントでペンタックスカメラ博物館の先行きを心配していたのだが、最悪とまでは行かないが悪い方に転んでいるなぁ。
HOYA(ペンタックス)がカメラをやめるというんならそれでもいいかもしれないが、まだカメラ事業続けるんならこの選択はあまりいいとは思えないなぁ。カメラに愛着がないし博物館をおくような国内拠点すらないということなのだろう。
収蔵品は日本カメラ博物館かニコンに引き取ってもらいたい。ニコンを挙げたのは、ニコンはペンタックスと同じくドイツの旧Contaxのピントリングの回転方向や絞りリングの回転方向を引き継いだ仲間だからだ。また、カメラを出している会社の中でニコンはカメラ事業の比重が高いのも理由の一つ。いつかカメラやめそうな会社に引き取られたら貴重な収蔵品が危ない(笑)。
富士SUPERIA PREMIUM 400を使ってみた ― 2009年07月03日 00時00分00秒
富士フイルムが今年3月に発売開始したSUPERIA PUREMIUM 400(スペリアプレミアム400)フィルムを使ってみた。なんか名前がすごい。SUPERIAはsuperior(優れた、上級の、超越した)につながるのだろうし、それにPUREMIUMなんだからものすごいフィルムなのか(笑)。
富士フイルムの写真フィルムは全体に派手目な傾向なので、富士の中では地味目のフィルムを使うことが多い。リバーサルだとASTIA 100F(アスティア100F、略号RAP F)やSENSIA III 100(センシア III 100 、略号RA III)、ネガカラーならPRO 400などだ。一般向けの富士のネガカラーはかなり色が派手なのであまり使わなかった。スペリアプレミアム400はどうだろうか。
SUPERIA PREMIUM 400はそんなに派手な感じではなかった。現像は富士純正には出さずコダック純正処理に出した。いつも使っているヨドバシの富士純正処理(ラボ送り)は、プリントが派手派手でアナログ指定をしてもものすごい色になるし、コダック(ケイジェイイメージング処理)の方が安いのである。その上富士にアナログプリント指定をして出すとデジタルプリントよりも1日余計に掛かる。値段が高くて気に入らないプリントで日にちも掛かるのだから、これはもうコダックに出すしかない(笑)。同じC-41処理なので現像に関して違いはないはずである。それに業界標準はコダックだし。
作例は、ペンタックスOptio W80が気になる ― 2009年06月26日と同じ場所ほぼ同時刻である(花と日の当たり具合が違うが)。
アジサイ:Nikon F100、Ai Nikkor 45mm F2.8P、純正NCフィルター・フードHN-35装着、F11、1/1000sec、富士SUPERIA PREMIUM 400、コダックC-41現像、Nikon SUPER COOLSCAN 5000 ED、ICE・GEMなし
GR DIGITALの作例と違って白飛びや黒つぶれは点々としかない。面倒なのでスキャナが自動でやったままの画像をJPEGに変換圧縮したものだ。スキャン直後のTIFF画像では白飛び黒つぶれはないのだが、JPEGに変換してWEB用に圧縮する過程で所々白飛び黒つぶれが発生した。
SUPERIA PREMIUM 400は富士にしてはそんなに派手ではないし、階調もよく出ているし、人物の顔などもいい感じになっている。肌の感じはコニカの「ポートレート400」や「ほっぺにチュッ」の方が好みだったが、富士のフィルムにしては私の好みに近い。また蛍光灯下でも色被りが少なかった。蛍光灯も色々な種類があるのだが、よくある3種類の昼光色、昼白色、電球色ともに自然な感じに写っていた。これはスペリアプレミアム400の長所だろう。ただ、値段は135-36ex2本パックがヨドバシカメラで税込1440円だった。安かったら常用フィルムにしてばんばん使いたいところなのだが…。PRO 400も5本パックなら税込3650円なので1本あたり730円となり、SUPERIA PUREMIUM 400といい勝負になるが、まとめて買ったときはSUPERIA PUREMIUM 400の方が少し安い。もう少し使ってみないと分からないが、New PRO 400よりもSUPERIA PUREMIUM 400の方が好みかもしれない。SUPERIA PUREMIUM 400は一般受けする派手さとマニア好みの階調の豊富さとの妥協点をうまく調和させている感じがする。粒状性はコダックのポートラ系の方が少ないが、富士の方がフィルムらしい粒状感かもしれない。ポートラはマネキンぽく写ることがあるので。
【関連】
富士フイルム SUPERIA PREMIUM 400 ゲット ― 2009年03月17日
富士フイルム、新設計の「フジカラー SUPERIA PREMIUM(スペリアプレミアム)400」新発売! ― 2008年12月18日
【関連追記;2009年9月25日】
Ai Nikkor 50mm F1.2 + 富士SUPERIA PREMIUM 400作例 ― 2009年09月25日
御岳山にレンタルカメラ店が期間限定で出店 ― 2009年07月04日 00時00分00秒
デジカメWatchによると、日本レンタルカメラが御岳山に期間限定で出店するそうだ。
日本レンタルカメラ、御岳山に期間限定で出店(デジカメWatch)
御嶽山って登ったことはないけど、近くを通ったことは何度もある。これを機会に行くことにするか。それでD3とかD700とか借りて35mmフルサイズデジタル一眼レフを体験なんてよさそうだ。
しかし、日本レンタルカメラのサイトに見に行くとNikon D3とかD700のレンタルはないのであった。D3xもない。高いカメラは元が取れないからなのかなぁ。Canon EOS 5Dはあるけど、1泊2日で16,000円って高いなぁ。1週間も借りたら中古で買えるやん。まあ御嶽山に1週間も行かないのだが(笑)。
レンズにしてみても、高くて買えないが一度は味わってみたいというようなレンズは用意されていない。アマチュア相手だから機材の取り揃えはこんなものなのか。ちょっと残念。というか頑張って買えよということなのだな。
このレンタル店の期間限定出店って面白いので、たとえば上高地にコシナがBessa R4AとCOLOR-SKOPAR 21mm F4Pのセットをレンタルする店を出すとか色々考えられると思うけどなぁ(笑)。
朝日新聞が「鉄道コム」を引き継ぐ ― 2009年07月06日 00時00分00秒
今日はカメラネタでなくてすまん。ぱにー様に言わせれば、カテゴリー「てちゅ」ですな(笑)。
朝日新聞社が「CNET Japan」や「ZDNet Japan」を事業継承(INTERNET Watch)という記事で、鉄道関連情報サイト「鉄道コム」というのがあるというのを初めて知った。
朝日新聞社と米メディア大手CBSのウェブ事業部門であるCBS Interactiveは1日、シーネットネットワークスジャパンが運営するIT専門情報サイト「CNET Japan」および「ZDNet Japan」などの事業を朝日新聞社が引き継ぐことで合意したと発表した。
(中略)
朝日新聞社が引き継ぐのは、「CNET Japan」と「ZDNet Japan」のほか、ゲーム情報サイト「GameSpot Japan」、鉄道関連情報サイト「鉄道コム」など。朝日新聞社は今後、同社が運営するニュースサイト「asahi.com」や情報サイト「どらく」などとの連携を図り、ウェブ事業を強化するという。
朝日新聞はアサヒコムでも鉄道特集というジャンルがあってもともと鉄分が濃い。さらに濃くなるのだろうか。最新のアサヒコム鉄道ニュースで興味深いのは、不正解者は電停に置き去り 阪堺電車でウルトラクイズ。こういうあそび、楽しそうだなぁ。
MARS-101(国立科学博物館):GR DIGITAL、28mm相当、F2.4開放、1/14sec、ISO154、-0.3EV、プログラムAE
MARS(Magneticelectronic Automatic Reservation System)-101は、1963年製造の国鉄座席予約システム。MARSの読みは「マルス」らしい。ちなみに、写っているのは"山海塾状態の石田純一"ではない(笑)。
Microsoft Video ActiveX コントロールの脆弱性により、リモートでコードが実行される ― 2009年07月07日 00時00分00秒
今日は更新が遅れてしまった。それで安易にニュース紹介ネタ。だけれども重要。
Windows XPとWindows Server 2003に非常に危険なセキュリティホールが発見されて、それを利用した攻撃も既に存在しているそうだ。
マイクロソフト セキュリティ アドバイザリ (972890) Microsoft Video ActiveX コントロールの脆弱性により、リモートでコードが実行される
修正パッチはまだないので、Windows XPとWindows Server 2003では以下の回避策をInternet Explorerに適用するか、Internet Explorer以外のブラウザを使用することが推奨されている。
具体的には、http://support.microsoft.com/kb/972890にある「回避策を有効にします」のFix itをダウンロードして、ファイルを右クリックし、[インストール] を選択する。また、Internet Explorer以外のFirefoxやOperaなどのブラウザを使用するのも回避策になる。
【追記:2009年7月8日】
上記のFix itを当てると、Internet ExplorerでYoutubeなどの閲覧ができなくなる。修正パッチが出るまでの間、機能を無効にするものなので仕方ない。しかし、Youtubeを見たいからといって回避策を無効にしたままInternet Explorerを使うのは危険だ。そこで修正パッチがでるまでの間は、FirefoxやOperaで動画等を楽しむのがいいと思う。
Firefox
Opera
【追記ここまで】
【さらに追記:2009年7月9日】
当方の環境ではデフォルトでActiveX無効、Javascript無効にして、特定のサイトのみ許可という設定のために、上記Fixに関係なくYoutubeが見られないようです。結城様ご指摘ありがとうございました。動画やFlashなどのサイトは一切Internet Explorerで閲覧しないために気づかなかったです。(^ ^;
【さらに追記ここまで】
【関連】
Microsoft Video ActiveX コントロール の脆弱性(MS 972890)について(IPA情報処理推進機構)
日本で最初に稼働した電子計算機FUJIC ― 2009年07月08日 00時00分00秒
カメラニュースネタもなさそうなので、おとといの記事の写真のMARSの横に展示されていた富士写真フイルム(現富士フイルム)の電子計算機FUJICとそれに関連した富士フイルムの記事を紹介したい。
写真のFUJIC(国立科学博物館)の説明書きには以下のようにある。
日本で最初に稼働した電子計算機
真空管式計数型電子計算機FUJIC1956年 クロック30kHz 使用真空管1700本
加算0.1ms 除算2.1ms 寄託:早稲田大学レンズの設計には膨大な計算が必要だった。富士写真フイルム株式会社の岡崎文次は、レンズ設計の自動化を考え、7年かけて1956(昭和31)年にFUJICを完成させた。これが日本で初めて稼働した計数型電子計算機となった。計算速度は人出の約2000倍になった。
写真の後ろに見えている突起みたいなのは全部真空管である。1700本あるらしい。実はもう一度国立科学博物館に行ってきたのだが、特別展の開催されていない時期だったので空いていたし、ICカードも借りられたし、色々な意味でよかった。特別展「インカ帝国のルーツ 黄金の都シカン」が2009年7月14日から10月12日まで開催されるので、しばらくまた混雑するのだろうか。
それで、昔のレンズ設計についてインタビューした記事が富士フイルムのマカロニ・アンモナイト内にあるのでリンクしておく。
写真用レンズをつくる人たち 富士写真光機を訪ねて
─── 70年代の当時と今とではコンピュータの演算速度がまったく違うはずですが、レンズ設計に要する時間はどれくらい差があるのですか。
●大野:「劇的に縮まった」と言いたいところですが、実はそれほど差がないのです。
●片桐:昔に比べて設計の条件がより複雑で高度になって、計算の項目が飛躍的に増えていますから。具体的には超小型で薄型のズームレンズの開発などです。
http://ammo.jp/monthly/0301/03.html
インタビュー先の富士写真光機株式会社は、2004年10月にフジノン株式会社に社名変更している
真空管式計数型電子計算機FUJIC(国立科学博物館):GR DIGITAL、28mm相当、F2.4開放、1/18sec、ISO154、プログラムAE、-0.3EV
後藤哲朗氏本人に訊く:ニコンが設立した「後藤研究室」とは(デジカメWatch) ― 2009年07月09日 00時00分00秒
更新が遅れてすまぬ。
後藤哲朗氏本人に訊く:ニコンが設立した「後藤研究室」とは(デジカメWatch)である。謎の「後藤研究室」に迫る(笑)。
たとえばコンパクトデジタルカメラ市場で、ニコンは一眼レフほどの存在感を出せていません。それはなぜなのか?
そ、それはサンヨーのOEM…うわっ誰か来たー(笑)。
「メーカーの開発者の立場で物事を考えると、どうしても作り手側の都合や論理で物事を進めがちになるものですが、カメラユーザーの視点を持って、お客さんが“カメラでこんなことができれば~~”と思う気持ちを達成させるためのことならば、なんでもやっていきます」
えーと、絞りリングで絞りを変えられれば、Aiニッコールレンズで露出計が作動すれば、ファインダーでちゃんとピントの山が見えれば…すごく当たり前のことなんですけど…(笑)。
「写真をあまり撮らず、作品をあまり観ないでカメラを作る人が増えてきた、という感じは受けています。もちろん、きちんと写真を知っている技術者もたくさんいるのですが、カメラやサービスからどんな作品が生み出されているのか。そこを見ていない。そうした意味では(コンパクトデジタルカメラでファンから強い支持を得ている)某社の某カメラには、ニコンの製品がおおいに参考にすべきところもあり尊敬しています」
これって以前カメラグランプリの授賞式で誉めていたリコーのGR DIGITALのことかなぁ(カメラグランプリ 2006贈呈式を開催(デジカメWatch) ― 2006年06月01日参照)。広角単焦点レンズの楽しさ、コンパクトで自分の思ったような設定でさっと撮れるカメラ、学んでくだされ。分かってるんならどうしてD50の時代にAF DX Nikkor 18mm F3.5とか出してくれなかったんだろう。
ミラーのある一眼は、その動作音や振動も含めて撮影する人をその気にさせる精密な機械です。ファインダーの見え味も自然で、長時間カメラを使っても絶対に疲れない。“ミラーのある一眼”は、今後も続いていくカテゴリです
私も光学ファインダー、それもスクリーンに映るタイムラグのない一眼レフの像は素晴らしいと思っている。だからこそ、ファインダーでピントの見えるカメラにして欲しいのだ。小さい像が井戸の底にあってピントがどこに来ているのかわからないようなファインダーなんだったら、ミラーなんかないほうがいい。
デバイスを寄せ集めた単なる電気製品では我々にとっても、カメラ好きのお客さんにとってもよい方向には行かないと思います。ニコンの出番はそこにあるのではないでしょうか
そうそう、色んなレンズを色んなボディに自由に付け替えたいと思う。絞りリングのないレンズはレンズ単体で絞りを変えられないし、古いボディにも使えないじゃない。そんなんでいいの?ボディだけじゃなくて、レンズも電気製品みたいになってるんじゃないかなぁ。全部のレンズが絞りリングやAi連動がないといけないとまでは言わないが(18-55mmとかGタイプでいい)、85mm F1.4とか絞りリング無いと困るよ。絞りリング無くさないでね。
D3シリーズはとても高性能で簡単に撮影できるカメラですが、あまりに大きくて重い。大きくて重いと、人はそれを持ち歩こうと思わなくなります。中級から普及クラスでもそう思っておられるお客様が多いですから、従ってまずはもっとコンパクトなカメラを作る必要があると思います
コンパクトで廉価なFXフォーマットのカメラが登場するんですかねぇ。
「とにかくラインアップを揃えることで一生懸命になってしまいましたが、昨年のD3Xで一応ラインが完成した今、そこには異端児もないと面白くありませんよ。仮にですが、小さくて高性能だけれど、“ある部分”に関しては結構オバカな機種はどうでしょう。でも"別のある部分"はきちんと拘って作り込んでいる。今のニコンのラインナップは当たり前すぎますから、その正常進化を狙うだけでなく、意外性のある異端児も投入するためのアイディアを後藤研究室では練っています」
(中略)
「例えば自分本位ですが、もっと小さく、毎日カバンに入れて使えるカメラを作りたいんですよ。D40はかなりコンパクト化することができましたが、“オジサン”が持ち歩く製品はコンパクトでも多少のステータス性がないと受け入れてもらえません。軽量コンパクトであるところは突出した機能と性能。質感も頗る高い。でも連写はできませんとか、シャッターチャージは手動ですとか。たとえ話であれば、3万円の低価格一眼レフがあって、もっと手軽にラフに使ってもらうことを意識してもいい。いろいろな意味で発想を変えないとダメですよね」
EMみたいなカメラ、デジタルで出すのかなぁ。もうデジタル一眼レフに興味なくなってきたから期待してないけどね(苦笑)。フィルムカメラで出してくれるって言うんなら評価は変わるけど(笑)。
写真は記事とは直接関係ない。
アメ横・摩利支天徳大寺(京浜東北線車内から):GR DIGITAL、28mm相当、F3.5、1/350sec、ISO64、-0.3EV、プログラムAE
GR DIGITAL III は7月27日発表なのか? ― 2009年07月13日 00時00分00秒
金曜日は結局更新できなかった。すまん。今日はなんだか梅雨明けのような天気だなぁ。
さて、GR DIGITAL II の発売から1年半が過ぎたが、後継機の噂がある。2~3年はモデルチェンジしないで行きたいというリコーのアナウンスからすれば今年の後半に後継機が出てもおかしくない。
それで、GR DIGITAL III が7月27日に発表されるという噂は、写真家・そえじまみちお氏の日記に以下のような記述があるのがソースのようだ。
7月8日(水曜日)(中略)
そのGR DITITALも'07年11月22日の発売から既に二年になろうとしていて、後継機の噂が絶えないような昨んですが、このカメラは完成度が高いだけに、後継機に吃驚するような変化を期待するのは難しいでしょうが、どんなカメラが出てくるのか楽しみにしているんですよ。撮像素子が小さいというのが唯一のネックですが、使い勝手は抜群に好く、本筋ではないワイコンを装着しての使い勝手も悪くないんですよね。
はっきりとは言えませんが、後継機に何やら動きがあったような雰囲気が伝わってきていたなと思ったら、昨日、この27日に大森事業所本館ホールで発表をするとの連絡を受けました。
http://homepage3.nifty.com/office-soejima/page7-other.html
おお、なかなか楽しみですなぁ。ワイコンやテレコンの共用を考えたら光学系の変更はなさそうだ。撮像素子や画像エンジンの改良で高感度時のノイズを減らす方向なのだろうか。初代GR DIGITALは高感度のノイズと保護フィルターが直付けできないことと別売防水ケースがないこと以外は不満はあまりないので、そういう「マイナーチェンジ」でも私はいいのだが、世間はどう見るか。
オリンパスのE-P1を触ってきたが、重くて思ったよりも大きいのでこれはGR DIGITALの代わりにはならないなと思った。別のカメラだ。E-P1の展示機はシャッターを押したときの感触もAFが遅くて半押しがわかりにくいので、半押しでタイムラグを減らそうとしたらシャッターを切ってしまったり、逆に押し方が足りなくてAFが作動しなかったりで半押しAFロックが難しかった。シャッターレリーズ時もミラーがあるんじゃないかと思うような振動が手に伝わった。20代半ばのカップルの女性の方が鼻に掛かった声で「これ、欲しー、欲しー」と男性の腕を掴みながら身体をくねくねさせていた(笑)。こういう女の人が好むカメラなのか(笑)。話はそれたが、GR DIGITALの後継機がE-P1ぐらいの大きさになってしまうとGRを名乗るのは難しくなるだろうなぁ。
【関連追記:2009年7月28日】
GR DIGITAL III 発表 ― 2009年07月28日
GR DIGITAL III 妄想 ― 2009年01月19日
Carl Zeiss Camera Lens News Issue 32 ― 2009年07月14日 00時00分00秒
関東地方の梅雨が明けたそうな。最近雨が降らないなぁと思っていたら、もう梅雨明けですか。なんだか完全な夏空という感じでもないですな。
さて、カメラニュースネタもなさそうなので10日も前のCarl Zeiss Camera Lens News Issue 32を紹介してお茶を濁そう(笑)。
Carl Zeiss Camera Lens News Issue 32(zeiss.com)
Camera Lens News Issue 32のフレームの中身だけのURLはこちら。
内容は、
- Light in the Dark: Fort Point San Francisco
- Planar T*1,4/50 ZE - A Standard Lens with a Difference
- Manual Focusing with AF Camera Systems
- New York City Impressions With the Distagon T* 2,8/21
- Your opinion is important to us!
だ。
"Manual Focusing with AF Camera Systems"は、MFカメラでフィルムで撮ればいいんじゃねーの、と突き放しておく(笑)。
写真は記事とは関係ない。
特急くろしお(キハ81)1976年頃:Asahi Pentax SV、SMC Takumar 200mm F4、Sakura Color II、Nikon SUPER COOLSCAN 5000 ED
動画の手ぶれ補正で新技術、撮影済みの動画を後から補正可能 ― 2009年07月15日 00時00分00秒
動画の手ぶれ補正で新技術、撮影済みの動画を後から補正可能(Technobahn)なのだそうだ。
リンク先の動画を見ると、元の動画よりも処理後の動画の方が画角が狭くなっているので、共通して写っている部分を頼りに揃えているようだ。そのため上にブレたときの画像は下の方が写ってないし下の方にブレたときは上の方が写っていないということで、共通して写っている部分だけが抽出されて結果画角が狭くなるのだろう。スチル写真でも手動でできそうな感じだ。ただ、スチル写真のブレは、連続して同じものが画面の同じ位置に写っていないという動画のブレとは別のシャッター幕が開いている間の動きなので、今回の動画のブレと性質が違う。スチル写真でいうとHDR合成(ハイダイナミックレンジ合成)に近い感じか。パノラマ合成の完全一致版みたいな感じか。





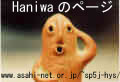

最近のコメント