収差をコントロールする愉悦を「PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8」で味わう(アカギカメラ第122回) ― 2025年07月22日 00時00分00秒
今回の「赤城耕一のアカギカメラ」は第122回:収差をコントロールする愉悦を「PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8」で味わう(デジカメWatch)だ。
今回、紹介するコシナから発売された「PORTRAIT HELIAR(ポートレートヘリアー)75mm F1.8」はユニバーサル・へリアーの登場から100周年を記念するということで、この特性と機能を応用した「球面収差コントロール機構」を装備していることが大きな特徴です。
この球面収差が与える影響を最大限に利用しようと考えたのが「ユニバーサルヘリアー」だったわけですが、球面収差量を撮影者がコントロールすることで、フレキシブルに使えることを目指したのだろうと考えられます。1本のレンズで複数の異なる描写のレンズを使うがごとく使用することができたからです。
もちろんフォクトレンダー以外の他メーカーからも古くから球面収差を生かした、多くのソフトフォーカスレンズは登場していますし、球面収差量を任意にコントロールすることでボケ味や合焦位置の描写を変化させようという試みを行ったレンズは過去にもありました。
現行品でもキヤノンRF100mm F2.8 L MACRO IS USMがSAコントロールリングと称して、球面収差を変化させることを可能とした機能を内蔵しています。
ユニバーサルヘリアーの現代版となった今回の「PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8」は、3群6枚のレンズ構成。いわゆるヘリアータイプを採用しています。Eマウントで、フォーカシングはMFです。
鏡筒は少々太めですが、重量バランスは悪くはありません。フォーカスリングは網目のような細かいローレットが採用され、フォーカスの微調整を行いたい場合は指がかりがよく助かります。収差のコントロールリングはシルバーで、視認性は良好です。
「球面収差量を任意にコントロールすることでボケ味や合焦位置の描写を変化させようという試みを行ったレンズは過去にもありました」として、現行のキヤノンRF100mm F2.8 L MACRO IS USMだけが挙げられているが、ここは、AI AF DC-Nikkor 135mm f/2DやAI AF DC Nikkor 105mm f/2Dを挙げて欲しかったなぁ。
AI AF DC-Nikkor 135mm f/2Dについては、ニッコール千夜一夜物語で大下孝一氏がニッコール千夜一夜物語 第三十二夜 Ai AF DC Nikkor 135mm F2S――ボケ味を追求した中望遠レンズAi AF DC Nikkor 135mm F2Sとして解説している。
さらに、接合の前玉と、その後ろの凸凹レンズの間隔を変化させることによって、非点収差や色収差などを悪化させることなく、球面収差だけをわずかに変化させて、前後のボケ味をコントロールするのである。球面収差は、DCリングがセンター位置にある時にはほぼゼロに補正されており、結果的に収差のバランスは、各収差を極限まで補正した超望遠レンズのバランスに近い。これはDCを効かせない状態では出来るだけ高性能に、かつ前後のボケをできるだけ「素直な」状態にしておくためである。この点が、背景ボケを良好にするため、球面収差をわずかに補正不足に残していた今までの中望遠レンズとは異なる、このレンズの個性となっている。
いかん、いかん。PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8の話なのに、AI AF DC-Nikkor 135mm f/2Dの話になるところだった。
PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8の話の戻すと、ニコンは105mmと135mm(どちらも旧製品)、キヤノンは現行品で100mmと、焦点距離が長めなので、75mmで出してきたのはちゃんと考えているなぁ。
PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8は、希望小売価格(税別)¥150,000で、結構いいお値段なので、 AI AF DC-Nikkor 135mm f/2DやAI AF DC Nikkor 105mm f/2Dの中古がライバルになってしまうかもしれない。
ただ、球面収差の過剰補正のときの後ろボケは、PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8の方は赤城耕一氏も書いているように、かなり癖のあるボケであるのに対して、ニッコール千夜一夜物語のAi AF DC Nikkor 135mm F2Sの方はそうでもない。
さらに、PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8の方は、球面収差が補正不足のときに、ピントの合った面がソフトフォーカスになっているのに対して、ニッコール千夜一夜物語のAi AF DC Nikkor 135mm F2Sの方は、ピント面はしっかりと描写していて前後のボケだけが変わっている。ここは大きな違いだ。球面収差が補正不足のときにソフトフォーカスになるからPORTRAITと付いているのかもしれない。
個人的にはソフトフォーカスよりも、かっちりくっきり針で突いたような描写の方が好みなので、赤城耕一氏にはすまないが、アカギカメラをみてDC Nikkorが欲しくなってしまった。ただ、PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8は、収差のコントロールリングを中立にした場合には、普通にシャープに写るので、ソフトフォーカスレンズにもできるポートレートレンズレンズと考えるとよいのかもしれない。でも収差のコントロールリングを中立のときでも、後ろのボケは好みじゃないんだけど…(泣)。
コシナは、いろいろな高性能レンズを比較的リーズナブルな価格で出してくれる会社なので、DC Nikkorのようなタイプの収差をコントロールできるレンズもいずれ出して欲しい。
あと、ニコンは、ZマウントでDC NIKKORを発売するのだ。
写真は記事とは関係ない。
横浜駅東口:Nikon Z6、SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ、18mm(35mm版換算27mm相当)、絞り優先AE(F6.3固定、1/800秒)、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(5520K)、APS-C(DX)フォーマット、マルチパターン測光、マニュアルフォーカス(MF)距離●2m、ピクチャーコントロール:オート、手ぶれ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、フィルターなし、フード(37mm→30mmと30mm→37mmリング2段重ね)、Jpegをリサイズのみ
SG-image 18mm F6.3、四隅の暗黒がユニークなんだけど、もう少し落ち込みがない方がいいなぁ。ここまで周辺光量が落ち込むと、CornerFixで補正できないのだ。このレンズのシャープさや、MFレンズだけれどもピント合わせもほとんどしなくてさっと撮れるところなどはすごくよいので、もう少しイメージサークルを大きくして(APS-Cのままでよい)周辺光量を緩和したSG-image 18mm F6.3 II とか出して欲しいな。そのときは、レンズバリアーは要らない。レンズバリアーがあると、速写性に劣るので(さっとレンズバリアーを開けられたとしても、ミラーレスカメラのAE機構が安定するまで時間が掛かる)。
色々なレンズがとっかえひっかえ使えるよい時代ですなぁ。
コメント
_ みっち ― 2025年07月22日 14時21分09秒
_ Haniwa ― 2025年07月22日 16時06分16秒
コメントありがとうございます。
いやぁ、暑いですね。
SG-image 18mm F6.3を持ち出したら、レンズバリアが閉まっていてびっくりしました。レンズバリアが閉まらないようにパーマセルを貼ってあったはずなのですが、あまりの暑さに糊がねちゃーとなってパーマセルがずれておりました(泣)。
>AI AF DC-Nikkor 135mm f/2Dは使ってました。これ、見掛けはすごく仕上げが良くて格好いいんです、シボ塗装なんて舐めたくなる(笑)ほどですし、まぁ内蔵のフードがてんで短い以外は、どこも不満のないレンズでした。
よいですねぇ。私も舐めたいです(笑)。
ニコンのある時期までの望遠レンズのフードが短いのはなんとかならなかったんでしょうかねぇ。私も、頂き物のAi Nikkor ED 180mm F2.8Sや、長年愛用のAI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED <NEW>とか、工夫して長いフードを付けて使っています。
>ただですねぇ、当時使っていたD800Eと組み合わせると、軸上色収差が派手に出ちゃうんですよ。(泣)このレンズを買えば、当然開放F2で使いたくなりますが、そうすると前ボケはマジェンタ、後ろボケはグリーンの縁付になってしまいます。やっぱ、フィルムカメラで使うレンズなんだな、と思いました。
>ttps://mitchhaga.exblog.jp/19731192/
あちゃーそういう問題がありましたか。
2013年のブログを拝見しましたが、かなり目立つ軸上色収差ですね。
>こうなると、もう折角のDCコントロールもどこへやら、もちろん、絞込めば解消しますし、CaptureNX2で補正もできますが、そのうち使わなくなって、売却しました。まぁ、今どきのセンサーとの組み合わせだと、どうなるかですけどね。
>
>Haniwa氏が人柱になって、確かめてみてください、万一駄目な場合でも猊下とのハッシ戦で十分役に立つと思います。(笑)
ニコンZ6は、軸上色収差も倍率色収差も補正してくれなさそうなので、AI AF DC-Nikkor 135mm f/2Dを使うと酷い目に遭いそうな気がします。
Ai Nikkor 35mm F2Sは、フィルムやD300・D300Sではなんともなかったのに、Z6で絞り開放で使うとエッジに色づきが出ます。エッジが目立たない被写体でも、にじんだ感じに写ります。これはショックでした。デジタルですと開放時に倍率色収差が目立つようです。
ttps://nij.nikon.com/enjoy/life/historynikkor/0084/index.html
D3やD300では倍率色収差を自動で補正していたのに、おそらくZ6では何の補正もしなくなっているのだと思われます。
ttps://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2008/05/21/8516.html
「倍率色収差補正は必ずかかるようになっていて、補正のON/OFFができませんね。
――ON/OFFできるようにしようという考えも一部ありました。しかし、倍率色収差を好む人がいるとは思えなかったので、敢えてON/OFFできるようにはしませんでした。 」
このような発想の人がもうニコンにはいないのかと思いました。
ここは、ニコンのレンズ設計者が意地を見せて、軸上色収差のないDC NIKKOR Zを設計して欲しいところです。
「作ってもいいですけど、その値段でHaniwaさんは買えるんですか?」というニコンからの、猊下のハッシよりも強い打撃がありそうな気がします(泣)。
ただ、手に入ればAI AF DC-Nikkor 135mm f/2Dは使ってみたいですね。
_ タロウカジャ ― 2025年07月22日 17時18分48秒
超広角もズームで14mmからのズームがあるだけでより広角域の単焦点はありません。
24mmから始まるズームレンズは目白押しですが70mm(50mm)から始まる望遠ズームは高額な70-200mmf/2.8だけで小型軽量な70-200mmf/4とか70-300mmf/4.5-5.6域の望遠ズームがありません。
勿論DCレンズや魚眼レンズもありません。
もう少し協力会社と連携して面白いレンズを発売してくれるといいのですがライセンス契約もなかなか厳しいのですかね。
Zのボディに1-2本のZマウントレンズとFTZⅡか他社のマウントアダプターであまり不自由していないのが実情です。今でもAi135mmf/2.8とかAi24mmf/2.8それとヤシカコンタックス85mmf/1.4は良い感じに撮れています。
お前は、色収差や操作性等を気にしないのかとお叱りを受けそうですね。
ニコンもFマウントレンズに固執している私の様なニコ爺が飛びつくようなZマウントの小型軽量コンパクトな新シリーズレンズを開発発売をしてくれるとうれしいですが市場は世界なのでそうはいかないですよね。
_ Haniwa ― 2025年07月23日 08時51分04秒
>ニコンはZマウントレンズについては基本的な製品の充実に力を入れますがあまり販売数が見込めない製品は出さないようです。
>超広角もズームで14mmからのズームがあるだけでより広角域の単焦点はありません。
単焦点のAI AF Nikkor 14mm f/2.8D EDが最後で、AF-S以降はAF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED(現行品)が最広角ですね。
AI AF Nikkor 18mm F2.8Dは製品ページはありますが、旧製品一覧には載っていないですね。18mmは生産終了が早かったからかもしれません。
AF-S以降、ニコンは超広角はズームでいいと思っているんでしょうね。
ズームは重いので、コンパクトで写りのシャープな超広角レンズの需要はあると思うのですが。
>24mmから始まるズームレンズは目白押しですが70mm(50mm)から始まる望遠ズームは高額な70-200mmf/2.8だけで小型軽量な70-200mmf/4とか70-300mmf/4.5-5.6域の望遠ズームがありません。
これも不満ですよね。70-300mmはタムロンからZマウントが出ていますから、ニコンは出すつもりがないということなんでしょうね。
AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VRも最近生産終了になりましたから、本当にここは穴が開いています。
>勿論DCレンズや魚眼レンズもありません。
魚眼レンズがないのはどうしたものかと思います。
AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED はAF-Sではない唯一のDX NIKKORですが、FTZ等を付けてもZボディではAFが効きません。魚眼レンズでMFはきついと思います。こういうところ、もう長いことニコンは矛盾を孕んだまま来ています。SONYやキヤノンに移行する人が多いのも当然だと思います。
>もう少し協力会社と連携して面白いレンズを発売してくれるといいのですがライセンス契約もなかなか厳しいのですかね。
サードパーティにレンズを作らせないぞ、レンズの儲けは俺たちが独占するんだ、と思っている内に、どんどんユーザーが離れていくし新しいユーザーも獲得できないでいるという状況じゃないでしょうか。
Zのボディに1-2本のZマウントレンズとFTZⅡか他社のマウントアダプターであまり不自由していないのが実情です。今でもAi135mmf/2.8とかAi24mmf/2.8それとヤシカコンタックス85mmf/1.4は良い感じに撮れています。
それでいいのだと思います。ニコンがZで最高性能のレンズを出したいというのは分かりますが、大きくて重くて高いレンズばかりだと手を出しにくいです。
Ai135mmf/2.8はコンパクトでいいですよね。私はAi Nikkor 135mm F3.5を先に買ったのに、F2.8の方も安いのを見つけて買ってしまいました。描写の違いは区別するのが難しいです(笑)。
>お前は、色収差や操作性等を気にしないのかとお叱りを受けそうですね。
>ニコンもFマウントレンズに固執している私の様なニコ爺が飛びつくようなZマウントの小型軽量コンパクトな新シリーズレンズを開発発売をしてくれるとうれしいですが市場は世界なのでそうはいかないですよね。
気にならないときは気になりませんよね。ただ、なんかこのレンズは気に入らないというときは、収差が関係しているのだと思います。私は、NIKKOR Z 28mm f/2.8(Special Edition)の写りが気に入らないのですが、このレンズは色収差が大きくて線が細かく描写されません。非常に不満です。このレンズ一本でスナップに行くぞと思って買いましたが、このレンズ一本で出掛けると、せっかくのシャッターチャンスに線の太い画像が記録されていて不満です。おそらくニッコール28mm史上最低のレンズだと思います。目茶苦茶悪いというわけではないですが、ほかのニッコール28mmがちゃんとしているだけに、単焦点でこの描写は不満です。重くてもNIKKOR Z 24-70mm f/4 S を持って行った方がいいです。ニッコール千夜一夜物語でどなたが設計されたのかどういう経緯でゴーサインが出たのかなど早く書いて欲しいと思っています。
そういう不満がありつつも、ニコンZを選択したのは、センサー前ガラスの厚みが薄くて、対称型広角レンズでも性能劣化が少ないからです。その意味でも今後はコシナVMマウントを増やして行く方向が楽しいのかなとも思っています。
_ めがねのパイロット ― 2025年07月23日 21時38分48秒
このZマウント版が出たら買いたいですね~
DCのZマウント版を作る気があるのか・・・
マイクロズームのZマウント版も70-180でタムロンに譲りましたし・・・
堅実さはあるものの、ラインナップの面白さが欲しいですね、ニコン。
_ Haniwa ― 2025年07月25日 08時31分00秒
コメントありがとうございます。
>このZマウント版が出たら買いたいですね~
>DCのZマウント版を作る気があるのか・・・
>マイクロズームのZマウント版も70-180でタムロンに譲りましたし・・・
>
>堅実さはあるものの、ラインナップの面白さが欲しいですね、ニコン。
そうなんですよねぇ。NIKKOR Zのラインナップやたらと標準ズームが多くて、特殊レンズが少ないんですよねぇ。
DC NIKKORも魚眼レンズもおもしろレンズ工房Zとかも出して欲しいですよね。あと、PC NIKKORもです。余裕ないんですかねぇ。こちらの懐も余裕ないですが(泣)。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。

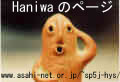

ただですねぇ、当時使っていたD800Eと組み合わせると、軸上色収差が派手に出ちゃうんですよ。(泣)このレンズを買えば、当然開放F2で使いたくなりますが、そうすると前ボケはマジェンタ、後ろボケはグリーンの縁付になってしまいます。やっぱ、フィルムカメラで使うレンズなんだな、と思いました。
ttps://mitchhaga.exblog.jp/19731192/
こうなると、もう折角のDCコントロールもどこへやら、もちろん、絞込めば解消しますし、CaptureNX2で補正もできますが、そのうち使わなくなって、売却しました。まぁ、今どきのセンサーとの組み合わせだと、どうなるかですけどね。
Haniwa氏が人柱になって、確かめてみてください、万一駄目な場合でも猊下とのハッシ戦で十分役に立つと思います。(笑)