FILM&IMAGE Vol.9 ― 2007年09月27日 00時00分00秒
富士フイルムが発行するフィルム情報誌、「FILM&IMAGE」の第9号が届いた。いや、届いたのは1週間前なんだけれどもその日はカメラ雑誌の発売日で、Carl Zeiss Distagon T* 2/28 ZF関連の記事が気になって、その後Nikon Digital Live 2007が気になったり、世界の中古カメラ市に行ってDistagon T* 2/28 ZFを触ったりして、後回しになっていたのだった。フィルム&イメージは、カメラ雑誌の発売日の前に発行すると話題になりやすいと思うんだけどなぁ。
今号は、表紙と巻頭特集が鉄道写真家フォトジャーナリストの櫻井寛氏だ。特集名も「鉄道一直線」。この方はアサヒカメラでも「懐かしのぞっこん鉄道」を連載されているが、鉄道がほんとうに好きなんだなぁ。ご両親が国鉄職員だったことが書かれていた。英才教育なのか(笑)。
他の記事は、
- ツァイス イコン:赤城耕一のフィルムカメラパラダイス第2回
- 丹地敏明さんと「フォルティアSP」:FILMIST列伝5
- 二軍物語:読売巨人軍 大塚淳弘氏
- 秋山庄太郎:モノクローム珠玉の名作選9
- 高橋宣之直伝撮影の秘訣 日暮の森 月夜の森
- チャレンジ!フォト広場:榎並悦子氏
- Q&A「バウンス」ってなんだ
- ようこそ富士フィルムウェブ写真美術館&ショップへ
「赤城耕一のフィルムカメラパラダイス」のツァイスイコン、作例のプロビア100Fで撮ったC Biogon T* 4.5/21 ZMやC Sonnar T* 1.5/50 ZMの空が濃い青でいいなぁ。Biogon T* 2.8/28 ZM(6群8枚)がContax G用のBiogon T* 28mm F2.8(5群7枚)と同じ光学系だったら買うのになぁ。なんで設計変えたんだろう。どこが違うのか分からないが、CONTAX G用のBiogon 28mmは雑誌の印刷でも違いが分かる感じがした。これはいいなぁ、と思うとG用ビオゴンだったのだ。ZMレンズの28mmはそういう感じがじない。レンズ構成の違いというよりは、コーティングやカラーバランスの違いかもしれない。ほかにDistagon T* 4/18 ZMの作例もある。
フォルティアSP、そういえば1本売りしていたので、かなり前に買ったのだった。使わずにすっかり忘れていた(笑)。フォルティアSPはISO50なので、今手持ちのコダクローム(ISO64)を頑張って使っているところなので低感度はコダクローム使うので精一杯なのであった。それに関東地方南部は8月末から晴天の日が少ない。紅葉の時期にフォルティアSP使えるといいなぁ。
どうした?ヨドバシカメラ ― 2007年09月26日 00時00分00秒
コシナとCarl Zeissの渾身の企画、Carl Zeiss ZFレンズに新しくDistagon T* 2/28 ZFが加わるというのに、ヨドバシドットコムのサイトには全然アイテムが追加されていない。他の新製品だと、EOS40DがどうしたとかD3とD300がなんたらとかα700の予約が云々とかパナソニックLUMIX DMC-L10が発表になったとかメールで知らせてくれるのに、コシナ・ツァイスの新レンズはシカトですか?ビックカメラはオンラインショップに載せてるのに。
ツァイス交換レンズ(yodobashi.com)
Distagon T*2/28mm ZF(biccamera.com)
それでやる気なしと判断して、15%引きの価格を表示していた東京・中野の某店で予約したのであった。
コシナ・ツァイスへのやる気の違いだけでなく、ビックカメラはポイントをJR東日本のSuicaに充当できるらしい。
まだあった! Suicaのオトクな使い方(鈴木貴博のビジネスを考える日:日経BP)
上記サイトを見ると、
ソフマップにモノを売る → ソフマップの親会社のビックカメラのポイントとして10%増しで受け取る → それをJR東日本のSuicaにチャージする → Suicaが使えるお店で現金の替わりに使う
これでかなりお得になるようだ。鈴木氏はヨドバシからビックに切り替えたと書いている。
リアル店舗でいえば、私はビックカメラでは色々といやな思いをしたことが何度もあるので、ビックとヨドバシの両方のポイントカードを持っていたのだが、ヨドバシでしか買わないことに決めたのだった。
まあ挙げればキリがないのだが、一番最近いやな思いをしたのは、藤沢に行って時間を調整しなければならなかったので、ビックカメラでカメラを触っていたときのことだ。なぜか触っていないカメラの防犯ブザーが突然鳴り出した。ここでヨドバシなら店員が飛んできて「申し訳ありません」というところなのだが、ビックカメラの場合は店員が全然来ない。何分も鳴りっ放しなのである。その場を立ち去りたいのだが、ここで立ち去ったら怪しい(笑)。仕方ないので、店員が来るまで待っていたのだ。そうしたらようやくビックカメラの店員が嫌そうにやってきて、私を睨んでブザーを停め無言で帰っていくんだな。ああやっぱりビックカメラだ(笑)、と思った。それ以前の不愉快なことは思い出したくもないというか思い出してきたのだが、ここに書いても皆が不快になるだけなので書かない(笑)。
まあ、そんなビックカメラに負けてどうする。Suicaにポイントの充当とかそういうのは、私は構わない。ビックも嫌いだし、JR東日本も鉄道会社として不満があるし、そんなエサで釣られてたまるか、という気持ちもある(笑)。しかし、ディスタゴンはサイトに載せてくれよ(笑)。ヨドバシ「カメラ」なんでしょ。たとえマニアックで全体から見ればわずかな層にしか受けないレンズであっても、ちゃんと扱ってくれ。いや、店舗では扱うのだろうが、ネットにも載せてくれ。yodobashi.comから店舗の在庫確認したりするのにも必要なんだよぅ。
写真は記事とは関係ない。
イネの花:Nikon F3、Voigtlander Macro Apo-Lanthar 125mm F2.5 SL、Kodachrome 200 (KL)、1/250sec、F11、Nikon SUPER COOLSCAN 5000ED
いまはもう黄色く実っているが、今月初めのイネ。白い虫みたいなのがイネの花らしい。
寿命ゼロのメディアが存在するワケ DVDは百年もつか?(3)(日経PC online) ― 2007年07月30日 00時00分01秒
寿命ゼロのメディアが存在するワケ DVDは百年もつか?(3)(日経PC online)
なかなか興味深い記事である。私は、デジカメの画像データはHDDとDVD-RAMに保存しているのだが、この試験結果は不安だ。DVD-RAMは太陽誘電のOEMだといわれているPanasonicのDVD-RAMにしているのだが(一部日立マクセルも使っている)。CD-Rも太陽誘電のものを使っているが、CD-Rは保存用とは思っていない。
しかし、コダクロームも国内販売中止になったいま、撮った写真を長期に保存するのは何が一番いいんだろう。オマエの撮った写真なんかそんなに長く残らなくて結構、というツッコミはなしで(笑)。どんなに下手糞な写真でも、当事者にとっては大事な写真というものはある。
Nikon F100用データバックMF-29はコダクロームの写し込みも濃い ― 2007年06月28日 00時00分00秒

相変わらずタイトル長めですまん。修理中のニコンF100なのだが、修理に出す前にF100にコダクローム64を詰めて撮ったものがあがってきた。普段F100の裏蓋はデータバックMF-29に換えている。というのは、いわゆる家族スナップや記念写真のようなものを撮るときは必ず日付を入れているからだ。これはプリントして人にあげたりするときに日付入りだと喜ばれるし、あとで自分でいつ撮ったものか分からなくなるからだ。日付入りだと喜ばれるというか、デジカメにはExifに撮影の日付時間が記録されるので、いまや日付が入っていないと不評なのだ。ニコンF-501にはMF-19、ニコンF3にはMF-14のデータバックをつけている。
それで、MF-14やMF-19の場合、ネガカラー、モノクロやE-6現像の内式ポジフィルムだとうまく日付が写し込まれるのだが、コダクローム(64、64プロ、200)だけはフィルムの構成が違うからか写し込みが薄かった。データの写しこみというのはフィルムの後ろ側(圧板側=撮影者側)から感光させるので、コダクロームの場合はベースや構成が違うから仕方ないのかと思っていた。まあ、コダクロームでデータ写し込みしてる人ってかなり少数派だろうなぁ。
ところが、ニコンF100用のMF-29で撮ったものはコダクロームでもばっちりくっきりオレンジに写っていたのだった。ということはコダクロームとMF-14やMF-19の相性が悪かっただけなのか。
MF-14やMF-19は3段階の感度手動設定で、MF-29は4段階の自動設定なので、MF-29の方がISO64やISO200にあった適切な写し込みができているのかもしれない。あるいは、写し込み用の光源の違いなのかもしれない。
感度手動設定の場合、写し込みが足りなければ、データバックの設定をより低い感度にすることで濃く写し込めるのだが、ISO64だと、一番低い段階なのでそれよりも低く設定できないのであった。
ともかくF100用MF-29、コダクロームで記録写真を撮るときに便利だ。
| データバック | MF-14 | MF-19 | MF-29 |
|---|---|---|---|
| 該当ボディ | ニコンF3シリーズ | ニコンF-501/F-301 | ニコンF100 |
| 装着方法 | 裏蓋交換式 | 裏蓋交換式 | 裏蓋交換式 |
| フィルム感度 | 白黒:ASA/ISO 100~400(L:100~400)、カラー:ASA/ISO25~400(L:25~64、M:80~160、L:200~400) | ISO25~1600(L:25~64、M:80~200、L:250~1600) | ISO32~3200 |
| フィルム感度切り替え | 押しボタンによる3段階切り替え式/光量切り替えは写し込み時間制御式 | 押しボタンによる3段階切り替え式/光量切り替えは写し込み時間制御式 | ボディ信号による自動設定(4段階切り替え) |
| データの写し込み方法 | 7セグメント6桁の赤色発光ダイオードによりフィルム裏面露光 | 7セグメント6桁の液晶とランプ光によるフィルム裏面露光 | 7セグメント6桁LCDランプ照射によりフィルム裏面より露光 |
| 写し込みデータ | 年月日、日時分、フィルムナンバー(-2~2000) | 年月日、月日年、日月年、日時分、フィルムカウント数(000000~999999) | 年月日、日時分、月日年、日月年 |
| 写し込みデータの大きさ(フィルム面上) | 文字高さ約0.5mm、幅約6.6mm(全文字表示時) | 文字高さ約0.6mm、幅約4.5mm(全文字表示時) | 文字高さ約0.8mm、幅約4.5mm |
| 電源 | SR44×2個 | SR44×2個 | CR2025×1個 |
| データバック用底ケース | CF-23D | CF-35D | なし(CF-57,CF-58) |
【追記:2020年1月20日】
フィルムカメラ写しこみ機能2020年問題 ― 2020年01月20日
ハードディスク・ドライブの故障率に関する事実(日経IT PRO) ― 2007年06月06日 00時00分00秒

カメラのネタが少ないので、カメラに関係あるPCネタを(笑)。
デジタルカメラで撮影した画像データをハードディスクドライブ(HDD)に保存されている方も多いと思う。私もまず最初にPCのHDDにコピーしてそれからDVD-RAMにコピーしている。常に二重にデータがある状態ではじめてCFカードやSDカードの画像を消去することにしている。その最初の保存先であるHDDの故障率に関する記事。
ハードディスク・ドライブの故障率に関する事実(日経IT PRO)
記事本文だけを読みたい方はこちら↓(低速回線向け)【追記】すまん、IT PRO会員(無料)でないと印刷向けページは全文表示されないようだ。【追記ここまで】
ハードディスク・ドライブの故障率に関する事実(日経IT PRO)【印刷向けページ】
私は、どこにデータを保存しようがデジタルデータははかないような気がしているのであった。心配しすぎ?
写真は記事とは関係ない。
東京国立近代美術館工芸館(旧近衛師団司令部庁舎):Nikon F100、Ai AF Zoom Nikkor 28-105mm F3.5-4.5D(IF)、1/250sec、F8、Kodachrome 64 Professional (PKR)、L37c
このニッコール28-105mm、前から思っていたのだが、少し青いような気がする。
Ai AF Zoom Nikkor 28-105mm F3.5-4.5D(IF)とコダクロームで自分のレンズの好みを知る ― 2007年05月07日 00時00分00秒

この連休中はシグマの28mm F1.8(I型)とF100を使うことが多かった。初めていくところなどはズームレンズの方が便利なので、Ai AF Zoom Nikkor 28-105mm F3.5-4.5D(IF)とどちらを持っていこうか迷った。結局シグマ28mm F1.8を持っていったのだが、それは以下の理由からだ。
Ai AF Zoom Nikkor 28-105mm F3.5-4.5D(IF)はコントラストも高くて比較的高画質だが解像力は飛び抜けていないのだ。これはコダクローム64(KR)やコダクローム64プロ(PKR)を使っていて気付いた。絞りを絞って撮った場合でもルーペで見たり、フィルムスキャナでスキャンしても、針で突いたような緻密な描写ではないのである。もちろん駄目駄目画質では全くない。個体差なのかと思って、アサヒカメラのニューフェース診断室(2000年7月号)での測定結果を探し出して見た。やはり、MTFは結構高いが、画面中央で200本/ミリには全く届かず、画面平均は50mm F4.2時の103本/ミリを除いて100本/ミリを切っている。
そこで、自分のレンズの好みが分かってきた。要するに解像力の高いレンズが好みなのだ、と。手持ちのズームレンズでも、一般に駄目駄目レンズと思われているAi AF ZoomNikkor 35-70mm F3.3-4.5S(F3.5-4.5でもF3.5-4.8でもない-よく間違えるので)の方が好みなのだ。この35-70は、広角端の歪曲は大きく、望遠端のコントラストはやや低いのだが、35mmから50mm過ぎあたりまでは高コントラストでかつ単焦点レンズ並みに解像力がある。アサヒカメラのニューフェース診断室1985年12月号に同じ光学系のAi Zoom Nikkor 35-70mm F3.3-4.5S(F3.5-4.8ではない)の測定結果が載っているが、絞り開放で画面中心は140本/ミリ以上で画面平均は、35mm時のF3.3開放で98本/ミリを除いてどの焦点距離やどの絞りでも100本/ミリを超えている。
これが単焦点レンズだと、たとえばAi AF Nikkor 50mm F1.4S(アサヒカメラニューフェース診断室1987年6月号)は、F1.4開放で140本/ミリ画面平均は74本/ミリだが、絞ってF5.6だと画面中心で224本/ミリ画面平均で132本/ミリなのだ。要するに解像力で言えば、28-105ミリは50ミリF1.4開放と同じくらいだということになる。
私がどうもズームレンズが気に入らないのは歪曲収差の問題だけではなかったのだ。高くて重いズームレンズだと解像力が単焦点並みになるのだろうが、そういう重いレンズは嫌だ。28-105mmでも十分重い(笑)。それは常用域が広角側だからだろう。広角レンズとしてみた場合、単焦点の広角レンズは小さくて明るいものが多いので、ズームレンズは暗いのに重くて大きいレンズに見えてしまう。
ちなみに、Ai AF Zoom Nikkor 28-105mm F3.5-4.5D(IF)は、若干色味が青寄りであることもコダクロームで気付いた。このレンズでよく使う富士クロームは青が強調されるフィルムだし、ネガカラーでは色味は分からないからだ。これもアサヒカメラのテスト結果と一致している。
たとえシグマの安い古いレンズであっても、単焦点は単焦点。解像力は上なのであった。逆光に弱いしカラーバランスは崩れてるし、外装はベタベタになってくるけど(笑)。ああ、Ai Nikkor 28mm F2.8Sも使ってあげなきゃ。
【関連】
Ai AF Zoom Nikkor 28-105mm F3.5-4.5D(IF) リポート(2006年03月24日)
写真は記事とは関係ない。
蓬莱橋(静岡県島田市):GR DIGITAL、28mm相当、1/440sec、F7.1、ISO64、-0.3EV、プログラムAE
静岡県島田市の大井川に掛かる蓬莱橋は、「世界一の長さを誇る木造歩道橋」としてギネスブックに載っているそうだ。全長897.4m、通行幅2.4m。地元では「賃取橋」と呼ばれていて、通行料が有料の橋である。往復すると1.8kmほど歩くことになる。静岡県は風が強い地域だが、ここは川なのでなおさら風が強い。写真が傾いてるのは風が強く橋が揺れているから、と言い訳しておく(笑)。料金小屋に掲げてある昔の写真では板が不揃いでうねうねと傾いている橋で、昔はもっと歩くのが怖い橋だったのだろう。
富士もこっそり歪み自動補正処理? ― 2007年04月19日 00時00分00秒

写真家・田中希美男氏のBlogによれば、富士フイルムのコンパクトデジタルカメラも、歪曲収差を自動で補正する処理が入っているそうだ。
歪み自動補正処理(Photo of the Day 2007年4月19日)
フジのカメラはいつ頃からだろうか、フジは黙ってますけど、撮影したあとにカメラ内で自動的にディストーションの処理をおこなうようにしていますね。液晶モニターを見ながらフレーミングしているときに、「画面周辺部でちょいと歪むなあ、樽型になるなあ」と感じる。ところが、撮影した直後にその画像を再生表示してみると、歪みが“ほどほどに修正”されていています。
ただし、こうしたソフト的な後処理は安易にはやらないほうがいいですね(道徳的に云々じゃないですよ、誤解しないでね)。撮影するときにテキトーに写しておいて、あとで画像処理ソフトでどうこうして仕上げる、というのと似てなくもない。結果的に良いものであれば、それはそれでイイじゃないかと考えてるほうだけど、ハッキリとした目的意識を持たずにそんなことしてちゃあいつまでたってもいい写真は写せないし、同じようにいつまでたってもいいカメラやレンズはできないよね。がんばるべきときは、やっぱり、がんばらないと、ね。
わたしもニコンCOOLPIX P5000の「歪み補正」で少し書いたが、こういう技術は悪くはないけれども、あくまでもレンズ側で最善を尽くして最後の手段として使うのがいいと思う。でも一般用のコンパクトカメラで歪曲収差にまで気が回るようになってきたのはいいことだと思う。というか、一般人でも変だと思うぐらい曲がって写るレンズが増えたということなのかも知れないが…。
写真は記事とは関係ない。
麦:Nikon F100、Voigtlander Macro Apo-Lanthar 125mm F2.5SL、F5.6AE、スポット測光、Kodachrome 64 Professional (PKR)
プランターで育てている麦。2ヶ月ぐらい前の写真なので、今は実がもっと大きくなっている。F100の絞り優先AEなのだが、スポット測光でも被写体が小さすぎて背景の明るさに引っ張られたようだ。
アサヒカメラ2007年5月号予告から ― 2007年04月13日 00時00分01秒

アサヒカメラの携帯向けサイト(PCからもアクセス可)で次号(2007年5月号の)予告が公開された。週末なので今日2つ目の更新。また来週\(^o^)/
個人的に気になる記事は(敬称略)、
- あなたは何問正解? クイズで楽しむニコンMF党・党員検定! 赤城耕一・神立尚紀
- これはまさしくベルビアだ 新ベルビアの実力判明 竹内敏信・まつうらやすし
- 散歩にはやっぱり銀塩だ! 富士フイルムクラッセSの楽しみ 赤城耕一
- シグマSD14で春の草花を撮る 萩原俊哉
- ソニー新αはこうなる! 赤城耕一
- ライカMPチタニウム登場 赤城耕一
- 阿部秀之のそうだったのか!デジタル一眼レフ入門 フジFinePix S5Proに見る「心意気」
- 赤城耕一のワタクシ的名機 キヤノン7S
- 試用速報 ソニー バリオ・ゾナーT*DT16~80ミリF3.5~4.5ZA 赤城耕一
- 試用速報 三菱製紙 月光 まつうらやすし
- ニューフェース診断室 ニコンD40+AF-S DXズームニッコールED18~55ミリF3.5~5.6GII 田沼武能/辻内順平/深堀和良/川向秀和/志村努/編集部
しかし、赤城耕一氏は何本記事を書いているんだ(笑)。赤城氏の書かれる記事と私の気になる対象とが重なっているので、赤城氏の記事は全てピックアップされてしまう(笑)。
「ニコンMF党党員検定」って、そういう知識も嫌いじゃないが、名玉を1ページ大の作例で紹介して欲しい。薀蓄語るよりも作例撮る方が手間が掛かるのは分かるのだが。そこで手を抜いては誰も雑誌を買わなくなる。
新ベルビアのインプレッション、楽しみ。個人的にはナチュラル系のフィルムが好きなのだが、新しい材料で従来のフィルムを「復刻」した富士フイルムは偉い!偉すぎる!派手系は好みじゃないが、富士に敬意を表して「新ベルビア」ことVelvia50 Professionalは買うつもり。
クラッセSも富士フイルムの心意気を買いたいのだが、いかんせん高い。SD14も購入検討対象ではないのだが、その撮像素子に将来性を感じて気になっているのだった。ソニーの新αはニコンやペンタックスの135フルサイズとも関係するので、目が離せない。
「ライカMPチタニウム」のチタニウムって、元素の名前としてはチタンなんだったか。でも○○チタニウムという会社も結構あるし。どうでもいいですな(笑)。ライカのチタンボディは、いままで純チタンではなくてチタンコーティングだったりするが、このライカMPチタニウムはどうなのだろう。ああ、Nikon F3/TやNew FM2/Tが欲しい。もちろん買えないがNikon F2 Titanも欲しい(笑)。
ニューフェース診断室は今頃ニコンD40だ。D40Xと一緒にテストしてくれればよかったのに。レンズもキットレンズ1本だけでなく、他のレンズも合わせてテストして欲しい。そうでないと、ボディよりも種類の多いレンズのテストが進まない。ニューフェース診断室が楽しみでアサカメ買っているといっても過言ではない。これも雑誌ならではの企画なのだから。
ライバル日本カメラも、詳細な予告はできなくても当月の目次ぐらいきちんと載せた方がいいと思う。あのサイトだと話題にも上らなくなっていずれ消滅するぞ。写真工業はちゃんと目次を載せている。
【関連追記:2007年4月25日】
ニコンMF党大検定(アサヒカメラ2007年5月号)(2007年04月25日)
【追記ここまで】
写真は記事とは関係ない。
千鳥ヶ淵(東京):Nikon F100、Ai AF Zoom Nikkor 28-105mm F3.5-4.5D(IF)、プログラムAE、マルチパターン測光、Kodak Kodachrome 64 (KR)、Nikon SUPER COOLSCAN 5000ED
これはズームの望遠端で撮ったものだが、周辺光量低下が見られる。今度はPKRではなくKRの方。コダクロームはスキャンが難しい。「出たまま」だと「見たまま」にならない。かといっていじればますます変になる(苦笑)。ファインダーで見たときはお堀の水面が見えていたのだが、現像すると水面が黒くつぶれて分からなくなっている。もう少し下げてもっと明るい部分の水面を入れるべきだった。
ニコンの生産終了リストに早くもD70sとCOOLPIX S7cが ― 2007年04月13日 00時00分00秒

ニコンの生産終了リスト(デジタル機器)に早くもNikon D70sとCOOLPIX S7cが掲載された。デジタルカメラのサイクルは短いなぁ。でもD70sはD70から数えると長い方かもしれない。後継のD80はファインダーがD200と共通になって少し改善されたが、デジタル一眼レフのファインダーはまだまだだと思う。
写真は記事とは関係ない。
牛ヶ淵2(東京・九段):Nikon F100、Ai AF Zoom Nikkor 28-105mm F3.5-4.5D(IF)、プログラムAE、マルチパターン測光、Kodak Kodachrome 64 Pro (PKR)、Nikon SUPER COOLSCAN 5000ED
リコー Caplio R6(デジカメWATCH実写速報)(2007年04月11日)の記事の写真と同じ日にコダクローム64プロで撮ったもの。お堀の水面やその手前の桜の立体感にぞくぞくするのだが、このサイズの画像ではほとんど伝わらない。アサブロも長辺300ピクセルの制限を何とかして欲しい。画像のピクセルの制限ではなく、何KB以下といった制限だとありがたいのだが。しかも長辺300ピクセルという制限だと、3:2の横長の135フィルムの画像の方が、4:3のコンパクトデジタルカメラの画像よりも小さくなってしまう。まあ、ニコンオンラインアルバムか、自分のHPに大きな画像を置いてリンク張ればいいのだが。
1年寝かせたコダクローム200(KL)はニュートラルだったが変なものが… ― 2007年03月15日 00時00分00秒

一昨年(2005年)の暮れに生産終了になったKodachrome 200(KL)を久々に使ってみたら、結構ニュートラルな色だった。KLはマゼンタ被りが有名で、私も過去に使ったかなりのコダクローム200がひどいマゼンタ被りだった。今回のフィルムは、乳剤番号(エマルジョンナンバー)は2671で消費期限10/2006のもの。冷蔵庫に保管していたものだった。しかし、もう手に入らないフィルムのこういう情報って誰の役にも立たないなぁ(笑)。
ところで、このコダクローム200のあがってきたスリーブのうち2コマにグレーの変なものが写っていた。写真は部分の拡大だが、変なものは長い方でフィルム上で約7mmぐらいの大きなものだ。この一つ前のコマにも少し違う位置にもう少し小さい変なものが写っている。
光学系に入ったごみかとも思ったのだが、それにしては大きい。フィルムの直前にあるゴミは、もっとはっきりと写るし、レンズの中にあるゴミはこのように写りこむことは少ない。ミラーボックス内に大きなほこりでもあったのだろうか。不思議だ。もちろん撮影直前にファインダーにこんな大きなものがあったら気付くので、ファインダーではこの変なものは見えていなかった。カメラはF100でレンズはAi AF Zoom Nikkor 28-105mm F3.5-4.5D(IF)(28mm時)SIGMA 28mm F1.8 ASPHERICAL(I型) + SC-40Mフィルターだ。スキャナはNikon SUPER COOLSCAN 5000ED。【追記】すまん、レンズを間違っていた。このときはシグマの28mm F1.8をつけていた。【追記ここまで】
撮影時のほこりじゃなくて、現像時のほこりや薬剤のムラかとも考えた。なぜなら、変なものの下の方に写っているキャベツがそこのところだけ濃く写っているからだ。ごみが光学系に入り込んだのならこんな風にごみの影の部分の画像濃度が濃くなるのはおかしいような気がする。うーん、なんだろう。


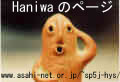

最近のコメント