コシナ、フォクトレンダー史上最高性能をうたう「APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical E-mount」 ― 2019年10月21日 00時00分00秒
久々のコシナネタのような気がする。コシナが「フォクトレンダー史上最高性能」をうたう「APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical E-mount」を発売するそうだ。
コシナ、フォクトレンダー史上最高性能をうたう「APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical E-mount」(デジカメWatch)
レンズ設計に軸上色収差や各種収差の抑制を目指すアポクロマート設計を採り入れたMFレンズ。ソニーEマウントカメラのイメージセンサーに最適化したとしており、解像力やコントラストの再現性の高さでも訴求する。
レンズ構成は8群10枚(異常部分分散ガラス5枚、両面非球面レンズ2枚)。
"Macro"が付いていないのでマクロレンズでもなさそうだし、最短撮影距離は0.45m で、普通の標準レンズと同じなので、どういう撮影を意図したレンズなのか自分はよく分からない。
「至近距離から遠距離まで高画質を保つというフローティング機構を採用している。」とあるので、接写リングやベローズでの撮影も意図していなさそうなのでなおさらよく分からない。高画素で緻密な風景撮影向けのレンズなのだろうか。
話は少し変わるが、コシナなどのいわゆる「レンズメーカー」のレンズラインナップを見ると、そのときどきの主流のカメラがよく分かるなぁと思う。
2019年版フォクトレンダー総合カタログを見ると、E-Mount Lenses(ソニーEマウントレンズ)は8本、Micro Four Thirds Mount Lenses(マイクロフォーサーズレンズ)も8本、VM Mount Lenses(VMマウントレンズ:事実上のライカMマウント互換レンズ)は19本、SLR Mount Lenses(一眼レフ用レンズ)は2本(ニコンAi-S互換)となっている。あれだけたくさんあった一眼レフ用交換レンズはニコン用を2本残すのみとなっている。
ライカマウントのカメラを持っている人がそんなに多いとは思わないが、ライカマウントのカメラを持っている人が交換レンズを買う可能性が高くて、またライカマウントはマウントアダプターで他のミラーレスカメラに使えるから、ライカマウント互換のレンズラインナップが多いんだろうなぁ。
まあ、コシナは商品開発の機動性が高いけど、軸足移すのもはやいよなぁ。きちんとした金属鏡筒で信頼の出来る光学性能のレンズをそこそこの値段で出してくれるコシナの存在はありがたいが、SLRレンズが少なくなっているのは少し寂しいな。
自分はライカマウントのカメラを持っていないが、もし持っていたら、NOKTON Classic 35mm F1.4を最初に買いたいな。VM Mount Lensesシリーズは、10mmから始まる超広角レンズのラインナップが充実しているのもうらやましい。値段もNIKKORの新しいレンズに比べたらかなり安いし。
とりとめもなく書いてしまったが、ソニーEマウントの35mmフルサイズのミラーレスカメラに、ライカMマウント互換のレンズを使うのが楽しそうだなぁと思う。
【追記】
フォクトレンダーTOP(コシナ)
フォクトレンダー生産終了品(コシナ)
【追記ここまで】
写真は記事とは関係ない。
アールエフラジオ日本野毛山無線基地(横浜市西区):Huawei P20 lite(ANE-LX2J)、3.81mm(35mm版26mm相当)、F2.2開放、1/157.4秒、ISO50、プログラムAE、AWB
Huawei P20 liteの撮って出しJPEG画像はかなりコントラストが高く、曇り空の雲はよく描写されていたが、手前の自転車などが暗くつぶれてしまっていたので、JPEG画像をすこしいじっている。
作例は野毛山動物園の近くにある中波ラジオ放送送信設備。神を感じさせるフィルムカメラの描写力(アンディ・サマーズ) ― 2009年07月21日の作例に写っているアンテナと同じもの。このブログで過去にこのアンテナを検察関係のものかもと書いた記憶があるのだが(となりに検察関係の官舎があったから)、今回近づいてみたら、RFラジオ日本(1422KHz)の予備送信所(1kW)だった。RFラジオ日本は、普段は川崎市の多摩川河川敷にある50kW(JORF 1422KHz南西に指向性あり)と小田原のJORL 1485kHz 100Wで送信している。
「JORF 昭和33年12月24日 ラジオ関東開局の地」というプレートが建物に付いているので、1958年にRFラジオ日本の前身のラジオ関東がここに開局したようだ。RFラジオ日本は神奈川県域の中波ラジオ局だが、事実上の「演奏所」は 東京都港区麻布台2-2-1 麻布台ビル北館2階にある。神奈川県のラジオ局なのにベイスターズやFマリノスやフロンターレやベルマーレを無視してジャイアンツ戦ばかり放送する「ねじれた」局というのが私の認識だ。かつてのベルディと同様に東京に移転すればいいのに(電波割り当て上無理だが)。代わりに本当の意味での神奈川県域中波ラジオ局ができればいいと思っている。読売は放送局関係では朝日や毎日よりも後発なので、どうしてもこういう後発局が読売系になってしまう傾向があって地元民が不幸だ(個人の感想です)。
台風19号東日本接近ないし上陸のおそれ、十分に準備を ― 2019年10月10日 00時00分00秒
大型で猛烈な台風19号が10月12日(土)~13日(日)にかけて東日本に接近ないし上陸の可能性がたかいとのこと。
台風19号 土曜から東日本に接近へ 甚大な被害のおそれ 2019年10月10日 8時21分(NHK NEWS WEB)
台風第19号に早めの備えを!(10月9日) (気象庁)
米軍の予想では、予報の中心線は伊豆半島の先石廊崎をかすめて相模湾岸から東京湾岸を通って東京・千葉・茨城方面に向かうことになっている。台風15号につづいてまた千葉県が台風の進路の右側になりそうだ。
十分な備えや予めの避難を。予め台風から遠い場所の親戚や知り合いの家に避難しておくというのもよいかも。
台風第19号に早めの備えを!(10月9日)[PDF形式:1.5MB] には、風が強まる前に家の対策の何をすればよいかが書かれているので、今日明日中に対策を。
台風19号 15号と同程度の暴風のおそれ いまからできる対策 2019年10月9日 19時05分(NHK NEWS WEB)も参照。
スマホは電池がなくなるのが早い上に近くの基地局がやられて繋がらないこともあるので、ラジオと電池もご用意を。ラジオ局も台風15号ではニッポン放送1242kHzが千葉県木更津市の送信所が停電して足立区の予備送信所から送信したり、その後自家発電で木更津から送信したりもした。それでも放送は続いていたので携帯電話よりは情報を受け取りやすいだろう。ニッポン放送が送信所の自家発電で横浜スタジアムからのプロ野球試合中継を放送しているのにはちょっと複雑な気分だったが。
AM1242kHzでお聴きのリスナーの皆様へ 2019/09/12 14:00(ニッポン放送)
画像は、米軍の予報から。https://www.metoc.navy.mil/jtwc/jtwc.htmlからhttps://www.metoc.navy.mil/jtwc/products/wp2019.gif
なお、図の12/18Zというのは、12日協定世界時(UTC) 18時ということで、日本標準時(JST)は+9時間なので、13日の日本時間5時を示している。
バイク用ナビRM-XR550XLにradikoをインストールした(その1) ― 2018年09月14日 00時00分00秒
災害も多いし、なんか天気ずっと悪いし、すっきりしない今日この頃ですが、皆様お元気でしょうか。
待望のニコン初の35mmフルサイズミラーレスの発表があったのに、実機の撮影リポートがほとんどあがってこないので、記事の更新機会を逸してしまった。マスコミにZ7配るのって遅かったのかしら。それとも記事が書きにくいのか…。Z7に対応したCapture NX-D Ver.1.5.0でカラーコントロールポイントが復活したという朗報もあるようだが。
Capture NX-D
Z7で向かってくるリニア新幹線実験線を連写とか、モータースポーツで高速連写とか、ドッグランで向かってくる愛犬を連写とか、サッカーで入り乱れた選手をジャスピンで追い続けるとか、そういう実写リポートを待っております(はぁと)。
さて、またまたバイクネタですまん。今回は、ちょうど2年前に買ったRWCのバイク用ナビX-RIDE RM-XR550XLでラジオが聴けないかと、radikoをインストールしてみた話だ。
バイクで一人で高速道路を走っているときに何が寂しいかって、ラジオが聴けないことだ。インカムの中にはFMラジオが内蔵されていてラジオが聴けるものがあった。しかし、最近そういう機種は減ってきている。FM放送は国によって周波数範囲が異なる上に、日本は76-90MHzだったのにアナログテレビの停波に伴って90-95MHzがFM補完放送に割り当てられたので、仕様変更しなければいけないのが面倒でラジオ内蔵のインカムが減ってきているのかもしれない。
あとは、radikoが聴けるので、スマホとインカムをペアリングしておけば、多少のタイムラグはあってもラジオの放送が聴けるのも大きい。
それで、私の使っているインカム(※)はデイトナのEasyTalk3というものなので、ラジオは内蔵されていない。※(ヘルメットの中にインカム附属のステレオスピーカーをセットしている。道路交通法規上も合法で、最近のヘルメットにも最初からスピーカーを内蔵する凹みがつくってある)
一つの方法として、小型ラジオ受信機のヘッドフォン端子にBluetooth送信機を付けてインカムとペアリングすれば、ラジオが聴ける。
ところが、Bluetoothの送信機にいいものがなかなかないのだ。Easytalk3はBluetoothの対応プロファイルがHSP, HFP, A2DP, AVRCPとなっている。しかし、ほとんどのBluetooth送信機はA2DPしか対応していないのだ。
A2DPで対応しているのなら、それでラジオ側とインカム側とでペアリングできて使えるじゃないかと思われるだろう。たしかにそうなのだが、そうすると、ナビゲーションシステムとインカムもA2DPなのでナビとラジオが同時に聴けなくなってしまうのだ。
Easytalk3は、ナビとはA2DP、携帯やスマホとはHSPかHFPで接続して両立しているようなのだ。だから、Bluetooth送信機はHSPかHFPにも対応していないと使いにくい。それがなかなかないのである。探すのが面倒だ。みつかってももう製造中止だったりする。最近Bluetooth内蔵の電化製品が多くなってきているので、こういうBluetooth送信機というのも廃れて来ているのかもしれない。
ということで、バイク用ナビX-RIDE RM-XR550XLは、防水の5インチandroidタブレットが実体(android 4.4.2)なので、ここにradikoをインストールしてみたらどうかということに至った。X-RIDE RM-XR550XLはバイク用ナビとしては珍しくWi-Fiユニット搭載なのだ(だから買った)。
それでインストールするradikoのアプリなのだが、バイク用ナビX-RIDE RM-XR550XLはGooglePlayがインストールされていないので、ダウンロードできない。RM-XR550XLにはブラウザもない。
しかたないので、Nexus7(2012)(android 4.4.4)にインストールしているradiko 5.0.3をESファイルエクスプローラでapkバックアップしたものを使うことにした。Nexus7(2012)をPCにUSB接続して"radiko.jp for Android_5.0.3.apk"をコピーした。それをmicroSDカードにコピーしてRM-XR550XLに挿入した。
RM-XR550XLには、ホーム画面の右下にある「本を開いた絵に?」のところをクリックした先に「ファイルマネージャー」がある。このファイルマネージャーでextsdの中がmicroSDカードの中身だ。ここにさっきコピーした"radiko.jp for Android_5.0.3.apk"があるのでタップしてインストールする。なお、事前に「設定」の「セキュリティ」のところで「提供元不明のアプリのインストールを許可する」にチェックを入れておく。
無事にインストールに成功した。\(^o^)/
radikoが「最新版でないのは、android 4.4ではこのバージョンが安定しているようなのでNexus7(2012)の方でもアップデートしないようにしているのだった。巷の情報によると"radiko.jp for Android_5.0.9.apk"が古いOSで使うには一番安定しているようだが、自分は持っていないし5.0.3で問題ないので、これをインストールした(野良のapkをダウンロードしてインストールするのは自己責任で)。
インストールが完了すると、「完了」か「開く」かをきいてくるので、「開く」にした。
すると、ラジコが立ち上がって位置情報をどうするのかきいてくるので、ドコモ回線じゃなくてWi-FiやGPSを使う方を選ぶ。RM-XR550XLにはドコモ回線につながる無線端末は内蔵されていないからだ。
これでラジコの画面が立ち上がってTBSラジオが鳴り出した(もちろん端末のWi-Fi設定は有効にしておく。アクセスポイントとの設定も済ませておく)。
ただし、ラジコは縦画面固定だ。ナビは横画面で使うものなので使いにくい(上の写真参照)。しかも、再生と停止ボタンが非常に小さい。使いにくいなぁ。でも。これでラジオ聴きながらナビも使えてバイクに乗れる。うれしい。交通情報も聴けるぞ。
ナビとラジコを同時起動してみたが、ナビの音声案内が入るとラジコの音声が小さくなって、ナビの音声が上からラジコよりもやや大きい声で案内する。おお、ばっちりやん。
しかし、ここで問題が発生。インストールした直後は、「完了」か「開く」かを訊いてくるのだが、いったんラジコを終了してしまうと、どこからも起動できないのだ。ナビのホーム画面には新しいアイコンが追加されないので起動のしようがない。しかし、設定のアプリのところをみるとradikoはちゃんとインストールされている。
androidって設定のアプリの画面から「強制停止」や「アンインストール」はできても「開く」や「実行」はできないんだな。面倒なOSだな。
規定のファイルエクスプローラは、mnt/sdcard以下とmnt/extsd以下のディレクトリしか参照できない。それで「ESファイルエクスプローラ」というアプリをインストールして全ディレクトリを参照できるようにした。そうするとESファイルエクスプローラのホームのアプリというところからradikoが起動できることが分かった。
しかし、そのESファイルエクスプローラもどこからも実行できない。仕方ないので、毎回microSDカードからESファイルエクスプローラをインストールし直して「開く」を選択した。
なんとかホーム画面を編集しなければ。
長すぎるので、今日はここまで。つづく。
【関連】
R.W.C バイク用ナビRM-XR550XLインプレその1 ― 2016年10月03日
R.W.C バイク用ナビRM-XR550XLインプレその2 ― 2017年03月14日
R.W.C バイク用ナビRM-XR550XLインプレその3 ― 2017年03月15日
RWCのX-RIDEナビが進化中 ― 2017年10月20日
RAMマウント用テザーをバイク用ナビRM-XR550XLのセーフティネットにする ― 2018年03月22日
【関連追記:2018年9月15日】
バイク用ナビRM-XR550XLにradikoをインストールした(その2) ― 2018年09月15日
【関連追記:2018年10月17日】
Bluetoothテザリング接続(バイク用ナビRM-XR550XLとMR04LN) ― 2018年10月17日
SONY ICF-R354MとICF-R350の感度は同等だった ― 2018年05月21日 00時00分00秒
SONY ICF-R350の液晶画面が…、ICF-R354Mこんにちは ― 2018年04月24日で試してみると言っていた感度比較を報告したい。
ICF-R350のシリーズは、写真のように名刺サイズで非常に小さいのだが、AMの感度が非常に良い。関東地方南部で昼間に山梨放送(765KHz、5KW)が聴けたり、夜ともなれば多くの放送局が内蔵バーアンテナで聞こえる。
それで、ICF-R350とICF-R354Mの感度を比べてみたのだが、ほとんど同じように高感度であった。片方で聞こえてもう片方で聞こえないという放送局はなかったし、聞こえる場合でも同じような電波強度で聞こえた。
NHK東京第二(693KHz、500KW)が深夜停波した後には、関東地方南部の木造建物屋内でIBC岩手放送(684KHz、5KW)が、両方のラジオで聞こえた。
ただ、音質には違いがあった。どちらも内蔵の巻き取り式モノラルイヤホンだが、ICF-R354Mの方が豊かな音だ。ICF-R350の方が硬い感じの音質だ。イヤホンが違うからなのか、内部の何かが違うからなのかは分からないが、明らかにICF-R354Mの方が音がよい。内蔵スピーカーの音は比べていないので分からん。すまん。
それ以外に大きな違いは、バックライトボタンを押したときだ。バックライトボタンを押すと「ピッ」という音とともにバックライトが点灯する。その「ピッ」と言っている間、ラジオの音は聞こえない。ただ、ピッという音は0.5秒も鳴っていない。この挙動が両者で違うのである。ICF-R350の方はライトボタンを押すとすぐにピッと言ってライトが付く。ところがICF-R354Mの方は、ライトボタンを押すと一瞬ラジオの音が聞こえなくなってからピッと言ってライトが付くのである。「ん、ピッ」という感じ。だからICF-R354Mの方が、ライトボタンを押したときに放送が聞こえない時間が長い。これは、寝床でラジオを操作するときに結構な違いとなる。
試しに、ライトボタンを連打してみると分かる。ICF-R350の方は何度ライトボタンを押しても、放送の内容は聞き取れるが、ICF-R354Mの方は、ライトボタンを何度も押すと無音の状態とピッという状態が続いて放送が聞き取れない。ライトボタンを何度も押すことは極端な例だが、ICF-R354Mはボタンを押したときの放送が聴けない状態が長すぎると思う。新しい方が必ずしも優れているとは限らない例である。電池の持ちも、古いICF-R350の方がよい。こちらは実用上気になるほどの差ではないが。
あと、ICF-R350の筐体の液晶窓部分にひびが入ったところには、KenkoのGR用の液晶保護シートをサイズが合うように切って貼った。同じようにICF-R354Mの液晶窓にも貼った。KenkoのGR用は反射も抑えられているし、少し硬いので保護になるだろう。
ICF-R354Mは、よく見ると表面が梨地になっている。妙なところに凝っているなぁと感心した。滑り止め効果を狙っているのだろうか。附属のビニルケースに入れて使っているので、梨地の恩恵には預かっていないのだが。
ちなみにICF-R350もICF-R354MもAMはアジア・ヨーロッパ・アフリカ仕様の9KHzステップだ。これを北米・南米仕様の10KHzステップに切り替える方法は説明書には書かれていない。なにか裏コマンドがあるはずと思いつつ見つけられていない。
ICF-R354MK付属のACアダプタAC-ET603はICF-SW7600GRで使えなかった ― 2018年04月26日 00時00分00秒
SONY ICF-R350の液晶画面が…、ICF-R354Mこんにちは ― 2018年04月24日のつづき。ICF-R354Mが販売終了なので慌てて購入しようとしたが、ラジオ単体のものは手に入らず(探せばあるんだろうがヨドバシのポイントを使いたかった)、仕方なく充電台とセットになったICF-R354MKの方を買ったのは書いた。
それで、使わない充電台のACアダプタがDC6Vなので、おなじくDC6VのICF-SW7600GRに流用できるのではないかと考えていた。私のICF-SW7600GRは北米版なのでACアダプタは付いていなかったのである。
SONY ICF-SW7600GR北米仕様ゲット ― 2012年09月14日
ICF-R354MKに付属していたACアダプタの型番はAC-ET603で、
INPUT:AC 100V~
50/60Hz 4WOUTPUT:DC 6V 300mA
とある。
コンセントにAC-ET603を挿して、DC側のジャックをICF-SW7600GRのジャックに差し込んだ。どちらも中央が+極の仕様だ。
あらら、NHKラジオ第一(594KHz)の声が震えている。NHK第二にしてみたが同様に声が震えている。DCジャックを抜いたら、内蔵のエネループに切り替わりちゃんと音は普通に聞こえる。もう一度AC-ET603を繋ぐ。やはり声が震えている。駄目だな。ICF-SW7600GRも販売終了になっていて壊れたら困るのでこれ以上は試さなかった。
テスターでAC-ET603の出力電圧を測ってみた。デジタルテスターではDC 10.05Vとでた。アナログテスターでは9.6Vぐらいを挿している。デジタルとアナログとでなんか誤差が大きいな。アナログテスターでは特に針が震えたりはしていないようにみえる。定格ではDC 6Vとあるのだが10V前後あるのは、無負荷なので電圧が高いのかもしれない。
何が原因なのか分からないが、AC-ET603はICF-SW7600GRには流用できないようだ。300mAとあるので、AC-ET603では出力が足りないのかもしれない。
ICF-SW7600GRの国内版に付属しているACアダプタの型番はAC-E601で、ヨドバシカメラだと税込5940円もする。
ソニー SONY AC-E601 [ラジオ用 ACアダプター 147612215](ヨドバシドットコム)
AC-E601がなぜこんなに高いのかというと、AC-E601は100~240V対応なのだ。海外でもトランス無しでコンセント用のアダプタのみで使えるように100~240V対応になっているのだろう。だからACアダプタAC-E601等が付属していない北米版ICF-SW7600GRは安かったのだろう。
ということで、ICF-SW7600GRはこれまでどおり単3形エネループ4本で使うことにする。エネループ運用で困るのは、電池が減ったときに警告マークが出ないで、いきなり終了してしまうことぐらいだ。いきなり終了したときに電池マークが点く。これはアルカリ電池で使うことを予定している機器でニッケル水素電池を使うとよくあることなので、常に横に予備の単3形エネループ4本を置いてある。なお、電池警告マークはエネループでは役に立たないが、電池が切れる直前は音が少し小さくなって、ボリュームを上げても満充電の時と比べてあまり音が大きくならない。これがICF-SW7600GRをエネループで使っていて電池が空になりそうな予兆である。
【追記】
なお、ICF-SW7600GRの取扱説明書には「ACパワーアダプター(日本国内モデル、ワールドモデルはAC-E601(付属)、他地域はAC-E60HG(別売り))をDC IN 6V端子につなぎます。」(日本語版10ページ)とあるので、AC-E60HGもICF-SW7600GR用ACアダプタのようだ。でもAC-E60HGって国内では売ってないっぽいなぁ。【追記ここまで】
SONY ICF-R350の液晶画面が…、ICF-R354Mこんにちは ― 2018年04月24日 00時00分00秒
荒野の故障ブログへようこそ!(泣)
今日の故障は、名刺サイズラジオSONY ICF-R350だ(泣)。先週、ふとみると、液晶画面にクラックが…(泣)。
ICF-R350は、2008年に買ったものと記憶する。出かけるときはカバンに放り込んでいつも持ち歩いていて、夜寝付けないときに聴きながら寝たりしていた。ICF-R350はOFFタイマーがあるので寝ながら聞くのに最適なのだ。
SONY ICF-R350(FM/AM・TVアナログ1-12ch)PLLシンセサーザーラジオ(現行品ICF-R351) ― 2008年12月04日
SONY ICF-R350のイヤホンを修理に出した、が… ― 2016年09月23日
それが、先週バイクに乗る時に使っているウエストバッグの底から液晶画面が割れた状態で発見された(泣)。おそらくその前にバイクに乗ったときに携帯電話か何かの角が当たって割れたんだと思う。行った先の駐車場でUターンするときにウエストバッグにハンドルがギューっと当たった記憶がある。そのときかも。
ただ、この割れた透明プラスチック部分は、液晶とは別の筐体部分らしく、液晶はちゃんと表示されていて、ほかの動作も問題ない。何か保護シールを貼っておけばよかったなぁ。今さらだが、保護シールを貼って使い続けようと思う。どこかでICF-R350のジャンク品があったら筐体を交換してみたい。
割れていて見てくれは悪いがICF-R350は問題なく使えるので、新しい名刺サイズラジオを買うつもりはなかった。
しかし、SONYのサイトをみるとこの数ヶ月でどんどんラジオが販売終了になっている。新製品も出てはいるが、無くなっていく機種の方が多い。
ICF-R350の後継品ICF-R354Mも販売終了在庫限りのようだった。ICF-R354Mの後継品そのものはないようで、FMがステレオのSRF-R356が新製品としてラインナップされている。
ただ、新しい機種ほど電池駆動時間が短くなっていて、しかも単4形1本だったものが2本になっていたりする。うーん。だったら、家族用に以前買ったICF-R354Mを在庫がなくなる前にもう1台買っておくか、と思った。以前、ICF-SW23やICF-SW22(JE)を買うかどうか迷っているうちに販売終了になって後継品がないままになってしまったのも背中を押した。ICF-SW23ってアナログ表示だけれどもカセットケースサイズで高感度でキャンプなどに最適だったんだよね。買っておけばよかった。
ICF-R354Mの単体はヨドバシカメラでは販売終了だったので、割高だが(だからまだ売れ残っている)、充電台付きの方を買った。ACアダプターはICF-SW7600GRに流用しようかと思う。
【追記:2018年4月26日】ICF-R354MK付属のACアダプタAC-ET603はICF-SW7600GRで使えなかった ― 2018年04月26日参照・【追記ここまで】
さて、ICF-R350は名刺サイズの小ささなのに、高感度で、夕方以降は関東地方南部で大阪朝日放送ラジオ1008KHzとか普通に聴けてしまう。鉄筋コンクリートの場合でも窓際に行けば朝日放送ラジオが聞こえる。東北放送ラジオ(1260KHz仙台)やSTVラジオ(1440KHz札幌)なども聞こえる。RCC中国放送(1350KHz広島)も聞こえる。
ラジコで遠方のラジオ局が雑音無しで聴けるこの時代にわざわざ中波の電波で聴く必要性がどこにあるかといわれれば、それはタイムラグのないリアルタイムで聴けるところにあると答える。
たとえば、横浜ベイスターズの試合中継は、東京のキー局が巨人の中継に重点を置いているので、なかなか放送されない(横浜の放送局であるはずのRFラジオ日本1422KHz(旧ラジオ関東)は読売系)。横浜スタジアムで行われている試合なのに関東地方では中継が放送されていないということが普通にある。ところが相手チームの地元局では横浜スタジアムから試合を中継しているのである。
だから、広島カープ対横浜ベイスターズの試合を横浜スタジアムで観戦しながら広島のRCCラジオを聴くのである。これがラジコだと何十秒から1分以上遅れているので、観戦しながら聴くのには向いていない。電波は光と同じ速度(約30万km/秒)で進むのでほとんどタイムラグがないのである。横浜から広島に送って広島からの電波を横浜で受信してもアナログなら事実上タイムラグがない。
ICF-SW7600GRで横浜の試合観戦しながら広島からの電波で聴く ― 2015年05月22日
ということで、ICF-R350とICF-R354Mの感度が同じぐらいなのかどうかなど聞き比べてみたいと思う。いままでうちにあったICF-R354Mは家族が使っているので比べられなかったのである。
【追記:2018年5月21日】SONY ICF-R354MとICF-R350の感度は同等だった ― 2018年05月21日
ICF-R354Mは、山ラジオICF-R100MT とICF-R350・ICF-R351系の統合後継品なので、「山エリアコール」機能も搭載している。また、親送信所の電波が届きにくい箇所にある「中継局」を簡単に選べる機能もある。さらに、メモリーボタンの「1」が必ずそのエリアのNHK第一になるようになっているらしい。基本機能はICF-R350と同じでさらにいろいろと進化しているようだ。
【追記】
なお、ICF-R350もICF-R351もICF-R1000MTもICF-R354MもFMは76~108MHzの受信範囲なので、FM補完放送(AM放送局が90~95MHzの範囲で送信している新サービス)は受信可能。欧米ではもともと108MHzまでがFM放送の範囲であるため、これらのラジオは海外で使うことを考慮して76~108MHzになっていた。
GPSBabelでGT-740FLのデータを取り出す ― 2018年02月27日 00時00分00秒
GT-740FLは感度がよくて、胸ポケットに入れているだけでちゃんと軌跡を記録できるよいGPSロガーである。
ところが、これまで書いてきたようにGT-740FLにはいくつか問題がある。まず。シリアル接続なのでCanWayというソフトウェアでないとデータを取り出せない。CanWayはWindowsにしか対応していない。
しかし、GPSBabelというオープンソースのフリーソフトウェアでもGT-740FLのログを取り出せるということを検索で知った。GPSBabelはWindows用だけでなくMac用、Linux用もある。
それで、GPSBabelをWindows7にインストールしてGT-740FLからデータを取り出せるか試してみた。
GPSロガーGT-740FLをMac/Linuxでも使えるGPSBabelを参考にさせて戴いた。
GT-740FLはSkyTraq 準拠のデータ方式で記録しているらしく、GPSBabelのinput設定でDeviceはSkyTraq Venus based loggers (download)を選択する。
Device Nameは、Windowsのコントロールパネルからデバイスマネージャを参照してどのCOMポートにGT-740FLが接続されているか調べて選択する。うちにあるPCだとCOM5とかCOM8が割り当てられていた。
inputのOptionsでは、上記ブログを参考にbaud=115200,initbaud=115200とした。Optionsを押した先の画面でBaud rate used for downloadにチェックを入れて115200を入力、Baud rate used to init device (0=autodetect)にチェックを入れて115200を入力する。
大事なのはFiltersである。これを指定しないと、GT-740FLに記録されているログがすべて1つのログファイルとして出力されてしまう。自分の場合今年の1月に一回データ消去して以降ずっとデータを溜めたままなので、Filtersを指定しないとものすごく巨大なGPXファイルができてしまい、KMLファイルに変換したら2ヶ月分の軌跡がごちゃごちゃに書き込まれていてGoogle Earthが途中で動かなくなってしまった。Filtersで日付時間指定で取り出す。
そうしてGPSBabelで取り出したGPXファイルを見てみると、速度がやはり約半分になっていた。そうするとCanWayが悪いわけではなく、GT-740FLが速度をkm/hで記録しているのが悪いんだろう。SkyTraqの規格は知らないのだが、SkyTraqも速度はノットで記録する決まりなのだろう。GT-740FL駄目じゃん。
だとするとCanWayはGT-740FLのメーカーが出している純正ソフトなのだから、エクスポートするときにkm/hをノットに変換して出力すべきだろう。あるいは、GT-740FLをファームアップしてノットで記録するように変えるかする必要がある(その場合CanWayもバージョンアップしてノットで扱うようにする必要がある)。
ともかく、GPSBabelというオープンソースでフリーのソフトウェアでGT-740FLのデータが取り出せることが分かったので、CanWayが今後新しいWindowsに対応しなくなってもGT-740FLを使い続けることができそうだ。MacやLinuxでもGT-740FLのデータを取り出せることになる。GPSBabel、ありがたい。
【関連】
GPSロガーGT-740FL(Sport LogBook)を買った(追記あり) ― 2018年01月10日
GPSロガー GT-740FL(Sport LogBook)は加速度センサーがネックか ― 2018年01月11日
GPSロガー GT-740FLのCanWayの代わりにGPS PhotoTrackr ― 2018年01月12日
CanWay 1.1.12とGT-740FLはタイムゾーンを触らなければなんとかなる(解決編) ― 2018年01月15日
CanWay 1.1.12とGT-740FLでログをエクスポートすると速度が半分になる ― 2018年02月26日
写真は記事とは関係ない。小湊鐵道月崎駅「森ラジオ ステーション」:Nikon D300S、AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED、Nikon NCフィルター、HB-23フード、10mm(35mm版15mm相当)、F8、1/30秒、手持ち撮影、絞り優先AE、ISO-AUTO(ISO 2200)、AWB、ピクチャーコントロール:ポートレート、マルチパターン測光、51点AF-AUTO 、高感度ノイズ低減:標準
写真は小湊鐵道の月崎駅にあった使っていない保線小屋をアート作品にした「森ラジオ ステーション」の内部だ。天井が抜けて天窓が壊れてブルーシートで覆ったりしていて修復中だった。今年のゴールデンウィークに公開できるように修復しているとのことであった。また行きたいですな。
SONY ICF-R350のイヤホンを修理に出した、が… ― 2016年09月23日 00時00分00秒
非常時の情報収集用に毎日持ち歩いているカードサイズラジオのSONY ICF-R350のイヤホン部分にヒビが入った。
寝るときに聞いたまま寝落ちしたりするので、体の下敷きになったのかもしれない。一応音は鳴っていたのだが、耳に挿入する部分なので、修理することにした。
ヨドバシカメラの修理部門経由で修理に出したら、見積もりが7128円とのこと。後継のICF-R354Mが買える値段だが、修理することにした。SONYは部品を出してくれるメーカーらしいので、イヤホンの部品だけ出してもらって自分で半田付けしてもよかったかなとも思ったが、修理の需要があるということを示すのも大事だと思って修理に出した。ビニルカバーがボロボロになったので、それも注文した。
古い方のカバーはカビが生えているみたいに見えるがそうではない。表面の擬革風の部分が剥げて下地が見えているのだ。
約10日で修理から帰ってきたのだが、小さなラジオなのに、プチプチでぐるぐる巻きにしてあってすごく大きな商品みたいになっていた。ヨドバシカメラの修理窓口の店員が「確認しますか?」と聞くので、中身を確認することにした。すると、店員は、そのぐるぐる巻きのプチプチをかなり強引に破いて取っていた。
そのときは光線の関係で気が付かなかったが、持ち帰ってみてみると、新しくなったはずのビニルカバーがもう剥げている。表と裏の2箇所だ。おそらく、梱包のプチプチを止めるテープか何かがそこに止まっていたのだ。それを強引にはがしたときに、疑似皮革の表面のビニルを一緒に剝がしてしまったんだと思う。がっかりである。乱暴に剥いていた店員のせいだと思うがその時点では気が付かなかったので泣き寝入りだ。
ちなみの以前のビニルカバーは、かなり長いこと剥けてなかったのだが、1箇所剥けてくるとそこからどんどん剥げていった。だからこの新しいカバーもじきにボロボロになるんだろうなぁ。
ヨドバシカメラ某店の修理受付部門は、空いているのに早口でとっとと処理したいという感じがしてよい感じがしないのだが(その店員の個性かもしれないが)、このラジオを見るたびにそれを思い出すことになるので嫌な感じだ。SONYのサービスセンターにもう一度ケースだけ注文しようかと思う。
こんどからどんな商品も修理はヨドバシカメラを通さずに直接メーカーに出すことにしよう。
ヨドバシカメラ経由の修理と言えば、この記事(「恥知らず企業ニコン」(ダイヤル式カメラを使いなサイ!))を思い出したのだが、この記事の時点では、修理受付は売場が担当していたんだなぁ。それにこれはヨドバシは悪くないみたいだし。
【関連】SONY ICF-R350(FM/AM・TVアナログ1-12ch)PLLシンセサーザーラジオ(現行品ICF-R351) ― 2008年12月04日
ちなみにさらに現行品はICF-R354M(ICF-R354MK C)となっていて、これはうちの家人が使っている。
ICF-SW7600GRで横浜の試合観戦しながら広島からの電波で聴く ― 2015年05月22日 00時00分00秒
今日はカメラネタでなくてすまん。順位が下がっているとの指摘を受けて急遽更新(笑)。米軍基地の騒音問題を扱っている記事がトップにあると困る政権側が必死で他のアサブロ記事をクリックしまくって順位を下げようとしているに違いない(嘘)。
写真は、4月に横浜スタジアムで撮ったもの。横浜スタジアムの試合って、巨人戦だと東京のラジオ局が中継するが、それ以外のカードだと地元の中波ラジオ某局が読売系でかつ神奈川県域局として免許を受けているにもかかわらず事実上の本社機能を東京に置いていて東京のラジオ局のフリをしているので、ベイスターズ戦は中継されない(除く対巨人戦)。ごく希にNHKの横浜FM局(81.9MHz)がベイスターズ戦を中継することがあるが、どこも中継しないので見るに見かねてという感じだ。
この日の対広島戦の場合、広島のRCC中国放送のみが試合を中継していて、インターネット経由のラジコプレミアムで聴くか、直接広島からの電波(1350KHz)を受信するしかない。ラジコプレミアムは有料の上に、タイムラグがあるので生の試合を見ながら聞くには適切ではない(TVKテレビ神奈川のワンセグもタイムラグがあって同様)。
それでこの日は、SONY ICF-SW7600GRを持って行って、広島からの電波を受信して聴きながら観戦した。日没後で屋外で特に電波を遮るものもないので、広島からの電波は安定して受信できた。電波は光と同じ速度で進むので、アナログ放送の場合人が感じられるタイムラグはない(デジタル放送だとデコードに時間が掛かるし、インターネット中継はバッファの時間が掛かる)。
しかし、横浜の試合を横浜から中継して広島からのラジオ放送(RCC 1350KHz)で聴かなければいけないとは…。
対戦相手が中日だと名古屋のラジオ局が、阪神だと大阪のラジオ局が中継するので、同じように名古屋や大阪からの電波を受信すればリアルタイムで試合中継が聴ける。交流戦で対日ハムだと札幌のラジオ局、イーグルスだと仙台のラジオ局、ホークスだと福岡のラジオ局、対西武だと東京の文化放送が中継するからそれを聞けばいいのだが、対ヤクルト、対オリックス、対ロッテの場合、ラジオでは中継されないことが多い。不憫よのぅ。
地元に密着していない某神奈川県域局の免許剥奪して、地域に根ざした別のラジオ局に割り当てればいいのに。同様のことは某兵庫県域局にも言えて、オリックス戦を中継せずに「関西唯一熱烈ジャイアンツ応援ナイター」なんてやっている。免許剥奪だな(笑)。まあ某兵庫県域局が阪神を応援しないというのは、多様な選択肢を用意しているのでよいことなのだが。これが某神奈川県域局になると、他の関東広域局(除く文化放送)と同じ巨人戦を中継するから選択肢がない。
このままベイスターズが優勝しそうになったら東京のラジオ局の扱いも変わるかねぇ(某神奈川県域局は読売系なので変わらないと思う)。
SONY ICF-SW7600GR at YOKOHAMA Stadium:Nikon 1 V1、1 NIKKOR VR 10-100mm f/4-5.6、焦点距離10mm(35mm判換算27mm相当)、F4 開放、1/125秒、AF-A、AFエリア:中央1点、マルチパターン測光、ISOオート (ISO 320)、AWB、ピクチャーコントロール:ポートレート、ニュートラルカラーNC 55mm、バヨネットフード HB-N106
1 NIKKOR VR 10-100mm f/4-5.6の広角端で至近距離にフォーカスしているが、無限遠が二線ボケ傾向ですな。まあその分シャープなレンズだということで。高倍率ズーム(27~270mm相当)ということも考えると許せる。
SONY ICF-SW7600GR北米仕様ゲット ― 2012年09月14日 00時00分01秒
9月1213日の午前中にamazon.co.jpでポチったSONYのワールドバンド短波ラジオSONY ICF-SW7600GR北米仕様が今日(14日)に届いていた。早い。
これはアメリカ向けに輸出したものを日本にもう一度輸入したものらしく、税込15450円だった。国内向けのものはヨドバシカメラで買うと税込33600円(定価税込42000円)するのでほぼ半額である。
ただし、北米向けのものには、ACアダプターが附属していない。また保証書もアメリカ合衆国内限定の保証書なので1年以内に故障しても自費で修理ということになる。あと、ステレオイヤホン、アルカリ単3電池4本、アンテナアダプターも北米仕様には附属していない。
北米仕様のICF-SW7600GRに附属しているのは、
1.アメリカ国内限定の保証書
2.コンパクトアンテナ
3.英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・ノルウェー語・ポルトガル語の取扱説明書
4.WAVE HANDBOOK(英語)
5.キャリングケース
だ。
説明書は英語が嫌な人は日本語版のICF-SW7600GR取扱説明書を検索してくだされ。SONYの取扱説明書ダウンロードのサイトにはICF-SW7600GRの日本語取扱説明書はアップされていない。
さっそくエネループ4本を入れて時間を合わせる(説明書参照:英語でも分かると思う)。問題はアメリカのAMラジオ(中波放送)は10kHzステップなので、日本やヨーロッパの9Hzに変更しないと使いにくいということだ(もちろん1KHzステップでも使えるが聞こえる局を探すときに面倒)。電源を入れてみるとやはり北米向けなのでAMは10KHzステップだ。これは以下の方法で変更できる。
1.電源を切る(POWER OFF)。
2.DIRECTを押す。
3.10秒以内に数字ボタンで「9」または「1」「0」を押す。
4.EXEボタンを押して決定する。
あと、アメリカのFM放送は周波数が87.5MHz~108MHzで、日本では76~90MHzなので日本のFM放送が受信できるか不安な人もいると思う。しかし、ちゃんと76.0~108.0MHzまで受信可能であった。FM放送は北米仕様ICF-SW7600GRでも問題なし。
ACアダプターはなくても困らないし、説明書も何とかなる。アンテナアダプターはICF-SW7600GRのアンテナ端子に専用外部アンテナ用の電源が来ているために、専用以外のアンテナをアンテナ端子につなぐときにあったほうがよいものだが、検索すると代替品や対策がたくさんヒットする。やはり一番のネックは日本での製品保証がないということだろう。私は「SONYタイマー」を信用しているので1年間は壊れないと思っている(笑)。以上のようなことが嫌な人は素直に国内版のICF-SW7600GRを買った方がいいと思う。
使い心地等はまたいずれ。遠隔地のAM局がよく聞こえる。さて、たね蒔きジャーナルを…。
皆様よい週末を!














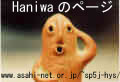

最近のコメント