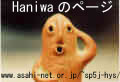ツァイスのZF.2の互換性情報が間違いだらけ… ― 2009年11月19日 00時00分00秒
あんまり揚げ足取りはしたくないのだが、ツァイスのZF.2レンズの互換性情報の表があまりに間違いが多いので取り上げることにした。WEB魚拓を取ってみたのだが、互換性の表の一部が画像でできていて魚拓だと肝心の部分が表示されない。あとでツァイスが差し替えるかもしれないのでスクリーンショットを載せておく(2009年11月19日2時20分JST取得)。
ZF.2: SLR lenses with F bayonet mount for cameras from Nikon(zeiss.com)
【追記:2011年7月15日】
サイトのリニューアルでURLが変わったようなので追記しておく。内容が変わったかは確認していない。
ZF.2: SLR lenses with F bayonet mount for cameras from Nikon(zeiss.com)
【追記ここまで】
FM3AやFEで絞り優先AEができないことになっている。FEは2箇所に書いてあるし。またF-301やF-501でシャッタースピード優先AEができることになっている。前者は「● compatible」にして「1 Can be realized as long as the camera model is equipped with this feature」の註をつけるべきだろうし、後者は「1 Can be realized as long as the camera model is equipped with this feature」の註をつけるのを忘れているのだろう。ほかにも探せば間違いがあるかもしれない。
【追記】
maple様ののご指摘でアイコンの絵が入れ違っているとのことです。ただ、それでもELやFEで絞り優先AEができないことになっているとか、FEが2箇所にあるとかF-301/F-501でシャッタースピード優先AEができるとかまだなんか変だ(笑)。maple様ご指摘ありがとうございました。
【追記ここまで】
まあツァイスってこんなもんなんでしょうな。最初にMaximum image quality meets the comfort of automatic control Carl Zeiss presents a new series of lenses: ZF.2 for F bayonet(zeiss.de)から張ってあったリンク先の互換性のページはZF.2のページじゃなくてZFのページだったし(いまはリンク先が訂正されている)。もうちょっと推敲してくれ。
【関連追記:2009年11月20日】
Carl Zeiss がCPU登載のZF.2レンズを発表、節操のなさに呆れた ― 2009年11月17日
コメント
_ maple ― 2009年11月19日 10時20分20秒
_ Haniwa ― 2009年11月19日 11時35分37秒
なるほど、説明は合ってるんですね。本文に訂正入れておきます。ありがとうございます。
_ あーる ― 2009年11月19日 16時41分24秒
FG-20も見当たらないですね。
まあ、ユーザーの方がよっぽどわかってるからいいですけど。
それよりもカニ爪を残してほしいですよ。
CPUも内蔵した今、今ならむしろ互換性の象徴としてアピールできると思うんですが。「FからD3まで完全に使えます」とか。
Nikonから圧力かかったんじゃないかと邪推してしまいます。そのうち絞り環もなくせ!とかの布石だったらイヤですねえ。
_ ノーネームしたん ― 2009年11月19日 23時13分31秒
!、Haniwaさん!、早速試して見るのです!(泣)。
ここに書きますが
>まあこの人は絞りリングが技術の進歩を阻害するなんて言ってる時点で終わってますが。絞り環がないとその分光学設計やVRなどを入れる自由度が増すのは理解できますが、そうでないレンズまで絞り環無くすこともなかろう、と。
絞りリングは使わない人は全く使わないですから・・、MFカメラ使わないとか、接写リング使ったり、リバースにするとか、そういう使い方しないと付いてるだけの存在だと邪魔としか・・・、自分はF-2にちゃんと使えるなら大きくても良いんですが(友人が以前修理の時に、ニコンで聞いた{絞りリング無くす理由}に、「小型軽量化であって、光学とか、VRは絞りリング付きでも実現可能なんですが、かなり大きくなる可能性が。」とか、言われたという事を話してたな、と、さっき思い出したんですが、レンズが大きくなっても良いのでバージョン違いなんかは作れないんでしょうか・・・。)。
そういえば某誌に”VRオフの時はVR系が動かないようになっている”という事が書かれていました、Haniwaさん!、VR付きGタイプを無理に改造して、絞れるようにする”改造”をするのです!、そしてF-3に付けて撮影を・・・。
_ Haniwa ― 2009年11月20日 09時04分47秒
たしかにEMがないですね。FE2もないです。そもそもなんかカメラの分け方が違っているような気がします。
ZF.2はカニの爪がないですから、フォトミック系を詳しく書いた方がいいようにも思います。
私も、今はカニの爪は使っていないですがNikomat FTnのきれいなのがあったら欲しいですから、カニの爪はあった方がうれしいです。まあ日本カメラのテストレポートも書いている某フリーライターさんは「カニの爪が必要なのはフィルム一眼レフのニコン、それもAi方式以前のニコンであり、それに現代のデジタル対応のレンズを付ける必要があるのだろうか。」なんて言ってますが、このZFシリーズは「当初FやF2用につくったもの」(ぶれげ様のコシナの電話回答 http://haniwa.asablo.jp/blog/2009/11/17/4701002#c4701528 )だそうで、それに加えて「デジタルでもばっちり」というのがツァイスのサイトで強調されていたものですから、まさにカニの爪があって当然のMFレンズなんですね。25mmを除いて光学系はZFとZF.2とで同じなんですから。ああ私はこの論理破綻したライターさんをスルーできないなぁ(苦笑)。田中希美男氏は毎回スルーしていて偉いと思いました。
>Nikonから圧力かかったんじゃないかと邪推してしまいます。
その発想はなかったです。しかし、今回のCPUをどこから調達したのかということを考えますとあり得ない話ではないですね。「シグマは自分のところで解析して自前でCPUを作ってレンズに載せているが、それ以外のレンズメーカーは純正のCPU(チップ)を純正メーカーから買っている」と10年以上前にサンダー平山氏がどこかで(たぶんCAPA)書いていました。そうするとZF.2のCPUをニコンから買うに当たってカニの爪はもう付けないで欲しいという条件が付けられる可能性はありますね。フォクトレンダーSL II のカニの爪も同じかもしれません。あくまでも想像での可能性の話ですが。
■ ノーネームしたん様
ないモードをどうやって実現するのですか(笑)。もしかしてZF.2レンズの絞りリングに「A位置」があって、F-501のシャッターダイヤルのスピードで絞りが自動で選ばれるのかも!(笑)
>友人が以前修理の時に、ニコンで聞いた{絞りリング無くす理由}に、「小型軽量化であって、光学とか、VRは絞りリング付きでも実現可能なんですが、かなり大きくなる可能性が。」とか、言われたという事を話してた
これは貴重な情報をありがとうございます。実現不可能とは言わないところがニコンらしいですね。ニコンFマウントに不可能なし、と(笑)。デジタル対応で光束の入り方とかがフィルムよりも制限があってそのためにレンズの根元が狭いのを克服しようとすると光学系が大きくなってしまうんでしょうか。レンズ側での手ブレ補正(VR)は、フィルムカメラでも機能するのがメリットですが、VRの機能するカメラは絞りリング無しで使えるカメラですから、VRかつ絞り環ありという必要性があまりないと判断されるんでしょうね。F3ではMFレンズとしてF100やデジタル一眼レフではVR付きのAFレンズとして使えるような70-200mm F2.8といったレンズがあれば理想的ですが、かなり高くなるんでしょうねぇ。経済がよければそういうバージョン違いもありうるかもしれません。
>”VRオフの時はVR系が動かないようになっている”
そうですよね、そうでないとVR 80-400mm F4-5.6DをMFカメラで使うときに困りますから。その辺はよく考えて作ってあるなぁと思いました。電気がない状態では普通のズームレンズとしての光学系を保っている、と。Gタイプに絞り設定を機械的にうまくできる方法はないものでしょうかねぇ。鏡筒を元に戻せないぐらいに改造するのなら方法はありそうですが、レンズが根元からポキッといきそうな…。
_ ノーネームしたん ― 2009年11月20日 21時35分24秒
確か2005年夏の終わりごろに言われた事らしいんですが(レンズの修理清掃に出す時に)、ゴト氏とかに今聞いたりすると、ぜんぜん違う事言ったりして・・・。
_ Haniwa ― 2009年11月25日 10時44分41秒
お返事遅くなってすみません。
違うこと言いそうですね(笑)。ゴト氏は「神がそう仰せになったのだ」として自分はなにも変わっていないというかもしれませんが(笑)。
アサカメの預言者ゴト氏の記事よりも、赤城耕一氏の記事の方が面白かったです。カメラ雑誌にあそこまで書ける人は他にはいないのでは(笑)。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。