フィルムとデジタル撮影での被写界深度の違い(Ai Nikkor 20mm F2.8SとCOLOR-SKOPAR 21mm F4 P) ― 2025年06月25日 00時00分00秒
COLOR-SKOPAR 21mm F4 Pを新品購入したら、前玉内側に傷があって交換してもらった際に、マウントアダプターの精度の問題やレンズの被写界深度表示に合わせても無限遠までピントが来ない問題(過焦点距離)など色々と悩んだ。
COLOR-SKOPAR 21mm F4 Pを新品で購入したが… ― 2025年05月25日 11時05分00秒
COLOR-SKOPAR 21mm F4 P 交換品無事に届く ― 2025年05月25日 19時06分
富士フイルム、フィルム現像をスマホで完結できるアプリ「写ルンです+」を公開 ― 2025年05月29日
焦点工房のLM-NZ II マウントアダプター購入 ― 2025年05月29日
Rayqual LM-NZマウントアダプターが出荷された ― 2025年06月04日
Rayqual LM-NZマウントアダプター + COLOR-SKOPAR 21mm F4 P ― 2025年06月06日
上記リンク先の最後の記事にみっち様がコメントをくださり、以下のように解説してくださっています。
みっち ― 2025年06月06日 18時23分01秒
>荒野の故障ブログへようこそ(泣)…
おっ、流石はHaniwa氏!というところなんですが、ちょいと疑問があります。
というのは、無限遠でピントがちゃんと合っているレンズで、途中の距離目盛表示が大きく狂っているのって、そんな事ありうるのかなぁ、という疑問です。そもそも、ここで云ってる被写界深度って、許容錯乱円径を0.033mmに取った場合の話だと思います。これで計算すると、焦点距離21mm、F8、距離2mでは、後方被写界深度は無限遠になります。でも、この0.033mmって、確たる科学的根拠に基づくものではなく、フィルム時代の話で、六つ切りだか四つ切だかの印画紙にプリントした画像を1mくらいの距離から視力健常な人が見てボケがない、とかが元になっていたような記憶があります。
一方デジタルでは、平気で等倍鑑賞しますので、この許容錯乱円径をいくつに設定するかは、かなり難しい問題です。フルサイズデジタルカメラで2400万画素ですと、だいたい画素ピッチは0.006mmくらいだと思います。許容錯乱円径を画素ピッチの2倍とすると、0.01mmくらいであり、上記条件での後方被写界深度は1mちょっとしかありません。これでは厳しすぎではないか、ということで許容錯乱円径を0.02mmとすると、後方被写界深度は5mちょいくらいです。
この問題は、昔から色々なサイトで議論されていたような。どこかに定説があるのかなぁ、まぁ、みっちが今思いつくのはこんなところです。
https://haniwa.asablo.jp/blog/2025/06/06/9780667#c9780707
みっち様ありがとうございます。
それで、CONTAX G用Biogon T* 21mm F2.8にはピントリングも距離指標もないので試せないが、Ai Nikkor 20mm F2.8S(Ai Nikkor 20mm f/2.8S)には、距離指標も被写界深度目盛りもあるので、2m・F8で試してみた。Rayqual LM-NZマウントアダプター + COLOR-SKOPAR 21mm F4 P ― 2025年06月06日でCOLOR-SKOPAR 21mm F4 P試した2m・F8とどう違うのか同じなのか。
【写真1_1】秋葉原・神田川(和泉橋から神田ふれあい橋方向を望む):Nikon Z6、Ai Nikkor 20mm F2.8S、F8、絞り優先AE、1/200秒、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(5810K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、FTZマウントアダプター、L37Cフィルター、フードなし、JPEGをリサイズ、ピントは「神田ふれあい橋」に合わせてある
【写真1_2】秋葉原・神田川(和泉橋から神田ふれあい橋方向を望む)【写真1_1】の中央部分をトリミング:Nikon Z6、Ai Nikkor 20mm F2.8S、F8、絞り優先AE、1/200秒、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(5810K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、FTZマウントアダプター、L37Cフィルター、フードなし、ピントは「神田ふれあい橋」に合わせてある
【写真1_3】秋葉原・神田川(和泉橋から神田ふれあい橋方向を望む)【写真1_1】の左側をトリミング:Nikon Z6、Ai Nikkor 20mm F2.8S、F8、絞り優先AE、1/200秒、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(5810K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、FTZマウントアダプター、L37Cフィルター、フードなし、ピントは「神田ふれあい橋」に合わせてある
ピントを「神田ふれあい橋」に合わせると、F8でも手前の「処方せん受付」のとこころまではピントは来ていない。ちなみにZ6のフォーカスピーキング機能では、F8に絞った状態では無限遠突き当てよりも少し手前の方がピーキングが強く表示されているし、拡大機能で見ても無限遠よりも手前にした方が鮮明なので、これらの写真はAi Nikkor 20mm F2.8Sの無限遠突き当てよりも少し手前になっている。
【写真2_1】秋葉原・神田川(和泉橋から神田ふれあい橋方向を望む):Nikon Z6、Ai Nikkor 20mm F2.8S、F8、絞り優先AE、1/200秒、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(5810K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、FTZマウントアダプター、L37Cフィルター、フードなし、JPEGをリサイズ、ピントはピントリングの2mに合わせてある
【写真2_2】秋葉原・神田川(和泉橋から神田ふれあい橋方向を望む)【写真2_1】の中央部分をトリミング:Nikon Z6、Ai Nikkor 20mm F2.8S、F8、絞り優先AE、1/200秒、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(5810K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、FTZマウントアダプター、L37Cフィルター、フードなし、JPEGをリサイズ、ピントはピントリングの2mに合わせてある
【写真2_3】秋葉原・神田川(和泉橋から神田ふれあい橋方向を望む)【写真2_1】の左側をトリミング:Nikon Z6、Ai Nikkor 20mm F2.8S、F8、絞り優先AE、1/200秒、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(5810K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、FTZマウントアダプター、L37Cフィルター、フードなし、JPEGをリサイズ、ピントはピントリングの2mに合わせてある
こうしてみると、Ai Nikkor 20mm F2.8Sで2m・F8にした方が被写界深度は深いのではないだろうか。COLOR-SKOPAR 21mm F4 Pの場合だと2m・F8だとどこにもピントが合っていない感じだったからだ。両レンズの像面湾曲がどれぐらいあるのかわからないので、真ん中と左側とで両レンズを比較して被写界深度が深いのか浅いのかを即座に判断することはできない。
しかし、今回のAi Nikkor 20mm F2.8Sだと、ジャストのピントにはなっていないが、鑑賞サイズによってはピンボケ判定にはならない感じだ。他方、COLOR-SKOPAR 21mm F4 Pの方は、遠くの神田ふれあい橋は明らかにピンボケだし、もっと近くの「処方せん受付」も鮮明ではなかった。
Rayqual LM-NZマウントアダプター + COLOR-SKOPAR 21mm F4 P ― 2025年06月06日参照
これだと、Ai Nikkor 20mm F2.8Sを使っている分には、「デジタルだと若干被写界深度が浅いけどまあ似た感じには使える」と思ってしまう。計算上はみっち様の仰るとおりだし、富士フイルムのサイトでも以下のように書かれている。
どこにピントを置くか、それは重要だ。どこまでピントを合わせるか、それも重要だ。しかしその基準は、きちんとあなたの目的・感覚に合わせてあるだろうか?
X-Pro2では、”被写界深度スケール”を”ピクセル基準 / フィルム基準”という2つの基準から選択できるようになった。これこそは、あなたの目的・感覚とカメラ設定をアジャストさせるための項目なのだ。
厳密なことをいうと、光学的にはピントが合っているは場所は、レンズ平面軸と平行なある一つの平面しかない。そこから1mmずれただけでもピントは合っていない。その面以外は”ボケ”ている。理論上は。しかし実際は、このボケ量が無視できるほど小さい場合は、ピントがあっているように見える。 そう”被写界深度”とは、ピントがあっている面とその前後にある(理論上はボケているのだが)、ボケてないように見える部分のことなのだ。
また、ピントから外れた面で発生するボケを”錯乱円”と呼んでいるが、ピントがあってるように見える程度の小さなボケを”許容錯乱円”と定義している。”許容錯乱円”が大きいほど、”被写界深度”は深くなる。つまり、”被写界深度”は”許容錯乱円”に比例する。
問題は、この”許容錯乱円”が、イメージャーの解像度や鑑賞媒体によって変わってくるということなのだ。
事実、昨今のデジタルセンサーは銀塩フィルムの解像力を超えており、許容錯乱円は小さくなっている。それに加え、ピクセル等倍表示がポピュラーになり、”許容”される錯乱円はさらに厳密になった。”浅く”なった”被写界深度”は、より厳密なピント位置・ピント範囲を追求するようになったとも言える。”ピクセル基準”の被写界深度は、そういった用途のためにある。
しかし、そもそも被写界深度とは”深い”からこそ意味がある概念とも言える。”深度”の深さを利用するスナップ撮影などでは、厳密すぎるスケールではむしろ用を成さないだろう。
ストリートに立つ、絞りをF8にセットする。光を探す。構図を決める。被写体がくる位置を予測する、そこをめがけてピント位置を決める、多少のズレは”被写界深度”がカバーしてくれる。そういった撮影では、ある程度の”許容”範囲を持ったスケールのほうが使いやすい。
それは、銀塩フィルム時代から受けつがれている肌感覚と言ってもよい。そして、その感覚にマッチさせた基準が”フィルム基準”なのだ。(※数値としては、4ツ切りプリントで出力し、標準的な鑑賞距離で見た場合の許容錯乱円をベースにしている。)
どちらが正しいかではない。目的・感覚に合わせて選択するのが正しい。鑑賞するサイズが決まっているのならば、それに相応しい方を選べば良い。二つから選べるのだから、それらを行き来しても良い。 ちなみに、XF14mmやXF16mm、XF23mmのような鏡筒に被写界深度スケールを持っているレンズの場合は、”フィルム基準”をベースに目盛が刻まれている。目測+マニュアルフォーカスで速写するような撮影スタイルには、この3本のレンズは非常に使い勝手が良い。
被写界深度考察(2016.04.21 富士フイルムX Stories)
ということで、Ai Nikkor 20mm F2.8SをZ6で使うときは絞ればかなり被写界深度に入るがフィルムよりは浅い、COLOR-SKOPAR 21mm F4 PをZ6で使うときは被写界深度はかなり浅く絞っても深度内に入るかは分からないということのようだ。しかし、レンズによってこんなにも被写界深度が違うのだろうか。やっぱりコリメーター(以下自粛)。
こうなると、たくさん持っている28mmでも試したくなってくるじゃないか(泣)。あと、距離環はあるけれども回転角が小さくて距離指標の無限遠の隣は0.4mのAF-S NIKKOR 20mm f/1.8G EDでも2mのものにピントを合わせた後そのままでF8で撮ってみたくなるじゃないですかぁ。神田和泉橋上でメジャーを出して2m測っている人がいても、「お前、Haniwaだなっ」と羽交い締めにしないで暖かく見守ってください(泣)。
8TBのHDDから12TBのHDDにコピーで苦戦 ― 2025年06月24日 00時00分00秒
デジタルとフィルムで被写界深度が異なる話は、Ai Nikkor 20mm f/2.8Sの作例も揃ったので執筆したいのだが、モニターがマシなデスクトップPCが以下の理由で塞がっているのでもう少し待って欲しい。
さて、その自宅のデスクトップPCが塞がっている理由は以下だ。データ用ドライブ(8TB)の空きが残り1割を切ったので、エクスプローラーで表示するとドライブが真っ赤に表示されるようになった。それでWD Blue 12TB WD120EAGZと裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6G とを買った話はした。
WD Blue 12TB WD120EAGZと裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6G
特に、裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6G は、2台のHDDやSSDを搭載できて、裸族のお立ち台TWIN単体でコピーができるとのことで期待していた。うちのデスクトップPCは古いので、マザーボードがデータ転送速度3Gbpsにしか対応していないので、単体でそれよりも速い速度でコピーできるのはありがたいのだ(コピー中にPCで他のことをできるし)。なお、このデスクトップPCは、USBについてはUSB3.1の増設カードで対応しているのだが、USB3.1の5Gbpsをフルには活かせない状況だ(マザーボードがボトルネックになっている)。まあ購入当時のUSB2.0の480Mbpsよりははるかにマシなのだが。
しかし、WD Blue 12TB WD120EAGZとWD Blue WD80EAZZを裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6Gに刺しても、転送が始まってしばらくするとアクセスランプが消えてしまう。ドライブは両方とも回転してはいるが、コピーしている気配はなくなる。うーん、WD Blue 12TB WD120EAGZは2025年5月に発売開始になったばかりで、裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6Gの「確認済み」のHDDには書いていなかったからなぁ。何度か試してみたが、裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6G単体でのコピーはできなかった(泣)。
さて、そうなると、PCを介してコピーするしかない。WDのHDDにはAcronis True Image for Western Digitalというソフトウェアが無償で公開されていて、以前にダウンロードしたことがある(使ったのか記憶にないがインストールされていた)。それの2016年版を使って見たら、途中でユーザーインターフェースが消えてしまって何をやっているのかやっていないのかわからない状態になったので、慌てて最新版をインストールした。
しかし、このAcronis True Image for Western Digitalで快調にコピーしていると途中で「ディスクにデータを書き込むことができません。ハードディスク'○'のセクタ'×××'に書き込むことができませんでした。Failed to write the snapshot manager drive.(0x10000DA)状態が不明です。(0x9)セマフォがタイムアウトしました。(0xFFF0)」というダイアローグが出て止まる。'×××'のセクタ部分は毎回同じ。
書けないセクタがあるんなら飛ばして書き込んでくれればよいものを、Acronis True Image for Western Digitalはおそらくファイル単位で書き込んでいるのではなく、ドライブ全体をイメージとして丸ママコピーしようとしているのだろう。だから書き込み先がちょっとでも違うと完全イメージコピーにならなくなるので書けなくなるのだろう。ちなみに「無視」としても「すべて無視」としてもアプリがフリーズしているのかして先へ進まなくなる。
こうなったらExplorerかコマンドプロンプトでコピーするしかない。これは以前エクスプローラでやったら6TBぐらいで3日掛かった記憶がある。コマンドプロンプトでxcopyコマンドでコピーすることにした。ただ、これもすんなり行ったわけではなく、Acronis True Image for Western Digitaで半端にコピーしたドライブは、もういちど「ディスクの管理」で「新しいシンプル ボリューム」としてフォーマットしないとPCから認識されない。これで相当時間を食った。
さてxcopy l:\ m:\ /s /e /h /i /c /yと、管理者権限でコマンドプロンプトに入れてコピーが始まった。寝ていたら階下のリビングからPCに入れている緊急地震速報のベルがずっと鳴っているのが聞こえる。PCには緊急地震速報のアプリを入れていて、現在地で揺れがほとんどなくても遠隔地で初期値がM5.0以上なら鳴るようにしてある。それが鳴っているのだ。しかも2分とか経ってもまだ鳴っているということは、遠隔地のM5.0以上の地震なのだろう(あとでみたら最近多発しているトカラ列島付近の地震らしい)。
嫌な予感がして1階に降りてPCをみたら、コマンドプロンプトがコピー途中でカーソル点滅になってコピーしていない(コピーしていたらコピー中のファイル名が延々流れて行っているはず)。enter押したりしてもコピーは再開しない。きっと緊急地震速報アプリが割り込んでコピーが中断されてしまったのだろう。これ、また1からコピーしないといけなくなる(泣)。
そうだ、いつもバックアップに取るのに使っている FreeFileSyncなら差分でコピーが取れるので、すでにコピー済みのファイルは飛ばしてコピーしてくれる。なんで気がつかなかったんだ。
朝になったらFreeFileSyncで5TBぐらいのコピーが終わっていて、あと12時間とかなんとか表示されている。しかし、しばらく見ていると、コピー元もコピー先もアクセスランプが点かなくなってコピーが止まっている。タスクマネージャからFreeFileSyncのタスクを終了させても停止しない。これはなんかフリーズしてるな。仕方ないので、PCを再起動したが、再起動が全然終わらない。これはAcronis True Image for Western Digitalをインストール以降そうなっているみたいなので、強制終了をして起動後にAcronis True Image for Western Digitalをアンインストールして再起動を掛けた。そうしたら、以前のように普通にすんなり再起動した。なんかAcronis True Image for Western Digitalは以前にもそんなことがあったような気がしたが、ブログの過去記事を漁るのも面倒なので、さっさとコピーを再開する。
もう一回FreeFileSyncで残りの3TB弱をコピーしていたら、こんどは強震モニタが関東地方の何かの揺れに反応してポップアップして、またコピーが止まった(泣)。
もう一回FreeFileSyncで残りをコピー。残り9時間ぐらいだそうな。
FreeFileSyncは、タイムスタンプとファイルサイズで同じファイルかどうかを判定して(何で判定するのかは細かく設定可能)、同じファイルだったらコピーしないので、途中までコピーしたドライブをコピー再開する際にも時間が無駄にならないのだ。
今日中にコピー終わるかなぁ。
【追記:2025年6月25日】
昨晩寝る前にはコピーが終わらなかったが、朝起きたらコピーは完了していた(嬉)。最後にもう一回ドライブD(内蔵SATA 8TB)→ドライブL(外付けUSBバックアップ用 8TB)→ドライブM(外付けUSB 12TB)とFreeFileSyncで同期させて(これは差分コピーなので時間が掛からない)、PCの電源を落として、内蔵の8TBを12TBに交換した。交換して内蔵しても12TBはドライブレターがMのままなので、「ディスクの管理」からドライブレターをDに変更した。うちの環境では、マイドキュメントなどはすべてDドライブに置くように設定を変更しているので、Mのままでは色々と困るからだ。普通に全部Cドライブに置いている人はドライブレターの変更をしなくてもよいかもしれないが、マイドキュメントなどをCドライブに置かないのは、OS再インストールの際にデータは無関係とかCドライブに容量の小さい(安い)SSDを置けるとかいろいろメリットがあるのでお勧めしたい。
なお、HDDのドライブレターがLとかMとか飛んでいるのは、このPCには光学ドライブが2基(DVDマルチとDVD/Blu-ray)とか、カードリーダーを繋げっぱなし(SDとかカードの種類ごとにドライブレターが割り当てられている)ので、EからKまで埋まっているからだ。ちなみにZもEPSONの複合機のUSBメモリスロットが勝手に割り当てられている(使ってないし、USBではなくネットワーク接続なのになぜドライブレターが割り当てられているのか謎)。ドライブAやBはWindowsではフロッピーディスク割り当て用なので使っていない(USBのFDDは持ってはいるが)。
【追記ここまで】
【さらに追記:2025年6月25日】
みっち様のコメントのお返事を書いていて、HDDコピーについて考えがまとまったので、記事本文中にも書いておく。
「HDDコピーは、余っているPCにFreeFileSyncで」
で、普段使っていないものだから久々に出したらアップデートの嵐でコピーが進まない地獄が始まる気が…(泣)。
【さらに追記ここまで】
【追記その3:2025年6月25日】
大事なことを書き忘れていた。WD Blue 12TB WD120EAGZは、裏面のネジ穴が4箇所しか無い。真ん中の2箇所にネジ穴がないので、裏面のネジ穴で真ん中の2箇所を使う方法で内蔵固定しているPCでは要注意だ。DELL Vostro 430はHDDの裏面のコネクタ側2箇所と真ん中の2箇所の計4箇所で留めているので、WD Blue 12TB WD120EAGZは、コネクタ側の2箇所だけで留めることになってしまった。ネジ止めのない側は一応脱落防止のガードがあるが、HDDは常時回転していて振動があるのでちょっと心配だ。たまに内部の埃を掃除するときにねじが緩んでいないか点検するようにしよう。なにかアダプタみたいなのはないのかなぁ。いっそのこと使っていないFDD用の2.5インチスロットにアダプターで固定できないかなぁ。Windows10のサポート終了まで持てばよいので、ときどきねじ弛みチェックでよいか。あとは、バイクに使っている3Mのゆるみ止め用嫌気性接着剤を塗っておくとか。
【追記その3ここまで】
ニコン【期間限定】新サービス「定期メンテナンス ゴム交換オプション」 ― 2025年06月18日 00時00分00秒
忙しくて今日は更新するつもりがなかったのだが、ニコンが【期間限定】新サービス「定期メンテナンス ゴム交換オプション」開始に伴う「定期メンテナンス 割引キャンペーン」のご案内という告知を出しているので更新だ。「ゴム交換」に反応してしまった(笑)。
「ゴム交換オプション」ってなんぞや?
このたび新サービスとして、通常の「定期メンテナンス」サービスにミラーレスカメラおよびミラーレスカメラ用交換レンズの外観ゴム交換をセットにした「定期メンテナンス ゴム交換オプション」サービスを開始します。
(ミラーレスカメラの外観ゴム交換については、分解作業が必要な場合がございます。)イメージセンサー清掃・レンズ表面清掃・外観ゴム交換の作業イメージ
(写真略)
ゴムフェチ歓喜ですな(違)。大事なのは以下だ。
新サービス開始に伴い、2025年7月1日から9月1日までの期間限定で、「定期メンテナンス」、「定期メンテナンス ゴム交換オプション」のサービス料金から最大20%割引になるキャンペーンを実施いたします。
キャンペーン概要
名称: 「定期メンテナンス 割引キャンペーン」
期間: 2025年7月1日(火)~2025年9月1日(月)受付まで
インターネットでのお申込み 9月1日(月)23:59まで
サービスセンター窓口でのお申込み 9月1日(月)まで(事前予約が必要となります)
内容: キャンペーン期間内で、「定期メンテナンス」、「定期メンテナンス ゴム交換オプション」をご利用いただいた方を対象に、サービス料金から最大20%割引をいたします。
対象製品: ミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、交換用レンズ
料金: (税込)表示金額はキャンペーン割引適用前の料金となります。
「定期メンテナンス」 「定期メンテナンス ゴム交換オプション」 ・ミラーレスカメラ ¥10,670~ ・ミラーレスカメラ ¥18,590~ ・デジタル一眼レフカメラ ¥10,120~ ・デジタル一眼レフカメラ ¥14,410~ ・交換用レンズ ¥6,050~ ・交換用レンズ ¥7,040~
「MF(マニュアルフォーカス)旧製品メンテナンスサービス」は去年2024年にやったばかりなので、今年はないのかのぅ……。。
写真は記事とは関係ない。
【写真】国鉄110形蒸気機関車(横浜市中区):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F8、絞り優先AE、1/40秒、ISO-AUTO(ISO 250)、AWB(5920K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)、専用フード、JPEGをリサイズ
3万7,000円のティルトレンズ「TTArtisan Tilt 35mm f/1.4」(デジカメWatch) ― 2025年06月16日 00時00分00秒
APS-C/マイクロフォーサーズに対応の3万7,000円のティルトレンズ「TTArtisan Tilt 35mm f/1.4」が発売になったようだ。
3万7,000円のティルトレンズ「TTArtisan Tilt 35mm f/1.4」(デジカメWatch)
APS-Cサイズのイメージセンサーに対応するMFレンズ。35mm判換算での焦点距離は54〜70mm相当(レンズマウントによって異なる)。ティルトおよび回転機構を搭載している。
レンズを左右それぞれ最大8°まで傾けることができ、奥行きのある被写体に対し、広範囲にピントを合わせられる。一方、ピント面を意図的に狭くしてミニチュア風の写真表現を作り出すことも可能。
ティルト(チルト)というと最近は、ある線を境に前後をぼかしてミニチュア風に撮ることばかり強調されているが、もともとはピント面を斜めにして絞らなくても全面にピントを合わせるものだったはずだ。そのような用途では、レンズに像面湾曲がないことや歪曲収差の小ささや解像力も要求されるために、逆の使い方のミニチュア風の方を強調しているのかもしれない。
そういえば、PC Nikkorって今はどうなんだろうと思って、ラインナップを見に行ったら、PC NIKKOR 19mm f/4E EDもPC-E NIKKOR 24mm f/3.5D EDもPC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D EDもPC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8DもPC Micro-Nikkor 85mm f/2.8DもPC Nikkor 28mm F3.5も、「旧製品」になっていた。Zマウントにはティルトやシフトのできるレンズはないから、要するにティルト・シフト可能な現行製品はニコンにはないということになる。
Fマウントレンズ製品一覧 (旧製品)
他方でキヤノンはTS-E17mm F4Lはまだ現行品だし、キヤノンの3D VRレンズが「Apple Vision Pro」新機能に対応(デジカメWatch)のような特殊レンズもある。ニコン、どうなってんの?
写真は記事とは関係ないけど、PC NIKKOR 19mm f/4E EDほしいよなぁ。
【写真】ランドマークタワー(横浜市西区みなとみらい):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F8、絞り優先AE、1/250秒、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(6080K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)、専用フード、JPEGをリサイズ
WD Blue 12TB WD120EAGZと裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6G ― 2025年06月14日 00時00分00秒
今日の関東地方南部は夕方から雨だというので、ずっと気になっていたハニワニワの草取りを、午前中にした。予報よりも早めに雨が降ってきたが、取った草をゴミ袋にまとめているときに降ってきたのでギリギリセーフだった。身体は疲れたが、精神的にはすっきりした。
さて、Haniwa家のリビングにあるデスクトップPC(Windows10 PRO 64bit)は家族共用になっていて、テレビを見ていたり家族の会話でなにか気になることがあったら即座に検索したりするような使い方になっている。しかし、Core i5 第1世代という超古参なので、Windows11にはできず、今年中に(というかWindows10サポート切れの10月よりも前に)新しいPCに買い換える予定である。
そのデスクトップPC(DELL Vostro430)は、マザーボードとCPUとグラフィックカード以外はほとんど購入時とは構成が変わってしまっており、数々のトラブルを部品交換で凌いできた。現在はCドライブが500GBのSSDで、データ用のDドライブが8TBのWD Blue WD80EAZZだ。その前に8TBのSEAGATE ST8000DM004(SMR)にしていたのだが、CrystalDiskInfoで「注意」になったので、CMRのWD Blue WD80EAZZに交換したのだ。最近は新しく買うHDDはほとんどWDばかりになってしまった。
SEAGATE ST8000DM004がCrystalDiskInfoで「注意」に ― 2023年05月11日
それで、その8TBがかなりいっぱいになってきていて、残り700GBぐらいしかないので、エクスプローラーで表示するとDドライブが赤く表示されてしまう。SEAGATE ST8000DM004から載せ替えるときに8TBよりも容量が大きなものにすればよかったのだが、当時は8TBを超えると急に値段が高くなっていたので、安い8TBでごまかしたのだ。しかし、今度はそうはいかない。
それで10TBの方が12TBよりも安いのだが、10TBだと2TBしか余裕がないので、仕方なく12TBのHDDを買うことにした。また、SMR方式のHDDはどうも信頼性に欠けるし、読み書きも遅い。大容量でCMRのHDDがあれば、多少高くてもCMRにしたい。
そこで、12TBのCMRで探すと、WD Blue 12TB WD120EAGZが安めだった。ドスパラの通販で WD120EAGZが33,280円だったのでそれを買った。当日出荷で翌日には届いた。
さて、問題は、8TBのHDDの内容を12TBのHDDにコピーするのに時間が掛かることだ。以前8TBをコピーするのに、普通にエクスプローラーでコピーしたら3日ぐらい掛かった。今回も3日掛かってコピーしてもいいのだが、3日間リビングのPCが使えないのは困る。以前よりも家族がPCを使う頻度が上がっているのだ。
そこで、調べると、CENTURYの裸族のお立ち台シリーズに、TWINというのがあり、それ単体で2台のHDDをコピーできるらしい。「裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6G」というものだ。ヨドバシで 6,280 円なので買った。これで、PCを使わずにHDD間でコピーできる。その間、デスクトップPCには、バックアップ用に使っている外付けHDDに入っているWD Blue WD80EAZZを入れることにした。そうするとIntelliParkを無効化できるので、ついでにやっておきたい。
WD Blue WD80EAZZにはIntelliParkという「罠」が ― 2023年05月15日
手順としては、まず新品のWD Blue 12TB WD120EAGZをクイックフォーマットしておく。次に内蔵HDDのDドライブWD Blue WD80EAZZのデータを外付けHDDのWD Blue WD80EAZZにコピーして両者を同じ内容にする。コピーには、差分コピーのできるFreeFileSyncを使っている。
次に、デスクトップPCからDドライブのWD Blue WD80EAZZを取り出して、外付けHDDのWD Blue WD80EAZZをPCのDドライブに入れる。
PCから取り出したWD Blue WD80EAZZをコピー元とし、フォーマットしたばかりのWD Blue 12TB WD120EAGZをコピー先にして、「裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6G」でコピーする。
コピーが終わったら、デスクトップPCの内蔵DドライブWD80EAZZとWD Blue 12TB WD120EAGZをシンクロさせて、WD Blue 12TB WD120EAGZが最新のデータ内容であるようにする。そのあと、WD80EAZZとWD Blue 12TB WD120EAGZを入れ替えて、デスクトップPCにはWD Blue 12TB WD120EAGZがDドライブとして内蔵されている状態にする。これで完成のはず。一番要注意なのが、裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6Gでコピー元とコピー先を逆にしないようにすることだ。
それで、バックアップ用のHDDはどうするか。もう1台WD120EAGZを買ってもいいのだが、出費がアレなので、8TB2台に分散してバックアップしようかとも思っている。具体的には、データ量の多い「ピクチャ」とそれ以外のDドライブ全部の2つに分けてバックアップするとか。
Windows10のサポートが切れるまでに新しいPCを買わねばならないので、あまりお金を使いたくないのだ(泣)。新しいPCを買った暁には、この12TBはそのPCに内蔵してDドライブにするつもり。
「裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6G」で8TB弱のデータは、どのくらいの時間でコピーできるのだろうか。説明書には参考値として、2TBのコピーに180分とある。3時間か。8TBだと12時間。参考値だからそんなに甘くはないような気もするが、まあ扇風機当てたまま放っておけばコピーは終わるからいいか。
https://www.century.co.jp/products/manual/CROS2U3CP6G_m06.pdf
【追記:2025年6月24日】
WD Blue 12TB WD120EAGZとWD Blue WD80EAZZを裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6Gに刺しても、転送が始まってしばらくするとアクセスランプが消えてしまい、コピーできないようだ。WD Blue 12TB WD120EAGZは2025年5月発売の新しいHDDで、裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6Gの確認済みHDDには記載されていないので(執筆時現在)、仕方ない。PCを介してコピーすることになった。
8TBのHDDから12TBのHDDにコピーで苦戦 ― 2025年06月24日
【追記ここまで】
【追記】WD Blue 12TB WD120EAGZの仕様表を追記しておく。
WD120EAGZ | WesternDigital WD Blue SATA3 6Gbps(SATA6G) 3.5型ハードディスク 12TB WD120EAGZ(CFD)からHaniwaが作成。
| 製品名 / 型番 | WD120EAGZ | |||
|---|---|---|---|---|
| JAN | 0718037907888 | |||
| シリーズ | WD Blue | |||
| フォームファクター | 3.5インチ | |||
| インターフェース | SATA 6 Gb/s | |||
| フォーマット済み容量 | 12 TB | |||
| 書き込み方式 | CMR | |||
| 対応機能 | Advanced Format(AF) | |||
| パフォーマンス | 最大インターフェース速度 | 6Gb/s | ||
| 電源管理 | 平均所要電力(W) 読み取り/書き込み | 8.8 | ||
| 平均所要電力(W) アイドル | 6.1 | |||
| 平均所要電力(W) スタンバイ/スリープ | 0.3 | |||
| 12VDC ± 5% (A、ピーク) | - | |||
| パフォーマンス | キャッシュ(MB) | 512 | ||
| 回転速度(RPM) | 7200 | |||
| 最大内部転送レート | 260 MB/s | |||
| 信頼性/データ整合性 | 保証 | 2年 | ||
| ロード/ アンロードサイクル | 300,000 | |||
| ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー | 10E14あたり1回 | |||
| MTBF (時間) | - | |||
| ワークロード率 (TB/年) | - | |||
| 使用環境 | 温度 動作時 (℃) | 0 ~ 60 | ||
| 温度 非動作時 (℃) | -40 ~ 70 | |||
| 耐衝撃性 稼動時(2 ms、書き込み) (Gs) | 70 | |||
| 耐衝撃性 稼動時(2 ms、読み取り) (Gs) | 70 | |||
| 動作音 アイドル (dBA) | 34 | |||
| 動作音 シーク(平均) (dBA) | 39 | |||
| 寸法等 | 本体寸法 | 26.1 x 147 x 101.6 mm | ||
| 重量 | 0.75kg(±10%) | |||
| 対応 | RoHS:◯ | |||
| PSE:対象外 | ||||
| 電波法:対象外 | ||||
| 関連リンク | メーカーリンク:https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/wd-blue-desktop-sata-hdd?sku=WD120EAGZ | |||
| 備考 | * ストレージ容量の単位は、1メガバイト(MB)=100万バイト、1ギガバイト(GB)=10億バイト、1テラバイト(TB)=1兆バイトです。使用可能な総容量は、動作環境により異なります。バッファまたはキャッシュの単位は、1メガバイト(MB)=1,048,576バイトです。転送速度またはインターフェースの単位は、毎秒1メガバイト(MB/s)=毎秒100万バイト、毎秒1メガビット(Mb/s)=毎秒100万ビット、毎秒1ギガビット(Gb/s)=毎秒10億ビットです。 | |||
【関連追記:2025年7月19日】
HDDの健康診断している?いつの間にか寿命が来ているかも?!壊れる前に買い替えを検討しよう 4~6TB HDDからの買い替えるなら10~12TB HDDがオススメ text by 坂本はじめ (PC watchのWestern Digitalによるスポンサー記事)
【関連追記ここまで】
COLOR-SKOPAR 21mm F4 P + Nikon Z6(作例通算9回目) ― 2025年06月11日 00時00分00秒
デジタルとフィルムの被写界深度とか、赤城耕一の「アカギカメラ」第119回:実用性と趣味性を両立、しかも廉価なニコン「Z5II」の紹介やRICOH GRシリーズ用のフィルター組み込みレンズフードに新色「ゴールドリム」を見て、フィルター部分にフードが掛ってないとフィルターに光が当たってよくないじゃないかとかそういえばGRにフィルターネジ枠付けろよとか(さらにフラッシュ無くすなとか)いろいろ書きたいことはあるのだが、作例貼るだけで済ます。すまん。【追記】そういえばバイクで千葉に行ったJR久留里線上総松丘駅 ― 2025年05月19日と国道410号四町作第一隧道(1902年開通) ― 2025年05月20日の続きも書いていなかった(泣)。【追記ここまで】
【写真】ささしまスタジオ(名古屋市中川区):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F8、絞り優先AE、1/125秒、ISO-AUTO(ISO 200)、AWB(6760K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)、専用フード、JPEGをリサイズ
ちょっと古そうだがイカす感じにリノベーションした建物を見つけて撮ろうとしたら、おねえさんが通りかかったので通り過ぎるのを待っていたら、中に入っていった。その日はなんかあるらしい。開いていた窓から、中に黒っぽい服を着た若い人が複数いるのが見えた。
なんか写真が暗いので、RAWからピクチャーコントロールとアクティブDライティング「標準」を適用してみた。ちなみにピクチャーコントロールを「風景」にするとシャドー部分が余計に暗くなるので、最新のピクチャーコントロールの「スタンダード」にした。まあ実際の現場は1枚目の写真の方に近いんだが。
【写真2】ささしまスタジオ(名古屋市中川区):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F8、絞り優先AE、1/125秒、ISO-AUTO(ISO 200)、AWB(6760K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)、専用フード、RAW(NEF)ファイルをNX Studio 1.7.1で最新のピクチャーコントロール「スタンダード」、アクティブDライティング「標準」で現像後Jpegに書き出してリサイズ
【追記:2025年6月25日】
Ai Nikkor 20mm F2.8Sで2m・F8にしたときもテストしてみました。
フィルムとデジタル撮影での被写界深度の違い(Ai Nikkor 20mm F2.8SとCOLOR-SKOPAR 21mm F4 P) ― 2025年06月25日
【追記ここまで】
ミッドランドスクエア(豊田・毎日ビルディング) ― 2025年06月10日 00時00分00秒
COLOR-SKOPAR 21mm F4 Pのスカッと晴れたときのパキッとした作例を撮りたいのだが、こんな季節なのでこれぐらいがせいぜい(泣)。
【写真】ミッドランドスクエア(豊田・毎日ビルディング)(名古屋市中村区):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F8、絞り優先AE、1/250秒、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(6050K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)、専用フード、JPEGをリサイズ
ちょっと黄色い感じがするのでホワイトバランスをいじろうと思ったのだが、何が正解か分からなくなったので、撮影時のAWB(6050K)のままのJPEG撮って出しをアップしている。
CONTAX G用のBiogon T* 21mm F2.8と比べて、COLOR-SKOPAR 21mm F4 Pの方はF8に絞ったままでニコンZ6のフォーカスピーキング機能を「標準」でフォーカスピーキングに従って撮ってもピントを外さないようだ。CONTAX G用のBiogon T* 21mm F2.8はF8に絞ってニコンZ6のフォーカスピーキング機能がピント合っているように色が変わっても、実際にはどこにもピントが合っていないということが頻発した。必ずEVFの拡大機能で確認してから撮影するようにしている。Fn1ボタンにEVF拡大を割り当てている。そういう意味でもCOLOR-SKOPAR 21mm F4 Pは撮影しやすいレンズだと思う。2007年の発売の対称型広角レンズ(ビオゴンタイプ)なのに、ちゃんとミラーレス機で使えているのもすごい(四隅に若干の色被りはあるが)。
デジタルとフィルムとで被写界深度が違う件のまとめはもう少しお待ちくだされ(ちょっと時間がない)。
【追記:2025年6月25日】
Ai Nikkor 20mm F2.8Sで2m・F8にしたときもテストしてみました。
フィルムとデジタル撮影での被写界深度の違い(Ai Nikkor 20mm F2.8SとCOLOR-SKOPAR 21mm F4 P) ― 2025年06月25日
【追記ここまで】
向野橋(こうやばし)(名古屋市中村区・中川区) ― 2025年06月09日 00時00分00秒
前から気になっていた名古屋の向野橋(こうやばし)に行ってきた。以前、シシド・カフカさん主演のNHKのドラマ「ハムラアキラ ~世界で最も不運な探偵~」(たぶん第6話)で映っていたので、寄ってみたいなと思っていたのだ。ドラマでは後ろに名古屋駅近辺の高層ビルが映っていたので場所はすぐにわかった。2020年のドラマなのでもう5年も経ったのか。
ドラマ10 ハムラアキラ ~世界で最も不運な探偵~(NHKアーカイブス)
向野橋(こうやばし)のトラス部分は、1899(明治32)年米国A&Pロバーツ社で製造され、1899年(明治32年)に京都鉄道によって保津川橋梁として京都の保津川に架橋されたものだった(後の山陰本線)。1928年(昭和3年)に架け替えられ、1930年(昭和5年)に跨線橋として名古屋市に移設されたようだ。保津川橋梁時代の1922年(大正11年)4月3日には保津川橋梁で列車の脱線転覆事故が発生し、損傷を受けたが修理されている。いまでもその損傷修理あとが残っている。
向野橋(なごやロケーション・ナビ)
向野橋(日本土木学会)PDF
名古屋の鉄道136年史(明治時代14)明治32年に作られた鉄橋を転用した向野橋(こうやばし)。(中京テレビ)
橋の下は、JR東海の名古屋車両区などになっていて(しかも近鉄名古屋線とJR関西本線と名古屋臨海高速鉄道あおなみ線も通っている)、鉄分の多い人には飽きない場所だ。
【写真1】向野橋(こうやばし)(名古屋市中村区・中川区):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F8、絞り優先AE、1/125秒、ISO-AUTO(ISO 200)、AWB(6620K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)、専用フード、JPEGをリサイズ
【写真2】向野橋(こうやばし)(名古屋市中村区・中川区):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F8、絞り優先AE、1/125秒、ISO-AUTO(ISO 180)、AWB(6610K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)、専用フード、JPEGをリサイズ
【追記:2025年6月25日】
Ai Nikkor 20mm F2.8Sで2m・F8にしたときもテストしてみました。
フィルムとデジタル撮影での被写界深度の違い(Ai Nikkor 20mm F2.8SとCOLOR-SKOPAR 21mm F4 P) ― 2025年06月25日
【追記ここまで】
今週のナナちゃん(ひとやすみナナちゃん) ― 2025年06月07日 00時00分00秒
COLOR-SKOPAR 21mm F4 Pの無限遠出ていないのではないか問題は、フィルムとデジタルの許容錯乱円の違いによる被写界深度の違いに寄る可能性が高いので、近いうちに記事にまとめます。
みっち様、コメントでのご指摘ありがとうございます。
ともかく、(フィルム向けの)被写界深度表示を当てにせず、ニコンZ6のフォーカスピーキング機能やピント拡大機能でピントを確認してバシバシ撮っていこうと思う。
【追記:2025年6月25日】
Ai Nikkor 20mm F2.8Sで2m・F8にしたときもテストしてみました。
フィルムとデジタル撮影での被写界深度の違い(Ai Nikkor 20mm F2.8SとCOLOR-SKOPAR 21mm F4 P) ― 2025年06月25日
【追記ここまで】
さて、いつもの名古屋のナナちゃんなのだが、「ひとやすみナナちゃん」ということで、これはスポンサーが付かなかった週のネーミングと衣装だ。
「ひとやすみナナちゃん」は、この2025年に入って4回目だと思う。しかも1週間ではなく2週間のときもあったので、「ひとやすみナナちゃん」の頻度が上がっている。2024年は1年で3回だったので、半年でそれを超えている。【追記:2025年6月8日】ナナちゃんコレクション | 名鉄百貨店 本店でちゃんと調べたら、いまの紺のワンピース以外の衣装の「ひとやすみナナちゃん」もあったようで、きちんと数えると2024年は8回の「ひとやすみナナちゃん」があったようだ。お詫びして訂正します。
| 年 | ひとやすみナナちゃんの回数 |
|---|---|
| 2025年(6月4日からの週まで) | 4 |
| 2024年 | 8 |
| 2023年 | 11 |
| 2022年 | 13 |
| 2021年 | 11 |
| 2020年 | 5 |
| 2019年 | 11 |
| 2018年 | 4 |
| 2017年 | 0 |
| 2016年 | 10 |
| 2015年 | 2 |
| 2014年 | 4 |
| 2013年 | 0 |
| 2012年 | 0 |
| 2011年 | 0 |
| 2010年 | 0 |
| 2009年 | 0 |
| 2008年 | 0 |
| 2007年 | 0※ |
| 2006年 | 0※ |
| 2005年 | 0※ |
| 2004年 | 0※ |
※印の年は、全ての期間のナナちゃんが掲載されていない。空白期が「ひとやすみナナちゃん」に相当する可能性がある。
うーん、ちょっとわからなくなってきた。すまん。 【追記ここまで】
日本の中でも景気がよいとされている名古屋でこの事態は、非常事態なのではないか。ちょっと心配だ。ナナちゃん経済予報の次回もお楽しみに(違)。
【追記:2025年6月26日】
追記時現在、ナナちゃんコレクションやナナちゃんについてなどのサイトがなくなって、名鉄百貨店のトップページに転送されるようになっている。大丈夫なのかナナちゃん。このあたりの大規模再開発の計画が出ていて、ナナちゃんをどうするのか心配の声が上がっている。
高崎社長: 「ナナちゃん人形は名鉄グループだけではなくて、街にも地域にも愛されている存在ですので、再開発にあたっても大切にしていきたい」
再開発後も「大切にする」とのことですが、具体的な保存方法は「検討中」としています。
長年、待ち望まれた名駅一帯の再開発計画でどんな姿に生まれ変わるのか、期待は膨らむばかりです。
高崎社長: 「名古屋の都心の街づくりに注力し、名古屋駅の担うところは『玄関口として新しい方向性を打ち出す』、そういった開発にしていきたい」
“ナナちゃん人形”の行方は…開発費用『5400億円』名鉄が名古屋駅前の再開発計画を発表 31階と29階建ての2棟(2025/03/24 21:01配信 東海テレビ)
ナナちゃんコレクション以下のページを復活するように強く要望したい。
【追記ここまで】
【さらに追記:2025年6月26日】
なんと、ナナちゃんコレクション以下のサイトのURLが変更になっている。だったら今までのページから新しいページに転送すればよいのに、どうして名鉄百貨店のトップに転送するのか。
新しいナナちゃんコレクションのURLは、
https://mds.e-meitetsu.com/nana/
だ。調べたところ、少なくとも2025年6月13日にはこのURLになっていたようだ。
【さらに追記ここまで】
【写真1】ナナちゃん(名古屋市中村区):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F8、絞り優先AE、1/125秒、ISO-AUTO(ISO 1100)、AWB(4870K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)、専用フード、JPEGをリサイズ
【写真2】ナナちゃん(名古屋市中村区):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F8、絞り優先AE、1/125秒、ISO-AUTO(ISO 1250)、AWB(5590K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)、専用フード、JPEGをリサイズ
Rayqual LM-NZマウントアダプター + COLOR-SKOPAR 21mm F4 P ― 2025年06月06日 00時00分00秒
精度が高いというRayqual LM-NZマウントアダプターが、爆速で出荷当日中に届いた。それでRayqual LM-NZマウントアダプターとCOLOR-SKOPAR 21mm F4 Pの組み合わせで撮ってみた。
懸念点は、Lomography Leica M - Nikon Z クローズアップマウントアダプターを使っても、焦点工房のLM-NZ II マウントアダプターを使っても、COLOR-SKOPAR 21mm F4 Pの絞りをF8に絞って2mの指標に合わせると、遠方にピントが来ていないことだ。COLOR-SKOPAR 21mm F4 Pの被写界深度表示に寄れば、2mに合わせると無限遠マークは「8」の表示よりも中心側にあり、被写界深度に入っているはずである。しかし、さきの2つのマウントアダプターだと無限遠どころか遠方の被写体にピントが来ていない。
それで、例の定点撮影場所、秋葉原の和泉橋からRayqual LM-NZマウントアダプター + COLOR-SKOPAR 21mm F4 Pの組み合わせで撮ってみた。
【写真1】秋葉原・神田川(和泉橋から神田ふれあい橋方向を望む):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F5.6、絞り優先AE、1/250秒、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(5820K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)、専用フード、JPEGをリサイズ、ピントは「神田ふれあい橋」に合わせてある
これまでこの場所からはF5.6で撮ることが多かったので、今回もF5.6で撮った。ピントはいつも通りに神田ふれあい橋に合わせたつもり。
球面平凸レンズ無しでこんな風に撮れるので、ミラーレス機のセンサー前ガラスの厚みによる像面湾曲の影響はあまりなく、ブルーグレイの色被りがあるぐらいだ。これはCornerFixでなんとかなる。
【写真1-1】中心部等倍切り取り:秋葉原・神田川(和泉橋から神田ふれあい橋方向を望む):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F5.6、絞り優先AE、1/250秒、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(5820K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)、専用フード、JPEGをリサイズ、ピントは「神田ふれあい橋」に合わせてある
【写真1-2】画面左等倍切り取り:秋葉原・神田川(和泉橋から神田ふれあい橋方向を望む):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F5.6、絞り優先AE、1/250秒、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(5820K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)、専用フード、JPEGをリサイズ、ピントは「神田ふれあい橋」に合わせてある
ここまではよい。
それで、F8で2mというスナップ的な使い方をするとどうなるか、だ。
【写真2】秋葉原・神田川(和泉橋から神田ふれあい橋方向を望む):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F8、絞り優先AE、1/125秒、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(6550K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)、専用フード、JPEGをリサイズ、ピントはレンズの2mの指標に合わせてある
F8・2mだと無限遠にピントが来ていないどころか、10~15mぐらいのところにもピントが来ていないぞ。なんてこった(泣)。
【写真2-1】中心部等倍切り取り:秋葉原・神田川(和泉橋から神田ふれあい橋方向を望む):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F8、絞り優先AE、1/125秒、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(6550K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)、専用フード、JPEGをリサイズ、ピントはレンズの2mの指標に合わせてある
【写真2-2】画面左等倍切り取り:秋葉原・神田川(和泉橋から神田ふれあい橋方向を望む):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F8、絞り優先AE、1/125秒、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(6550K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)、専用フード、JPEGをリサイズ、ピントはレンズの2mの指標に合わせてある
【追記:2025年6月7日】
この、距離指標に合わせて被写界深度表示に入らない現象は、デジタルとフィルムとでの許容錯乱円の違いによる可能性が高く、「故障」ではなさそうなので、取り消し線で消しておきます。
みっち様、コメントでのご指摘ありがとうございます。
この件は調べて別記事にする予定です。
荒野の故障ブログへようこそ(泣)。
ヨドバシドットコムで買ったレンズのピントがおかしいのって、やっぱり電話して交換してもらうしかないのかなぁ。参ったなぁ。これ、当たりが来るまで交換し続けるってこと?前のレンズに傷があったものとシリアルナンバー1番違いだから(同じ時に同じメンバーで製造した可能性が高い)嫌な予感がしたんだよなぁ。ヨドバシドットコムに電話してみるか(泣)。なんかこのブログ、皆様の期待を裏切らないよな(泣)。
ちなみに、同じコシナ製のCarl Zeiss Distagon T* 2/28 ZFは、ニコンZ6にFTZマウントアダプターで、無限遠突き当てて絞り開放で星にピントが合う。ボディ内手ぶれ補正があるので手持ちで星が撮れてしまう。だからボディがおかしい可能性は低いと思う。
【追記】ああ、でも、Distagonで星撮って以降にボディが狂っている可能性もあるから、いま他のレンズでも試してみる必要があるなぁ。MマウントはほかにLomoしかないので、FTZ経由で各種Fマウントの距離指標や置きピンで被写界深度内にピント来るかなど試しておく必要があるなぁ。いい加減ちゃんと写真撮らせてくれ~(泣)。
【さらに追記:19:23】
この記事のコメント欄でみっち様が、「許容錯乱円」がフィルムとデジタルとでは異なる可能性を指摘されて、試算してくださっています。
被写界深度考察 2016.04.21 Written by... FUJIFILM にも以下のように書かれている。
どこにピントを置くか、それは重要だ。どこまでピントを合わせるか、それも重要だ。しかしその基準は、きちんとあなたの目的・感覚に合わせてあるだろうか?
X-Pro2では、”被写界深度スケール”を”ピクセル基準 / フィルム基準”という2つの基準から選択できるようになった。これこそは、あなたの目的・感覚とカメラ設定をアジャストさせるための項目なのだ。
厳密なことをいうと、光学的にはピントが合っているは場所は、レンズ平面軸と平行なある一つの平面しかない。そこから1mmずれただけでもピントは合っていない。その面以外は”ボケ”ている。理論上は。しかし実際は、このボケ量が無視できるほど小さい場合は、ピントがあっているように見える。 そう”被写界深度”とは、ピントがあっている面とその前後にある(理論上はボケているのだが)、ボケてないように見える部分のことなのだ。
また、ピントから外れた面で発生するボケを”錯乱円”と呼んでいるが、ピントがあってるように見える程度の小さなボケを”許容錯乱円”と定義している。”許容錯乱円”が大きいほど、”被写界深度”は深くなる。つまり、”被写界深度”は”許容錯乱円”に比例する。
問題は、この”許容錯乱円”が、イメージャーの解像度や鑑賞媒体によって変わってくるということなのだ。
事実、昨今のデジタルセンサーは銀塩フィルムの解像力を超えており、許容錯乱円は小さくなっている。それに加え、ピクセル等倍表示がポピュラーになり、”許容”される錯乱円はさらに厳密になった。”浅く”なった”被写界深度”は、より厳密なピント位置・ピント範囲を追求するようになったとも言える。”ピクセル基準”の被写界深度は、そういった用途のためにある。
ということで、Rayqual LM-NZマウントアダプター + COLOR-SKOPAR 21mm F4 Pの組み合わせで絞り開放で無限遠が出ていれば故障ではないということだろう。無限遠が出ているのか確認できたら、あとはどの辺に距離を置いたらF8で自分の思う「ピントが合っている」になるのかを探す旅に出ればよいのだろう。
みっち様ご指摘ありがとうございました。
【さらに追記ここまで】
【追記:2025年6月25日】
Ai Nikkor 20mm F2.8Sで2m・F8にしたときもテストしてみました。
フィルムとデジタル撮影での被写界深度の違い(Ai Nikkor 20mm F2.8SとCOLOR-SKOPAR 21mm F4 P) ― 2025年06月25日
【追記ここまで】
【関連追記】
COSINA USERs にレンズの購入年月日等登録した ― 2025年05月24日
COLOR-SKOPAR 21mm F4 Pを新品で購入したが… ― 2025年05月25日 11時05分
COLOR-SKOPAR 21mm F4 P 交換品無事に届く ― 2025年05月25日 19時06分
富士フイルム、フィルム現像をスマホで完結できるアプリ「写ルンです+」を公開 ― 2025年05月29日
↑COLOR-SKOPAR 21mm F4 Pの作例1枚目
焦点工房のLM-NZ II マウントアダプター購入 ― 2025年05月29日
↑COLOR-SKOPAR 21mm F4 Pの作例2枚目
COLOR-SKOPAR 21mm F4 P 作例(3枚目) ― 2025年05月30日
COLOR-SKOPAR 21mm F4 P 作例(実質その4) ― 2025年06月03日
Rayqual LM-NZマウントアダプターが出荷された ― 2025年06月04日
↑COLOR-SKOPAR 21mm F4 Pの作例5枚目

























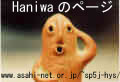

最近のコメント