今週のナナちゃん(ひとやすみナナちゃん) ― 2025年11月09日 00時00分00秒
今週のナナちゃんだ。今週は「ひとやすみナナちゃん」でちょっと寂しい。
ひとやすみナナちゃん(2025年11月 名古屋市中村区):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F5.6、絞り優先AE、1/40秒、ISO-AUTO(ISO 2000)、AWB(4580K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「ポートレート」、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)フィルター、専用フード
今回からニコンZ6のピクチャーコントロールを「ポートレート」にした。
ニッコール千夜一夜物語でも、佐藤治夫氏が以下のように書かれているからだ。
毎回の事ですが作例はレンズの素性を判断して頂くため、ピクチャーコントロールは輪郭強調の少ないポートレートモード等で撮影しました。また、あえて特別な補正やシャープネス・輪郭強調の設定は行わないようにしています。被写体は一般ユーザーがこのレンズを使用することを想定して選びました。撮影距離の遠近が網羅できるように心掛けました。
ニッコール千夜一夜物語 第九十五夜 Micro-NIKKOR C 5cmF3.5
私は、レンズの素性を判断するために撮影しているわけではないのだが、本願寺伝道院 ― 2025年09月07日以来、暗部が潰れるのが気になってきたからだ。
ニコンD300やD300Sではスポーツ撮影で、写っている人の表情がよく見えるようにポートレートにしていたのだが(身内に写真を配るため)、ニコンZ6ではスポーツ撮影しないので、ずっとピクチャーコントロール「オート」のままだったのだ。
こんどからはデフォルトを「ポートレート」にして、気に入らなければRAW現像していじることにした。
現場からは以上です。
赤城耕一の「アカギカメラ」 リコー「GR IV」 ― 2025年11月05日 00時00分00秒
最近、アサブロが異常に重く、「504 Gateway Timeout」が頻発するので、Twitter(現X)で数日前からASAHIネット障害アナウンス@AsahiNetStatusにメンション付けて、これは引っ越し先を探すしかないとつぶやいていたら、昨日あたりから急にアサブロが軽くなった。少し前にASAHIネットの技術担当とメールでやりとりした際には、記事数が多いブログはいかんともしがたいという返答を得ていたのに、やればできるんじゃないか。改善したのになんだかすっきりしないぞ。【追記】誤字とか修正したらやっぱり、「504 Gateway Timeout」になった。直ってないな。避難先を探そう。【追記ここまで】
さて、本題だが、今日はリコーGR IVの話題だ。いつも読んでくださる方は「あれ?HaniwaはもうGRからは撤退するから話題にもしないんじゃなかったのか?」と思われると思う。私ももうリコーGRには見向きもしないつもりだった。しかし、尊敬する赤城耕一先生のGR IVのレビューですよ、スルーするわけにはいかない。
赤城耕一の「アカギカメラ」第128回:王道にして最新。さらに迅速・高画質を求めたリコー「GR IV」(デジカメWatch)
いいですな、GR IV。欲しくなってしまう。歪曲収差をデジタル補正ではなく、レンズの光学系だけでなんとかしてしまおうという哲学は本当によい。素晴らしい。今回のGR IVは、GR IIIとはまた光学系が違っているようだ。
レンズ構成図をみてみますとGR IIIと似てはいますが、最後部に1枚増えて、4群6枚から5群7枚に刷新され、非球面レンズが2枚から3枚になっています。集光レンズやカバーガラスも改良され、より画面周辺まで光量を取り込み、画質が向上しているとアナウンスされています。GRシリーズはカメラ内の画像処理で歪曲収差補正をしておらず、このあたりも光学設計者の気合いというか実直さを感じますね。
公表されていますMTFを見てみますと、周辺までほぼ一直線で、てっぺんを維持します。いわゆる天井に張りつくという形状に近いですから、光学レンズの理想性能に近いものです。当然、鮮鋭性に優れ、画像の均質性に優れることを意味しています。
すばらしい。ただ、GR IVは、ヨドバシドットコムで¥194,800(税込)もするので、私はちょっと買えない。頑張ったら買えない価格でもないのだが、うちにあるGR DIGITAL初代もGR初代も7~8年で起動すらしなくなってしまったので、7~8年で壊れてしまうようなカメラに20万円は出せない。GR初代の方は、最初は鏡筒内部のフォーカシングで動くレンズ部分が、ガガガガと滑るようになってピントが合わないことが増えてきたのだったが、最期には起動すらしなくなってしまった。GR DIGITALはAFの故障はなかったが、最期は起動しなくなった。なんか寂しい。いずれもずっと持ち歩いていたものなので、捨てずに取ってある(写真参照)。
今回の赤城耕一氏の記事で気になったのは、以下の部分だ。
もっとも、筆者はワイドコンバーター装着したままの超広角専用GRとして、初代GRを現在も愛用しています。
そうか、そういう使い方があったか。と思ったが、中古のGRってほとんど見かけないし、あっても高いんだよね。高い中古を買って、保証期間が切れた1年後ぐらいに壊れるとか、精神をやられそうなので手を出しづらい。
このところ、GR IIIの中古が急に出てきたが、16,7万円もする。それって、新品時のGR IIIよりも高くないか?まあ抽選販売とかしていたから、台数がそんなに出ていないんだろうなぁ。GR IIIは抽選販売にしていなかったら、おそらく何かの拍子にポチッと逝っていたと思うが、抽選販売だったしかなり高くなっていたので冷静になってしまい縁が無かった。
ということで、せっかくの赤城耕一先生のレビューだが、私はもうGRを買うことはないと思う。愛用していたし、GRの代わりはGRしかないと思うが、もう買えない。さようならGR。
赤城耕一の「アカギカメラ」 第127回:ニコンZ で、DタイプFマウントニッコールをAF化する!? ― 2025年10月20日 00時00分00秒
ニコンFマウントのカップリングAFレンズをニコンZボディでAF(オートフォーカス)できる「MonsterAdapter LA-FZ1」を赤城耕一氏が詳細なレポートをしてくださっている。
赤城耕一の「アカギカメラ」第127回:ニコンZ で、DタイプFマウントニッコールをAF化する!?(赤城耕一 2025年10月20日 07:00)
「なぜ、マウントアダプターFTZを使用しても、ニコンFマウントニッコールのDタイプ、SタイプのレンズがAFで動作しないのか!」と、Zシリーズ発表当初から噛みついて、ニコンの皆さまからは嫌われてきた筆者です。だからLA-FZ1が登場したことは無上の喜びであり、落涙を抑えきれないほど感激したわわけです。
「おまえ、そうまでして、古いAFニッコールをZに装着し、AFで使いたいのかよ?」と言われそうですが、「はいそうです」としかお答えのしようがありません。
だって、FマウントのDタイプ、SタイプのAFレンズが筆者の手元にたくさんあるわけであります。
筆者の家では原則として「絞り環のないFマウントニッコールは購入してはならぬ」という厳しい家訓があるものですから、一部を除けば、レンズ内にモーターを搭載しないAFニッコールであるD、Sタイプのレンズが多くなるわけですね。また距離指標や絞り環のない土管みたいなZレンズを愛でるというのもあまり面白くありません。
はい、正直に申し上げればこれらは言い訳で、貧しい年寄りの写真家には小商いしかありませんから、高性能高額の新型Zマウントレンズを簡単には購入することができないのです。
手持ちのFマウントレンズの多くを売り飛ばしても、悪い冗談みたいなお値段にしかなりませんから、Zマウントレンズを購入するには多額のお金が必要になります。ならばZボディでも流用したいと考えるのは当然のことであります。
冒頭から場外ホームラン(場外ファウル?)を連発してくださる赤城耕一氏。素敵です。
私なんか、カップリングAFのAI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED <NEW>やAI AF Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4-5.6DがニコンZ6 + FTZでAF(オートフォーカス)できないものだから、安く出ていたAF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDという絞り環のないレンズに手を出してしまった。しかし、ニコンZ6でAF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDを使うと遠景では非常に残念な画質なので、結局Z6でマニュアルフォーカスでAI AF Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4-5.6Dを使ってみたり、Z6導入前のようにD300SでAFで使ったりするという愚を犯している(泣)。
筆者を勇気づけたのは、ソニーから発売されたAマウントレンズをEマウントカメラに装着できるマウントアダプターLA-EA5でした。LA-EA5は、モーター非内蔵のAマウントレンズを使用してもAF撮影が可能という利便性の高いものでした。
したがって、同じモーター非内蔵のDタイプ、Sタイプニッコールも、やろうとおもえばモーター内蔵のFTZアダプターさえ用意されさえすればAF撮影が可能になるはずですが、待てど暮らせど、AF駆動モーターを内蔵したFTZアダプターは登場しません。
はたしてそれで生まれたのがLA-FZ1であります。MonsterAdapter ブランドのマウントアダプターは、各メーカーのカメラ、レンズの相互互換を実現した各種アダプターを多く用意しています。
カメラメーカーにとっては旧レンズばかり使用されてしまうことになるわけですから、利益率の高いとされる交換レンズが売れなくなってしまうのは少々困るかもしれませんが、ユーザーとしては経済性や利便性を求めるのは当たり前のことでしょう。非常に言いづらいですが、筆者は「ニコンが本来やるべきことをMonsterAdapter が実現した」というふうにもとれるわけであります。
このあたりはチクチクとニコンを責めてくださっています。「待てど暮らせど、AF駆動モーターを内蔵したFTZアダプターは登場しません」私もその気持ちです。「待てど暮らせど」という気持ち、ニコンにはわかりますかね。「ニコンが本来やるべきことをMonsterAdapter が実現した」という言葉の重みをニコンは受け止めてほしい。
ある意味、旧来からのニコンユーザーにとってはLA-FZ1は夢のアダプターのようでありますが、筆者は真実を追求するジャーナリストなので、きちんと報告しますが、最初に感じた印象を述べれば、今回使用した限りにおいては、LA-FZ1はまだ夢のマウントアダプターではなくて、あいみょんの唄じゃないけど少々「雑なサプライズ」ということになります。
そう、すべてのDタイプ、Sタイプのニッコールにおいて、完全なAF挙動はまだ望むことができないということです。
赤城耕一氏の正直な報告だ。以下、輸入元の焦点工房が発信している注意書きの説明などがある。
Monster Adapter側からも現時点でAFが動作するニッコールレンズ対応表がアナウンスされています。なお対応しているレンズでも、挙動が怪しいものが多々あることはお伝えしておきます。
MonsterAdapter LA-FZ1 firmware v1.00 対応レンズ / Supported Lenses List
他のサードパーティー製のレンズやアクセサリーを使う時と同じことです。心の安寧を常に求める人、カメラの動作に神経質な人にはオススメできません。2度と撮り直しのできないもの、特に重要な撮影には使用しない方がいいでしょう。
これも重要な点ですな。身内のスポーツ撮影にMonsterAdapter LA-FZ1とニコンZ6とで撮影したりして、いいシャッターチャンスにフリーズして撮れなかったとか目も当てられない。自分の使い方だとこれはお散歩で気まぐれにスナップ撮るような撮り方に使うのがよい。でも、お散歩にAI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED <NEW>持ち出すか?といわれたら、このレンズを買ってからかなり長く使っているが、散歩に一度も持って行ったことはない。やっぱり要らんアダプターなのか(泣)。
大事な撮影にはFTZでちゃんと撮らねばなるまい。そう考えると、前にも書いたが、カップリングAFでAF作動するマウントアダプターよりもマウント面が前後してAF作動するマウントアダプターの方がいいのではないかという気がしてきている。マウント面が前後するAFアダプターは、マウントアダプターとカメラとの間の通信はするが、マウントアダプターとレンズとの通信はない。AFレンズだろうがMFレンズだろうがレンズごと前後してピントを合わせるからだ。そうなるとレンズとの相性は電気的にはない。相性があるとすればIFやRFといった全群繰出し式ではないピント合わせ方式を用いたレンズでレンズ本来の性能が出ない可能性があるということだけだ。だったらとっととそのマウント面が前後するAFアダプターを買えばよいのだが、焦点工房で発売しているそのてのマウントアダプターは1年以上ファームアップが止まっているようなので、買うのを躊躇しているのだ。いつまでもサポートしろとは言わないが、サポートが終わったのなら新しいのを発売してほしい。
さて、赤城耕一氏のMonsterAdapter LA-FZ1レポートに話を戻すと、レンズごとに報告がある。これはありがたい。
目次
AF NIKKOR 24mm F2.8D
AF NIKKOR 28mm F2.8D
AF NIKKOR 35mm F2 D
AF NIKKOR 85mm F1.8 D
AF Zoom NIKKOR 20-35mm F2.8D IF
AF VR Zoom NIKKOR 80-400mm F4.5-5.6 D ED
AF Micro NIKKOR 60mm F2.8 D
私の持っているレンズは1本も入っていない(泣)。でも多くの人が持っているレンズが並んでいるので、貴重な情報だ。たとえば、AF NIKKOR 24mm F2.8Dは以下のようだ。
AF NIKKOR 24mm F2.8D
コンパクトで取り回しの良いレンズです。LA-FZ1との相性は25点かな。残念。頻繁に異常を検知した旨のアラートが出ます。またAF-Sモードに設定しているのにフォーカスが合焦していないのにシャッターが切れたり。個体差なのでしょうか。チリチリした描写ではないので好きなんですけど残念です。
正直です。赤城耕一氏の好みの焦点距離である35mmのAF NIKKOR 35mm F2 Dは、
筆者が愛してやまないレンズなんですが、LA-FZ1との相性も素晴らしく良くて、アラートは出ませんでした。90点をつけます。ほとんど動作的な不安もないのですが、鏡筒内の動作音が少々うるさい。じつはNIKKOR Z 35mm f/1.8 Sが高性能すぎて、どうにも困ったなあと思っていたところでしたから喜んでいます。
とのこと。「NIKKOR Z 35mm f/1.8 Sが高性能すぎて、どうにも困ったなあ」という考え方もあるのだな。自分はAi Nikkor 35mm F2Sを愛用していたのだが、フィルムやD300Sで絞り開放でも滲まないのに、Z6で使うと絞り開放で滲んでしまい萎えていたのだが、赤城耕一氏のように考えればよいのだな。気を取り直してまたAi Nikkor 35mm F2Sを使ってみよう。このレンズの絞り開放での描写が好きだったのでちょっと使い方を変えないとダメだが。
ということで、MonsterAdapter LA-FZ1の今後の発展と、「ニコンの改心」に期待したい。
写真は記事とは関係ない。
秋葉原・神田川(和泉橋から神田ふれあい橋方向を望む):Nikon Z6、SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ、18mm(35mm版換算27mm相当)、絞り優先AE(F6.3固定、1/160秒)、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(6860K)、APS-C(DX)フォーマット、マルチパターン測光、マニュアルフォーカス(MF)距離●2m、ピクチャーコントロール:オート、手ぶれ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、フィルターなし、フード(37mm→30mmと30mm→37mmリング2段重ね)、Jpegをリサイズのみ
ニコンのレンズでない作例ですまん。SG-image 18mm F6.3は、NIKKOR Z 28mm f/2.8(Special Edition)よりもシャープに写っているようにみえる。まあAPS-Cサイズにしてさらに四隅が暗黒なんだけれども。こういうレンズはニコンはNIKKOR銘で出せないんだろうなぁ。だったら「おもしろレンズ工房Z」とかで出せばいいのに。「つまんねー奴だなぁ」(チコちゃんの声で)。
Titanセキュリティキーが壊れた ― 2025年10月15日 00時00分00秒
荒野の故障ブログへようこそ(泣)。
Google謹製のTitanセキュリティキー(Model: K9T (USB-A/NFC))というのを、Googleアカウントにログインするときの2段階認証の一つの手段として使っていた。しかし、このあいだ使おうとPCのUSB端子に刺したら、「USBデバイスが認識されません このコンピューターに最後に接続されたUSBデバイスが正しく機能していないため、Windowsによって認識されていません。」というメッセージが出て、認識されないのだ。同じPCのほかのUSB端子に刺しても同様で、PCを再起動しても同じ。他のPCに刺してみたら同じメッセージが出るので、これはGoogleのTitanセキュリティキーが壊れたのだと判断した。
このTitanセキュリティキーModel: K9T (USB-A/NFC)は、USB Type-Aで薄いのでずっと小銭入れにいれて持ち歩いていた。
故障の原因は、おそらくバスの料金箱のFelicaのタッチではないかと推測していた。どうしてSuica、PASMOのタッチで壊れたと推測するかというと、昔バスカードがあったときに、バスに乗るときはバスカード(5千円で5850円分乗れる優れものだった)、電車に乗るときはカード型Suicaというのをやっていて、Suicaの入った財布にバスカードを入れて改札でタッチするとバスカードの情報が消えたことが何度かあるからだ、そのたびにバス会社の定期券発行所まで行って再生してもらった(バスカードは使った記録が裏に印字されていたので残額が分かって再設定してもらえたのだ)。定期券販売所の人も手慣れたもので「また改札機でバスカード壊した人が来た」という感じだった。バスカードが廃止されたからすっかり忘れていた。
このTitanセキュリティキーModel: K9T (USB-A/NFC)って4千円もしたのになぁ。いま新しいのをみたら5625円になっていた(泣)。買って2年半ぐらいしか経ってなかった(泣)。
それで、こんどは財布には入れないで持ち歩くので、分厚いのでもいいかとUSB Type-Cの方を選んだ。しかし、これは失敗だったかも。USB Type-AのTitanにはUSB Type-A→Type-Cのアダプターが付いているが、Type-Cのセキュリティキーにはアダプターは付いていないのだ。というかType-CオスをType-Aに変換するアダプターは規格外なのであった。これじゃ、USB Type-Aしかない古いPCでGoogleのログインをしなければならないときに困るなぁ。自宅のリビングのPCにはType-Aしかない(買い換え予定)。
そこで、規格外と知りつつ、YOUZIPPER ユージッパーType-C 変換アダプタ APX-ACというのを買った。880円だった。セキュリティキーをPCに刺すのに使う分にはよいが、モバイルバッテリーのType-Cに刺して反対側をこの変換アダプタでPCのType-Aに刺したりすると、両方から給電されておかしなことになってしまうので危険だ。このセキュリティキーをPCに刺すとき以外には使わないようにテプラを貼っておこうと思う。
なお、TitanセキュリティキーModel: K52T (USB-C/NFC)は、こんどは家の鍵と一緒に付けておくことにした。
なお、壊れたセキュリティキーは、セキュリティ キーの使用を中止するの「2 段階認証プロセス」のところからGoogleのアカウントとの紐付けを削除した。ログインするときにはセキュリティキー以外の2段階認証でログインする(スマホとかメールとか)。
それで、古い方の壊れたTitanセキュリティキーModel: K9T (USB-A/NFC)をよく見ると、なんだか反っている。金色の接点のある側が凸になるような感じ。それでこのプラスチック製のTitanセキュリティキーModel: K9T (USB-A/NFC)のそりを戻す方向にむにゅっと曲げたりしてみた。もう一度PCに挿入すると、なんと認識されるではないか。もう新しいTitanセキュリティキーModel: K52T (USB-C/NFC)を買ってしまったぞ(泣)。
ただ、何度もむにゅむにゅ曲げたりしていると、何回かに一回はまた「USBデバイスが認識されません このコンピューターに最後に接続されたUSBデバイスが正しく機能していないため、Windowsによって認識されていません。」というメッセージが出るので、これは使うのをやめた方がいいな。いざというときに認識されない恐れがあるし、中の基板が浮いたりしているのだろう。
届いたTitanセキュリティキーModel: K52T (USB-C/NFC)の方をGoogleアカウントに紐付けようとすると、PINを設定しろといわれる。回避方法はその時点ではない。そしてPINを設定すると面倒なことに、Googleの2段階認証の際にこのTitanセキュリティキーModel: K52T (USB-C/NFC)を刺すと、PINを入力しろと言われるのだ。いままでのTitanセキュリティキーModel: K9T (USB-A/NFC)の方は、PCに刺して金属の部分をタッチするだけでGoogleにログインできたのに、新しいTitanセキュリティキーModel: K52T (USB-C/NFC)の方だと、PINを入力してから金属部分にタッチしろといわれる。これはかなり面倒くさい。しかもこのPINはWindowsセキュリティが要求しているっぽい。Windows11の設定のアカウントのサインインオプションのセキュリティキーのところからPINを削除したりできるが、そうするとせっかくGoogleに紐付けたセキュリティキーが「不正なセキュリティキー」といわれてしまう。仕方ないので、セキュリティキーをGoogleカウントから削除して、もう一回登録し直した。その際にまたPINの登録も要求される。Windows11からセキュリティキーを登録するからPINを要求されるのではないかと思ってWindows10のPCからもやってみたがうまくいかなかった。そういうことを何度もしていたらGoogleアカウントがロックされてしまった(泣)。これはスマホからすぐに解除できた。
なお、個人的なGoogleアカウントは、新しいTitanセキュリティキーModel: K52T (USB-C/NFC)を使うことで、パスワードの入力は省略できるがPINの入力が求められるようになった。しかし、仕事で割り当てられているGoogleアカウントは管理者がパスワードレスにすることを許可していないらしく、セキュリティキーを挿入してもパスワードが要求される。この場合にはなぜかPINは要求されない。古いTitanセキュリティキーModel: K9T (USB-A/NFC)ではどちらのアカウントもパスワードが要求されていたので、結局セキュリティキーだけでログインされるのを防ぐためにPINが要求されているのだろうか。
新しいTitanセキュリティキーModel: K52T (USB-C/NFC)はPINを要求されて面倒なので、結局、古いTitanセキュリティキーModel: K9T (USB-A/NFC)ももういちど登録し直して新しいTitanセキュリティキーModel: K52T (USB-C/NFC)とは併用することにした。新しい方は分厚いのでキーホルダーに、古い方は薄いので今までどおり財布にいれることにした。
なお、TitanセキュリティキーModel: K52T (USB-C/NFC)に禁断のYOUZIPPER ユージッパーType-C 変換アダプタ APX-ACを付けて、PCのtype-AのUSBポートに刺してもちゃんと認識されてGoogleアカウントにログインできた。
この規格外のType-Cメス→Type-Aオスのアダプターは、Type-A側から給電したり、双方向のデータに使う分には問題がないが、Type-C側から給電するような接続をすると、おそらくType-A側の機器が壊れるので注意が必要だ。両端Type-CのケーブルにこのYOUZIPPER ユージッパーType-C 変換アダプタ APX-ACを付けて、Type-A側をPCに、Type-C側をスマホにしたら、ちゃんとandroidスマホに充電できてスマホのファイルもPCからみえた。Type-C側にモバイルバッテリーなどをつないでType-Aで接続しないように気をつけないといけない。
【写真】右から、Type-Aメス→Type-Cアダプター(TitanセキュリティキーModel: K9T (USB-A/NFC)に附属のもの)、TitanセキュリティキーModel: K9T (USB-A/NFC)、新しいTitanセキュリティキーModel: K52T (USB-C/NFC)、別途買ったYOUZIPPER ユージッパーType-C 変換アダプタ APX-AC(Type-Cメス→Type-Aオスアダプター:USBの規格外)
なお、セキュリティキーをどうして持っているのかというと、Googleの2段階認証でスマホを忘れたりスマホが壊れたり無くしたりしたときにログインできなくて困るからだ。一応Gmail以外のメールアドレスも2段階認証に登録しているが、スマホも自分のPCもなく、そこにある端末でGoogleにログインしなければならないときに、セキュリティキーがあれば2段階認証ができるからだ。2段階認証には複数手段あった方がよくて、そのうちの一つがセキュリティキーなのだ。あんまり使うことがない割にはちょっと値段が高いけど。
また、セキュリティキーは、海外に行く人も持っているとよいという例がTITANセキュリティーキー買ってみた(Softbank security blog パブリッククラウドエンジニア 淺沼 太輔 2023年4月13日掲載)に書かれていた。
尚、筆者は海外旅行に行くことが好きで過去に海外に行ったタイミングでGoogleアカウントの再認証を求められ、SMS認証のみ入れていたので認証できない目に会ったことがあります。海外に渡航されたことがある方はご存じかもしれませんが、日本のキャリアのローミングサービスなどをオンにせず現地でツーリストSIMなどで通信を行った場合は日本の電話番号やSMSが使えません。この様に、日本の電話番号で二段階認証をかけているとGoogleアカウントのログインに困る事があります。海外出張されることが多いビジネスマンなども同様にトラブルに巻き込まれた際には物理キーがあると非常に便利です。
【参考】
Google「Titan セキュリティキー」ってどう使うの?NFCによるスマホ利用にも対応(PC Watch 山口 真弘 2022年12月1日 06:31)
Titan Security Key - FIDO2 USB-A/USB-C + NFC
【追記:2025年10月16日】
そういえば、「海外に行く人は、クレジットカードや銀行カードの2段階認証をSMSではなくメールにしておいた方がいい」と言っている人もいた。海外にいくときに普段使っている携帯の電話番号のSIMを海外でもローミングで使っているのならよいが、現地のSIMを買って入れている場合に、クレジットカードや銀行カードの2段階認証を求められて、上記のGoogle2段階認証のSMSが届かないのと同じ目に遭う可能性があるからだという。普段はSMSにしていても、海外に行く前にメール認証に変更してから出掛けるといいという。SMS認証にしていて現地SIMだと海外でクレジットカードや銀行カードがロックされて詰むらしい。Haniwa家もIIJmioを使っていて海外ローミングサービスはないので、注意しないといけない。
【追記ここまで】
なお、Titanセキュリティキーの互換性は以下を参照。
Titan セキュリティ キーについて
iOS バージョン 13.3 以降を搭載した iPadはNFC非対応のようだ。
セキュリティを強化する
ジャーナリストや活動家など、標的型オンライン攻撃の危険性が高い立場にある方は、高度な保護機能プログラムで Titan セキュリティ キーを設定してセキュリティを強化されることをおすすめします。
いやいや、「ジャーナリストや活動家」でなくても「高度な保護機能プログラム」やったほうがいいよ。いつなんどき「貴様!さては、Haniwaだなっ!」みたいな目に遭うとも限らない(違)。
ニコンZ6 の静止画モードで「i メニュー」に撮影範囲設定登録できました(追記あり) ― 2025年10月09日 00時00分00秒
ニコンZ6で、APS-Cサイズ用のMFレンズSG-image 18mm F6.3を使っていて、撮影範囲を変更するときに、「i メニュー」に撮影範囲設定を登録できないとこのブログのあちこちで書いていましたが、今日たまたま検索したらZ7/Z6 の静止画モードで、i メニューをカスタマイズする方法というニコンのサポートQ&Aに「i メニューに割り当てられる機能は次のとおりです。」とあって、筆頭に「撮影範囲設定」がありました。ニコンZ6は「i メニュー」に「撮影範囲設定」が登録できます。お詫びして訂正致します。m(_ _)m
【追記:2025年10月12日】
「i メニュー」に「撮影範囲設定」が登録できるが、U1、U2、U3(ユーザーセッティングモード)の場合には、「i メニュー」に登録した「撮影範囲設定」は電源をOFFにすると消えて初期設定に戻る。これは説明書にははっきりとは書かれていないが、Z7/Z6 で U1、U2、U3(ユーザーセッティングモード)を設定する方法には、
※ 下記のメニュー項目は登録はできません
< 静止画撮影メニュー >
記録フォルダー設定
撮像範囲設定
カスタムピクチャーコントロール
多重露出
インターバルタイマー撮影
タイムラプス動画
フォーカスシフト撮影
とあるのと関係しているのだろう。
だったら、最初から U1、U2、U3(ユーザーセッティングモード)時には「i メニュー」に撮像範囲設定を設定できなければよいのに、しれっと登録できて、電源OFFにしたら元に戻っているというたちの悪い仕様になっている。
U1、U2、U3(ユーザーセッティングモード)は、ISO感度を自動にしておくと、焦点距離の短いレンズは最低シャッタースピードが1/焦点距離(mm)秒にされてしまって被写体ブレが頻発するので、下限を決めたり下限を高めにするために使っていたが、撮像範囲設定を記憶してくれないので、かえって何がU1、U2、U3(ユーザーセッティングモード)で記憶されていて、何が記憶されていないのか分からなくなってしまうので、使うのをやめようと思う。特にしれっと「i メニュー」に登録できて電源OFFで登録が消えてしまうという挙動が気に入らない。ヽ(`Д´)ノ←既に何に怒っているのか忘れている
【追記ここまで】
これで、SG-image 18mm F6.3と他のレンズをとっかえひっかえで使っても安心だ。以前やろうとしたときはどうしてみつからなかったのだろう。もしかしたら、「i メニュー」に登録する画面で、「撮影範囲設定」は一番上にあるので、途中のメニューに設定されていて下にしかスクロールしなくて見過ごしていたのかもしれない。ともかくすまんです。書き散らかしたところは見つけ次第訂正しておきます。m(_ _)m
写真は記事とは関係ない。
Air India(羽田空港第3ターミナル):Nikon D300S、AI AF Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4-5.6D、145mm(35mm判換算217.5mm相当)、F5.6、1/2000秒、ISO-AUTO(200)、専用フードHB-15、Nikon L37Cフィルター、AWB、ピクチャーコントロール:スタンダード、マルチパターン測光、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、JPEGをリサイズ
D300SにMB-D10を付けないで、AI AF Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4-5.6Dを持って行くのが、自分の機材の中では一番軽量で簡便な望遠撮影だ。AI AF Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4-5.6Dは、ZシリーズとFTZの組み合わせではAF撮影ができないが、74x116mmでコンパクトだ。重さは505gでそんなに軽くはないが70-300mm F4~というクラスの中ではまあ軽い。「望遠撮影する予定がないが念のため」というときにAI AF Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4-5.6Dはカバンの隅に入れて持って行きやすい。あとから、AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED も手に入れたが、AF-Sの方は、ニコンZ6では2,30m先以上の距離で画質がよくない(またJR久留里線上総亀山駅に行ってきた ― 2024年06月21日とAF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDは遠景が弱い ― 2024年08月06日とJR久留里線上総亀山リベンジ ― 2024年12月18日参照)。近距離ではAF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED(2006年12月発売開始)は、AI AF Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4-5.6D(1998年3月発売開始)と見分けは付かない画質なのだが。
カメラマンリターンズ#14でのニコン原田壮基氏 ― 2025年10月06日 00時00分00秒
みっち様のコメントへのお返事を書いていて、「間違いだらけのレンズ選び2025 カメラマンリターンズ#14」の記事をずっと書こうと思ってそのままになっていたのを思いだした。ピクチャーコントロールについては、ピクチャーコントロール:間違いだらけのレンズ選び2025 ― 2025年09月08日で書いた。
編集部: ところでZ 50mm f/1.2 Sはどこまで絞るのは許せますか?
原田: 私は絞らないんで分かりません。
編集部: それはニコン公式ですか?
原田: もちろん、私個人の見解です。
森田:開放で撮れ。
原田: どんなレンズでも、最初のテストで絞って特性を見る以外、基本絞って撮ることはありません。写りがどうであろうと絞りは要らないと思っています。絞る、という行為が身についていないというか・・・。子供を連れて公園に行っても、ずっと露出オーバーなので撮れないんです。だから早く夕方にならないかなぁって(笑)
阿部:原田さんと一緒に50mm F1.2のメカ設計をやってくれたナカノさんって若い人がいるの。彼に原田さんは絞りなんて要らないって話をしたら、絞りを設計した当の僕も本当は要らないと思っていますって(笑)
森田:洗脳されてる。
【引用者註】原田:原田壮基 氏(ニコン・光学設計)、阿部:阿部秀之 氏(写真家)、森田:森田浩一郎 氏(カメラマン編集部/スタッフ)
(間違いだらけのレンズ選び2025 カメラマンリターンズ#14 モーターマガジン社 41ページ)
原田氏はそう言ってるのだが、同じページの下に原田氏の撮影した写真が載っており、その横には、
撮影者
株式会社ニコン 光学本部
原田壮基これまで多くの機種を一緒に開発してきたメカ設計者さんを会社のそばの公園で撮影しました。Z50/1.2でこの日、午前は長男の高校入学式を撮影し、夜はこのレンズの開発に関わった方を撮影。自分が開発に関わったレンズで身近な人たちを撮影できる、この仕事の醍醐味です。
撮影レンズ: NIKKOR Z 50mm f/1.2 S(光学設計を担当)
撮影情報
絞りF8 1/25秒 プラス0.5露出補正
ISO200 WB: オート(間違いだらけのレンズ選び2025 カメラマンリターンズ#14 モーターマガジン社 41ページ)
絞りF8、おーい、絞っとるやないかいっ。
写真が小さいので、F1.2開放なのか、F8なのかはよく分からない。もしF1.2だったら後ろの建物の明かりの点いた窓はもっとボケているような気もする。やっぱりF8で撮っているんじゃないのかっ。これは大菩薩峠で(以下略)。
あと、この「間違いだらけのレンズ選び2025 カメラマンリターンズ#14」で気になったのは、以下の部分。
阿部: ないものねだりの時間みたいなんで。僕もひとつ。是非DCニッコールを復活させてください(笑)
原田:わー、来ましたね。私もそれやりたいです。
阿部: 毎回言うんだけど、大事なことなので今回も言います。キヤノンにやられちゃったのが超悔しい! (笑)
原田: ここから先はオフレコで。(オフレコ)
編集部: いやー(笑)。やっぱりカットですかね。
阿部: DC ニッコールはニコンの宝です。
原田: 絶対にやりたいですね。私はDCニッコールを見てニコンに入ったので。
編集部: コシナのポートレート HELIAR はどうなの?
豊田:ユニバーサルヘリアー登場100周年を記念したレンズということで、ヘリアークラシックをベースに、できるだけ球面収差だけをコントロールしようと努カし、描写を楽しむコンセプトです。ですから厳密なDCコントロールというよりは、楽しさ重視だと思います。だから内部の可動域も大きいワケで。
阿部:だよねー。そんな簡単には作れないから。
山田:でもね。あえて言わせて。そこはやはり、製品として出てるかどうかの方が重要だと思う。出てもいないものを「できる」って言われても、ふざけるなっていうのが本当のところだから。そんなにいいって言うんだったらディスコンにするなよ、っていうのも本音だし
原田:私が定年退職するまでDCに関わりたいなぁ・・・と願っています。可変収差レンズには夢があります!
阿部: いっそ、PlenaにDC機構を入れるってのは?
山田:そっちいくと絶対買えない値段になるからやめて!(笑)
【引用者註】阿部:阿部秀之 氏(写真家)、原田:原田壮基 氏(ニコン・光学設計)、豊田:豊田慶記 氏(写真家)、山田:山田久美夫 氏(写真家)
(間違いだらけのレンズ選び2025 カメラマンリターンズ#14 モーターマガジン社 40~41ページ)
DC NIKKORは、原田氏が定年になるまでに関わりたいとのこと。期待したい。というか、また話は戻ってしまうのだが、Ai AF DC Nikkor 135mm F2DなどのカップリングAFレンズを、ニコンZボディでAF可能にしなさいよ、ニコンは。
【関連】
ピクチャーコントロール:間違いだらけのレンズ選び2025 ― 2025年09月08日
ニコン開発者インタビュー - NIKKOR Z 50mm f/1.2 S(PHOTO YODOBASHI)
NIKKOR Z 50 mm f/1.2 Sの開発 原田 壮基, 中野 拓海(日本写真学会誌84 巻 (2021) 3 号 p. 182-186)
写真は記事とは関係ない。
名古屋三井ビルディング北館と名古屋モード学園(名古屋市中村区):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F8、絞り優先AE、1/125秒、ISO-AUTO(ISO 280)、AWB(8070K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)、専用フード、RAW(NEF)ファイルをNX Studio 1.8.0で最新のピクチャーコントロール:ポートレートで現像
カップリングAF(ボディ内AFモーター)のNikkorレンズでAF可能なMonsterAdapter「LA-FZ1」国内発売 ― 2025年10月03日 00時00分00秒
焦点工房からAFモーター内蔵のニコンFマウントレンズ →ニコンZマウント変換 MonsterAdapter「LA-FZ1」発表 ― 2025年02月22日で期待していた、MonsterAdapter「LA-FZ1」がついに国内発売だそうだ。
DタイプニッコールレンズでAFが可能 モーター内蔵のニコンZボディ用マウントアダプター MonsterAdapterから「LA-FZ1」が発売(デジカメWatch 2025年10月3日 11:32)
いつもはデジカメWatchと同じようなタイトルで記事にしているのに、今回は違うのは、デジカメWatchの「DタイプニッコールレンズでAFが可能 モーター内蔵のニコンZボディ用マウントアダプター 」というのは不正確だからだ(ニコ爺砲炸裂)。
Dタイプというのは、AFの方式を表してはいないので、たとえばPC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D がMonsterAdapter「LA-FZ1」でAFが可能になるわけではない。PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8Dは、マニュアルフォーカスなのだ。
それはさておき、MonsterAdapter LA-FZ1(ニコンFマウントレンズ→ニコンZマウント変換)電子マウントアダプター 販売開始 Posted:2025年10月3日(焦点工房)を見てみよう。
特長
・初期AFニッコールおよびDタイプレンズ(モーター非内蔵)でAE/AF撮影が可能。
・画面の広い範囲で像面位相差AFが動作。
・各種被写体検出機能や顔検出・瞳AFに対応。
・カメラのボディ内手ブレ補正機構に対応。
・アダプター側面のスイッチでAF/MFの切り替えが可能。
・撮影画像の焦点距離、露出などの撮影データはExif情報として記録。
・アダプターのファームウェアアップデートが可能。
※初期ファームウェアでは、AF-I/AF-S/AF-P(モーター内蔵レンズ)、電磁絞り(Eタイプ)、レンズ内手ブレ補正には非対応です。今後のファームウェア更新で対応となる場合がございます。
対応機種(2025.10.3 発売時点)
初期AFニッコールおよびDタイプレンズ(モーター非内蔵)
Z5、Z5II、Z6、Z6II、Z6III、Z7、Z7II、Z8、Z9、Zf、Z30、Z50、Z50II、Zfc
※対応カメラやレンズについては、AF動作確認リストまたは、メーカーオフィシャルサイトにてご確認ください。
とのことだ。また、ここでも「初期AFニッコールおよびDタイプレンズ(モーター非内蔵)でAE/AF撮影が可能」なんて書いてる。PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED とMonsterAdapter「LA-FZ1」とでAFが可能になる日が来るのかと、大菩薩峠で(以下略)。
気になる価格は、デジカメWatchによると6万9,000円。なんか高いぞ。この値段だったら、D750の並品中古が買えてしまうやん。ただ、焦点工房の直販だと55,800円 (税込)なので、許せてしまう。
さてさて、どんなものかインフルエンザじゃなかったインフルエンサー様の先行レポートを拝見しよう。
そして、前にも書いたが、カップリングAFがあまりうまくいかないのであれば、マウント面が前後するAFアダプター(たとえばTECHART TZM-02(ライカMマウントレンズ → ニコンZマウント変換)電子アダプター AF対応にニコンFマウント→ライカMマウントのアダプターを重ねる)で、カップリングAFのAFニッコールを使った方が便利かもしれない。IF方式やRF方式などのレンズだと本来の性能が出ないかもしれないが、マニュアルフォーカスで近くまで持って行っておいて最後にAFで合わせるなどすれば、そんなに性能劣化しないのではないかという気がする。またこの組み合わせだとMFレンズもAFで作動するので、カップリングAFのニッコールの一部しかAF作動しないLA-FZ1よりも有利だ。そこら辺がちょっと微妙な感じもするが、みんなで大事に育てようMonsterAdapter「LA-FZ1」。
Windows 10を1年間延命できる「ESU」の登録をしてみた ― 2025年10月02日 00時00分00秒
いよいよWindows10のサポートが2025年10月14日で終了する。Windows11のハードウェア要件を満たすPCはWindows11に移行すればよいが、満たさないPCは買い換えるしかない。それで、Windows10のサポート期限までに買い換えるつもりでいた。しかし、一向に仕事が一段落せず、次にどんなPCを買うのか全く検討しないままに10月になってしまった。高い買い物なのに慌てて変なものを買ってしまいそうだ。
それでどうしたものかと思っていたら、タダで「Windows 10」を1年間延命できる「ESU」の登録が開始されたので試してみました 一般的な環境ではお盆以降にも利用できるようになるはず 樽井 秀人 2025年7月25日 06:45という記事を見つけた。
「拡張セキュリティ更新プログラム」(Extended Security Update:ESU)は、サポートが終了したOSに対して有償でセキュリティパッチを提供する取り組みです。大量のデバイスを抱えていたり、動作検証などに膨大な手間がかかる組織では、後継OSへ移行したくてもすぐには難しいことがあります。ESUはそうした環境向けに時間的猶予を与えるもので、本来は基本的に法人向けですが、「Windows 10」に関しては特別に、個人向けにも提供されます。個人向けの価格は年間30米ドルに設定されていますが、以下の条件のいずれかを満たせば、無償で1年間利用できるとのこと。
・「Windows バックアップ」で設定をクラウドに同期する
・「Microsoft Rewards」のポイント1,000と引き換え後者は日頃から「Bing」などを利用しなければ達成できませんが、前者はそれほど難しくないので、実質無料と言えるでしょう。
なお、ESUへデバイスを登録するには以下の要件を満たす必要がある点には注意してください。
・「Windows 10 バージョン22H2」のHome、Professional、Pro EducationおよびWorkstationエディションを実行しているデバイス
・最新のアップデートがインストールされていること
・「Microsoft アカウント」にサインインしたデバイス(ESUライセンスは「Microsoft アカウント」にに紐づけて管理される)条件を満たした環境ならば、「設定」アプリの[更新とセキュリティ]-[Windows Update]ページに、ESUへの登録を案内するメッセージが表示されるはずです。[今すぐ登録]をクリックして、ESUへの登録を開始しましょう。
我が家のリビングの共用PCは、もはや骨董品のDELL Vostro 430 Intel Core i5 750、RAM 16GB、Cドライブ 500GB SSD、Dドライブ 12TB HDD、NVIDIA GeForce GT220 973MB、Windows10 PRO 22H2だ。
Microsoft Rewardsは1000ポイントいってなかったが、Windows バックアップでOneDriveにバックアップを取ったら、ESUの条件を満たした。なお、OneDriveはMicrosoft 365 Familyに入っているので、家族が各自1TBのOneDriveを使えることになっている。今回のバックアップにどのくらい容量を使っているのかわからないが、OneDriveの使用ファイル量が全然増えていないので、どこにバックアップを取っているのかよくわからない。わからないが、必要なファイルは自分で外付けHDDにバックアップを取っているので問題なしだ。
ということで、2026年10月13日までWindows10の拡張セキュリティ更新プログラムが提供されることになった。時間ができ次第次のデスクトップPCを選定したい。
【関連】
Windows 10 コンシューマー向け拡張セキュリティ更新 (ESU)(マイクロソフト)
写真は記事とは関係ない。
【写真】大阪市中央公会堂(2025年8月):Nikon Z6、AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED、F8 絞り優先AE、1/400秒、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(5300K)、マルチパターン測光、 オートエリアAF、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、自動ゆがみ補正、手持ち撮影、マウントアダプターFTZ、バヨネットフード HB-72、ニコンNCフィルター、Jpeg画像をPhotoshop Elements 6.0で「レンズ補正」垂直方向修正&トリミング
2万7,000円の広角シフトレンズ「AstrHori 18mm F5.6 Shift」 ― 2025年09月12日で、ちょっとシフトレンズがほしくなってしまったが、超広角レンズで絞ってかっちり撮った後に画像処理アプリでいじるとどうなるかやってみた。うん、シフトレンズ要らんな(笑)。
名鉄百貨店本店の「垂直落下タイプ」エスカレーター ― 2025年10月01日 00時00分00秒
もう10月になってしまった。今日は涼しいが、まだ暑い日も多く、秋の感じがしない。さて、今回は、名古屋・名鉄百貨店本店の「垂直落下タイプ」エスカレーターの話だ。
名鉄百貨店本店周辺は、再開発が予定されており、名鉄百貨店本店も2026年2月28日で閉店になるらしい。
ビルは約400mの一続きに…名古屋駅“5400億円の再開発プロジェクト” 閉店決めた百貨店等のこれまでと今後(2025/04/18 16:57配信 東海テレビ)
名鉄百貨店本店が2026年2月28日をもって閉店。名古屋駅前の再開発は本格進行へ。
それで、名鉄百貨店本店にある、珍しい「垂直落下タイプ」エスカレーターも見納めになるというので、撮ってきた。
何が珍しいかというと、エスカレーターの手すりが入っていったり出てきたりする下部の部分が、丸くなっているのではなく、床の中に垂直に出入りしているところだ。「日本で3基しかない」うちの2つが名鉄百貨店本店にあるそうだ。しかし、残りのもう1基は「東宝ツインタワービル(1969-2019)」にあったそうなのだが、東宝ツインタワービルは2020年解体済みなのだそうだ。となると、この名鉄百貨店本店の東芝製「垂直落下タイプ」エスカレーター2基が「最後の2基」ということになる(このあたり、検索すると「世界で3基」とか「日本で3基」とかあってよく分からないが、少なくとも日本に3基あったうちの1基は既になく、この名鉄百貨店本店の2基が日本で最後の東芝製「垂直落下タイプ」エスカレーターのようだ)。
【写真】東芝製「垂直落下タイプ」エスカレーター(名鉄百貨店本店、名古屋市中村区):Nikon Z6、Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 P、F8、絞り優先AE、1/125秒、ISO-AUTO(ISO 2000)、AWB(4830K)、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス(MF)、手ぶれ補正ON(ノーマル)、高感度ノイズ低減:標準、ピクチャーコントロール「オート」、手持ち撮影、Rayqual LM-NZマウントアダプター、Kenko PRO1D plus プロテクター(W)、専用フード、Jpegをリサイズ
フルサイズ対応の超広角レンズ「TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH」が安くて気になる ― 2025年09月27日 00時00分00秒
アサブロが重いのは、ASAHIネットの技術担当者と少しやりとりして、若干改善はしているが、根本的には解消していないし、担当者も根本的な改善は難しいという。何よりも困るのが、アサブロ管理画面の「記事の編集・削除」がタイムアウトして開けないことだ(これは10年以上前から指摘しているのに、ASAHIネットはずっと「そんなことはない」と言い続けてきた)。ASAHIネットは、調整はしたが「対象ブログの管理画面には多くの記事が登録されているため、より一層負荷の影響を強く受けてしまっていたと考えられ」るといっている。この画面が開けないと、一旦公開した記事の修正ができないので、タグの打ち間違いなどHTMLの表示に重大な間違いがあったときに困る。そこで、ログインしたのちに、「記事の編集・削除」から各記事の修正画面にはいるところ、ログイン後に直接各記事の修正URLを指定して各記事の修正画面に入ることにした。URLの末尾は、公開されているURLの末尾と同じ数字と記号だからだ。そういうごまかしをしながらも、このブログを快適に続けるにはどうすればよいのか考えなければならないところに来ているようだ。
さて、タイトルの「フルサイズ対応の超広角レンズ「TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH」が安くて気になる」の話題に入ろう。
デジカメWatchにフルサイズ対応の超広角レンズ「TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH」 前面にレンズフィルターを装着可能 本誌:折本幸治 2025年9月26日 13:25という記事があり、記事中には、デジカメWatchにしては珍しく価格の表記がない。調べると、焦点工房のオンラインショップで37,800円税込のようだ。
銘匠光学 TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH 大口径広角レンズ
銘匠光学 TTArtisan には(※)もうひとつ、七工匠 7Artisans 14mm F2.8 単焦点レンズ52,200円税込というのがあって間違いやすいが、今回気になる方も、52,200円の方もマニュアルフォーカスで、どちらも非球面レンズを使っているので、何がどう違うのかわかりにくい。※【追記】TTArtisanと7Artisansってどちらも焦点工房が輸入元なので同じ会社だと思っていたが、これは違う会社だね。すまん。【追記ここまで】
仕方ないので比較表を作ってみた。
| レンズ名称 | TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH | 7Artisans 14mm F2.8 |
|---|---|---|
| 対応撮像画面サイズ | 35mmフルサイズ | 35mmフルサイズ |
| 焦点距離 | 14mm | 14mm |
| レンズ構成 | 10群13枚(ASPH非球面レンズ2枚、高屈折レンズ2枚) | 9群13枚(ASPH非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚、高屈折レンズ5枚) |
| 絞り | F2.8-F16 | F2.8-F22 |
| 絞り羽根 | 8枚 | 10枚 |
| 最短撮影距離 | 0.2m | 0.43m |
| フィルター径 | 77mm(付属フィルターホルダー使用) | 77mm |
| サイズ(マウント部除く)ニコンZ用 | 約Φ65×79mm / 質量:約468g | 約Φ79×82mm / 質量:約507g |
| 付属品 | 前後キャップ、フィルターホルダー | 前後キャップ フィルターホルダー |
| 直販サイトでの価格(税込) | 37,800円 | 52,200円 |
うーん、どっちの方がいいのか分からん。
↑TTArtisan 14mm f/2.8 ASPHの方のレンズ構成(左)、MTF曲線(右)だ。
TTArtisan7Artisans 14mm f/2.8 の方のレンズ構成だ。MTFはみつからなかった。【追記】Official 7Artisans Storeで7Artisans 14mm f/2.8 のMTFを見つけた。しかし、7Artisansの方はどの線が何なのかの定義がないため、「MTF風グラフ」(雰囲気)になっている(泣)。↓【追記ここまで】
どちらのレンズ構成図も、 水色:高屈折レンズ 桃色:ASPH(非球面)レンズ 黄色: ED(特殊低分散)レンズのようだ。
歪曲収差がよく補正されているかあるいは素直な樽型で、2段絞ったF5.6あたりから四隅までシャープなのであれば、一本欲しいなとは思う。ただ、作例を見ても歪曲収差のよく分かる作例はささそうだ(泣)。あと、どっちの方が上位なのかよくわからんのもよくない(※)。後から出た安い方が下剋上なのか、それともEDレンズ使わない安価なバージョンなのか。どちらも非球面レンズ使っているのに、後から出た方だけASPHがついているのもなんかすっきりしない。ちょっと様子見ですな。もっと作例カモーン!※【追記】上記追記でも書いたが、TTArtisanと7Artisansとは別メーカーのようだ。こりゃ、ますます使っている人のインプレとかみないとどっちがいいのかわからんな。【追記ここまで】
14mmといえば、ニコンだとNIKKOR Z 14-30mm f/4 Sがあって、これはいずれ買いたいと思ってはいる。
あと、AI AF Nikkor 14mm f/2.8D EDがあった。これはM/Aリングの付いたカップリングAFのものなので、Nikon ZでFTZやFTZ IIを使ってもオートフォーカスはできない。Fマウントの14mmはAF-Sのものがないうちに終了してしまったようだ。【追記】このAI AF Nikkor 14mm f/2.8D EDって、定価は272,250円もしたが、最終的にヨドバシで168,280円(税込)だったようだし、中古品は6~7万円※であるようだ。だとすると、かさばって出目金レンズだが、AI AF Nikkor 14mm f/2.8D ED買う方がいいかもね。ただし、AI AF Nikkor 14mm f/2.8D ED中古品の出物は少ない。なお、「AI AF Nikkor 14mm f/2.8D ED」は、かつて「Ai AF Nikkor ED 14mm F2.8D」と表記されていた。 【追記ここまで】【さらに追記】※AI AF Nikkor 14mm f/2.8D EDはもう少し程度のいいものだと10万円ぐらいするみたいだなぁ。やっぱり世の中そんなに甘くない。【さらに追記ここまで】
あと、Ai AFで思い出したが、焦点工房扱いのMonsterAdapter「LA-FZ1」はどうなったのだろうか。ニコンZボディでAi AFなどのカップリングAFが可能なマウントアダプターだ。「不具合修正を経て9月中旬に発売」という情報のまま、もう9月下旬なのだが。これも、VRが効かないとかAF-SやAF-IはAFが動作しないなどの制限があるらしいので、だったらLeica M
マウントでAF可能なアダプターにLeica M→Nikon Fのアダプター2段にして使った方がいいような気もする。VR内蔵のレンズでVR(手ぶれ補正)が動作しないということは、ニコンZボディ内蔵のVRは効くのか効かないのか不明だからだ。ニコンZ内蔵のVRは、VR無しレンズの場合はボディ単体でVRが効く仕様だが、レンズ内蔵のVRが効かないということは、ボディ単体のVRが効かない可能性がある。そうするとMFレンズやカップリングAFレンズだとボディ内VRが効くのに、このMonsterAdapter「LA-FZ1」でボディ内VRが効かないという後退した状況になる。仕様がよく分からないので、これも楽しみにしつつ、ちょっと様子見。頑張って欲しい。
【関連】
ニコン「Zf」のシルバーモデル9月26日(金)に発売 ― 2025年09月05日
焦点工房からAFモーター内蔵のニコンFマウントレンズ →ニコンZマウント変換 MonsterAdapter「LA-FZ1」発表 ― 2025年02月22日
【関連追記:2025年10月3日】
カップリングAF(ボディ内AFモーター)のNikkorレンズでAF可能なMonsterAdapter「LA-FZ1」国内発売 ― 2025年10月03日














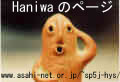

最近のコメント